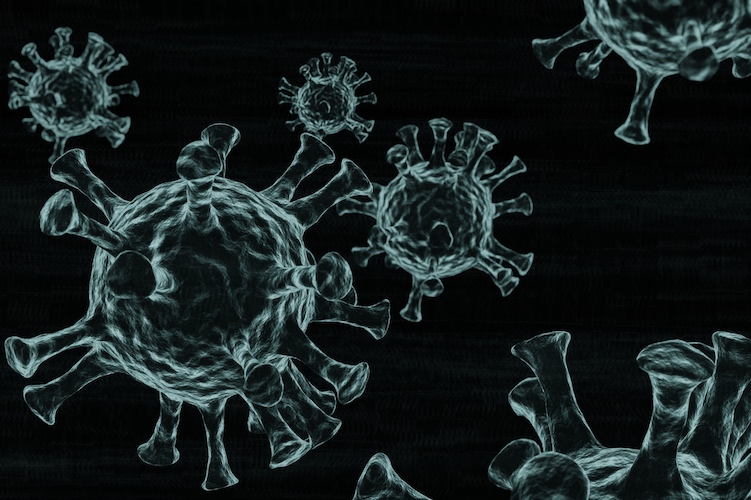【連載/第5回】
誰がパリ五輪に抵抗しているのか ?
Qui luttent contre les Jeux Olympiques 2024 de Paris ?
佐々木夏子
監視資本主義・テクノポリス(Technopolice)
近年のオリンピックは(無観客開催といった異常事態にでもならない限り)、開催国にとって「平時最大の治安維持作戦」となることが避けられなくなっている。
それ以前と以後でオリンピックの警備体制が大きく変わったマイルストーンとなっているのが、1972年ミュンヘン五輪 *1と、2001年のアメリカ同時多発テロ事件だ。ミュンヘン五輪事件の一因に選手村の警備の甘さを指摘する声は小さくなかった。それを受けて4年後のモントリオール五輪は「以後オリンピックの規範となる、きわめて大がかりな治安維持作戦が展開された初の大会」となった、とアルバータ大学の社会学者、ドミニク・クレマンは分析する。モントリオール五輪の警備予算は、クレマンの計算によると5200万ドルとなっており、ミュンヘン五輪の200万ドルから「劇的に増額」したのだった。
しかし時代は1970年代である。対ミュンヘン比で2500%増加となった警備費の内訳を詳しく見てみると、モントリオール市警の超過勤務手当やカナダ他州から動員された警官の出張経費(交通、宿泊その他)が大半となっている。テクノロジーは前面に出ておらず、モントリオール五輪を「監視カメラ(CCTV)が広範に、かつ体系的に使用された初のオリンピック大会」*2 とする分析はいささか大げさ、とクレマンは論じる。「カナダ連邦警察は監視カメラを10数台ほど購入したに過ぎず、さらにそれらは警備においてそれほど重要な役割を担ったわけではなかった」*3 とのことだ。
翻って2001年のアメリカ同時多発テロ事件以降のオリンピックは、最先端の治安維持テクノロジーの見本市という性格も持つようになる。2002年冬季五輪は、同時多発テロからわずか数ヶ月後に、当時PTSD状態にあった米国で開催されることになっていた。このタイミングで、アメリカ国家安全保障局(NSA)が組織的パニックを起こしていたことは想像に難くない。それにエドワード・スノーデンの告発後の世界を生きる私たちは、NSAの監視網の規模を知っている。監視資本主義が成熟しきる2017年まで待たされることになる、NSAの元諜報員によるソルトレークシティ冬季五輪における大量監視の告発は、それがたいして話題にならなかった、という点にこそ注目すべきであろう。この元スパイ、トーマス・ドレイクによると、NSAは「電子メールやSMSを含む、ソルトレークシティ発、あるいはソルトレークシティに向けられた、事実上すべての電子コミュニケーションを収集・保管」*4 していたとのことだ。それに対するNSAの言い分は食い違っている。NSAによると、外国のテロリスト集団との関与が合理的に疑われる国際通信に限った監視であった、とのことだ。しかし仮にドレイクの告発ではなくNSAを信じるにしても、スノーデン以前にそんなことが明らかになっていたなら結構な問題になっていたはずである。
ソルトレークシティから2年後の2004年アテネ五輪は、オリンピック開催都市が要塞と化した初の事例と分析されることが多い。アテネがオリンピック開催都市に選ばれたのは1997年、つまりテロ対策がまだオブセッションとなっていなかった「911以前の世界」のことである。911を挟んで世界は様変わりした。けれどもギリシャのような小国に、様変わりした「世界標準」に短期間で追いつくことは不可能である。そこで最大の選手団を派遣する米国が大規模な介入に乗り出したのだ。
エドワード・スノーデンが大量にリークしたNSAの機密文書の一つに「アテネ五輪に向けた信号情報部(SID)のトレーニング(SID Trains for Athens Olympics )」*5 と題されたものがある。2003年8月15日付の同文書には、NSAが84年ロサンゼルス五輪以降オリンピックへの関与を高めており、ソルトレークシティではFBIと共同で「オリンピック諜報センター(Olympic Intelligence Center)」を運営し「大会前と開催中に脅威警報と状況認識を提供するため、外国諜報活動と法執行を融合」した、と記されている。そして米国外での開催となる2004年アテネ五輪に向けても、NSAは「国際大会で前例のない、大きな役割を担うことを見越して2004年の大会に向けて準備中」であり、大会一ヶ月前までに10名の分析官が現地に派遣される予定だ、と述べられている。
アテネ五輪を「スーパーパノプティコン」とする監視システムの基幹となったのは、NSAから大型契約を受注 *6 する米国の民間軍事企業、SAIC(その後Leidosに改名)社が開発したC4I(Command control communication computer intelligence)システム *7 であった。「疑わしい隣国」*8 に囲まれ、「初のポスト911オリンピック」の開催国として信頼されていなかったギリシャは、高額な軍事技術をアメリカに売りつけられる格好となったのである。最終的にアテネ五輪がミュンヘンやアトランタ *9 のような惨事と化すことはなかったが、その功績をSAIC社のC4Iシステムに帰することはできない、と論じるのはクレタ大学の社会学者、ミナス・サマタスである。サマタスによると、ギリシャ政府が2億5500万ドルも支払ったSAIC社のC4Iシステムには技術的・官僚的問題が相次ぎ、ほとんどなんの役にも立たなかった、とのことである。まずシステム納品が大幅に遅れた。仕様書に問題が見つかっても、SAIC社とギリシャ政府の間で円滑なコミュニケーションはできなかった。そして何よりもC4Iのソフトウェアシステムに相次いだ技術的問題(ソフトウェアとハードウェアのインターフェース不備、80人が同時にログインすると発生するクラッシュ…)こそが「SAIC失敗の根本的な原因」であった。結果、ギリシャ防衛省を中心とする「従来の警備手段」つまり人海戦術がアテネ五輪の警備の中心となったのである *10。
最終的にアテネ五輪の警備費用は15億ドルに達した。これはシドニー五輪の1億7960万ドルから831%の増加となっている *11 。そして外国の軍事関連企業が暴利を貪った「スーパーパノプティコン」は、アテネ五輪が残した最大の「レガシー」となって後続の大会を規定したのだった。
北京五輪(2008年)を挟んでアテネから8年後に開催されたロンドン五輪は、「Olympic Security」という巨大分野の存在を世に知らしめ、この言葉を一般名詞として人口に膾炙させることになった。警備を受注した世界最大の民間警備保障会社、G4S社が必要な人員を集められなかったため、軍隊が追加動員をかけることになり、同社に賠償金支払いが命じられた顛末は日本でも詳しく紹介されている *12 。元々大量の監視カメラによって知られ、「世界でもっとも監視されている都市」と言われているロンドンは、五輪開催決定直後の同時多発テロ(2005年)を経てさらにその傾向を推し進めることになった(パナソニックだけで大会に向けて監視カメラを2500台を納入)。高額の費用をかけて設置された監視カメラが、オリンピック閉幕とともに役割を終えて撤去される、なんてことはもちろんありえない。その4年後のリオ大会は、本連載第4回で既述のとおり、過剰な治安維持による人権侵害の横行した大会となって世界中から批判を浴びた。
2021年に開催された東京オリンピックも、本来ならばこの流れに沿うはずだった。事実、五輪開催を名目に2017年に可決された「共謀罪法」のように、日本社会を不可逆的に変えてしまった「レガシー」もある。2018年になると「東京2020ゴールドパートナー」であるNECの開発した顔認証技術の大会での使用が発表されたが、当時日本でこの点について議論が活性化することはなかった。サンフランシスコ市が警察その他機関による顔認証技術の使用を禁止するのはその翌年、ショシャナ・ズボフの『監視資本主義の時代』(野中香方子訳、東洋経済新報社)の邦訳が出版されるのはそれから3年後の2021年のことである。「東京五輪が初の顔認証導入五輪となる」という重みを受け止める準備は、2018年時点の日本社会にはなかった、と言ってよいだろう。
そしてコロナ禍によって東京五輪の延期が決定すると、顔認証技術を使った体温測定や、防犯カメラによる移動経路の記録・感染者追跡の展望についての報道 *13
が出てくる。最終的に東京五輪は無観客開催となり、こうした一大監視スペクタクルが実行に移されることはなかったけど「初の顔認証導入五輪」という足跡はしっかり残された。NECはこう自慢している:
選手やスタッフ、ボランティアなどの全大会関係者を対象に競技会場、選手村、大会関連施設であるIBC(国際放送センター)/MPC(メインプレスセンター)等の入場時における本人確認を行う顔認証システムを納入しました。 具体的には、ICチップを搭載したアクレディテーションカードと事前に撮影・登録した顔画像をシステム上で紐付けし、大会会場、施設における関係者エリアの入場ゲートに設置した顔認証装置を用いて、顔とアクレディテーションカードによる厳格な本人確認を行いました。また、顔認証装置は、アクレディテーションカードを読み取り機に着券すると即座に顔認証を行うため、スムーズな認証が可能です *14。
パリ五輪開催にともなう監視強化を危惧するフランスの人権団体などがもっとも危惧していたのは、このような事態がパリでも、特に観客相手に展開されることだった。たとえばフランスのウェブメディア『ランディマタン』が2021年1月26日に掲載した「2024年だけでなく今後もずっと、オリンピック・ビッグ・ブラザーに反対(NI EN 2024, NI JAMAIS : NON AU BIG BROTHER OLYMPIQUE)」*15 という意見記事で特に強く表明されているのは、オリンピックの生み出す「例外状態」においてリアルタイム顔認証技術がフランスでなしくずし的に許可されてしまうことへの懸念である。
結論から先に書いてしまうと、パリ五輪における顔認証の導入は(2023年現在では)見送られている。関係者による最初期の公言は、2021年10月12日にパリ政治学院(Sciences Po)で開かれたラウンドテーブル(本連載第3回参照)の場での、オリンピック・パラリンピック競技大会閣僚間代表、ミシェル・カドの発言である。その一ヶ月後には大手メディアが、パリ五輪に顔認証は導入されない、と報道 *16 するようになった。パリ五輪組織委のこうした判断の背景となっているのは、この技術をめぐる議論の活性化である。NECの自慢話しか聞かされなければひたすら便利なだけだと思ってしまいそうだが、顔認証技術が孕む深い問題はここ数年で世界的に広く共有されるようになっている。
サンフランシスコ市が警察による顔認証技術を禁止した理由の中には、技術の不正確さ、特に有色人種が対象になると認証精度が落ちる「人種的バイアス」というものがあった。顔認証技術について丁寧な報道を行なっている米ニューヨークタイムズ紙は、2018年2月9日に「顔認証は正確である、もしあなたが白人男性であるならば(Facial Recognition Is Accurate, if You’re a White Guy)」*17
という記事を出している。これはもちろん、白人男性を対象にした場合の顔認証の正確さを讃えるために書かれたものではない。この技術がいかに人種差別的でいかに当てにならないか、という批判が主旨である。しかしそれからわずか4年後の2022年5月26日にニューヨークタイムズが出した記事は「誰もが使える顔検索エンジンが、危険なほど正確になっている(A Face Search Engine Anyone Can Use Is Alarmingly Accurate)」*18 という見出しである。人工知能の飛躍的な発達により顔認証技術もここ数年で急速に改善され、それとともに技術をめぐる議論も社会モデルを問う根源的なものとなった。個人の顔という公共空間に曝けだされる生体情報で、「Shazam」*19 のような真似が可能になる社会をわれわれは望んでいるのか、と。
フランスを含むヨーロッパでは、こうした議論はアメリカ以上に活発である。フランスのデータ保護監督機関である「情報処理および自由に関する全国委員会(Commission nationale de l’informatique et des libertés、以下CNIL)」は、顔認証技術を専門とする米Clearview AI社 *20 に、EU一般データ保護規則(以下GDPR)違反の廉で2千万ユーロの罰金を命じている(2022年10月)。こうした流れの中で、パリ五輪組織委員会は顔認証技術の採用を(今のところ)見送っているのだ。しかしそれで一息ついたのも束の間、2022年末になると治安維持に関する条項が大半を占める「新オリンピック関連法案(projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)」*21 が報道されるようになる。同法案の中でもっとも論議を呼んでいるのが、AIアルゴリズム搭載(あるいは「スマート」)監視カメラの利用を許可する第7条である。同条文第一項では「2025年6月30日まで実験的に」と留保をつけた上で、「テロや大事故のリスクがとりわけ高いスポーツ大会、娯楽・文化的催し物の安全性確保を目的とする限りにおいて」、「イベント会場やその周辺、および交通機関や道路に設置された監視カメラによって収集された画像を、人工知能システムを含む処理の対象とすることができるようになる」と定められているのだ。
AIアルゴリズム搭載監視カメラは「異常検知」と呼ばれることもある。従来型の非AIアルコリズム搭載(あるいは「おバカ(dumb)な」)監視カメラが、視野に入った情報をひたすら垂れ流すだけで事後的な使用(例:カメラに映った犯罪者の追跡)を前提としているのに対し、AIアルゴリズム搭載監視カメラは予防的な対応を可能とする。どういうことか。スマート監視カメラは、ディープラーニングによって学習した「異常な行動」を認識した時点で警告を発し、人間の介入を要求するのだ。「異常な行動」には、たとえば人間が突然座り込んだりとか、路上で複数の人間が集合したりとか、そういったことも含まれる。
フィリップ・K・ディックの短編、および同作をスティーブン・スピルバーグが映画化した『マイノリティ・リポート』の世界では、「プリコグ」と呼ばれる予知能力者を使った犯罪予防が行われている。3人の「プリコグ」の内2人(マジョリティ)が犯罪を予知すると、事件を未然に防ぐために警察が介入するのだ。私たちが生きる現実の2023年の世界はSFではないので「プリコグ」は存在しない。しかし監視カメラにAIアルゴリズムを搭載するという発想は『マイノリティ・リポート』の犯罪予防局のそれに限りなく接近したものである。要は犯罪が行われる前に「疑わしきを排除する」ことを可能としよう、というものだ。言うまでもなく、この発想は近代司法制度の根幹に対立している。
多くの法律家が危惧しているのは、この技術を内面化した人間が自らの振る舞いを技術に合わせて律することである。ジル・ドゥルーズが言うところの「モグラの巣穴よりもはるかに複雑にできている」「とぐろを巻くヘビの輪」*22 に、個人が過剰適応してしまう世界だ。たとえば空港のような場所における身振りの抑制は、当たり前のものとなってすでに久しい。しかしその拡張を──「安全性」と引き換えに──私たちはどこまで受け入れるべきか? たとえばロックコンサートのような場で、人口知能が想定する「異常な行動」を控えるような世界に生きることを、私たちは望んでいるのだろうか?
今年1月31日にフランスの元老院が同法案を賛成多数(賛成245票、反対28票、棄権64票)で可決した数日後に、仏ル・モンド紙は「2024年オリンピック:フェスティバルに落とされる監視の影」と題された記事を出している:
スマート監視カメラは規範を逸脱する身振りに取り組む。けれどもベルフォール市で開催される音楽祭「ユーロケエンヌ」の主催者、ジャン=ポール・ロランはこう問うのだ。「アルゴリズムはウォール・オブ・デス〔ロックコンサートで見られるモッシュ〕をどう解釈するのだろう?」ポゴダンスや芸術的パフォーマンスなど、異常とされる身振りの検知はフェスティバルの精神自体に反するものとして経験されるのかもしれない。「フェスティバルとは、異常行動こそが規範となっている空間なんだ」とその道のプロは主張するのであった*23。
ウォール・オブ・デスはその名の通り危険であり、Wikipediaによると「過去に死者が出たこともある」*24
らしい。危険の回避を至上価値とするならば、アルゴリズム搭載監視カメラの認可は歓迎すべき「レガシー」であろう。ロシアのウクライナ侵攻を受けてUEFAチャンピオンズ・リーグ決勝戦のサンクトペテルブルクでの開催が急遽スタッド・ド・フランスに変更となり、フランス警察が世界中に見せてしまった無様な警備失敗劇を繰り返すことはできない、というプレッシャーもある。元老院の老政治家たちだけでなく、フランスの民意も概ね「新オリンピック関連法案」に好意的であるのは、安全性を重視する価値観が強力であることを示している。問題の一つは、東京オリンピックが初の顔認証オリンピックとなった際にそうであったように、技術をめぐる功罪についての議論が熟していない内に不意打ち的に決定されることなのだ。今後同法案は、3月21日から国民議会で審議された後、可決される見通しである。
本稿執筆時(2023年2月)においてフランスでもっとも熱心に同法反対キャンペーンを展開しているのは、ラ・クアドラチュール・デュ・ネット(La Quadrature du Net、以下LQDN)というデジタル権利に取り組む市民団体である。LQDN発足のきっかけは違法ダウンロードを厳しく取り締まる2009年のHadopi法 *25 であり、初期においては知的所有権の過剰保護を批判し、「インターネットと自由」*26 を擁護していた。LQDN発足から2014年までスポークスパーソンを務めていたジェレミー・ジマーマンは、LQDNの前にはフリーソフトウェア推進団体Aprilに所属しており、2012年には電子フロンティア財団から表彰されている。
しかし時の流れとともに「インターネットと自由」が意味するところは大きく、そして急速に変わっていく。2010年代にはオンライン監視技術の問題が周知されるようになり、知財批判の緊急性は相対的に低下した。この流れにおける最重要アクターは、もちろんエドワード・スノーデンである。LQDNにおいては2014年にジェレミー・ジマーマンが脱会し、新陳代謝を果たした彼らも監視資本主義批判に活動の基軸を移すようになる。そして専門知をフル活用したロビー活動によって、今ある形でのGDPR制定に大きく貢献 *27 したのだった。今日、私たちがCookieへの同意を拒否できるのは、部分的にはLQDNのおかげなのである。
その後、ウェブ上だけでなく都市空間にも監視資本主義は魔の手を伸ばしている、という認識とともに、LQDNは他の市民団体とともにTechnopoliceというキャンペーンを2019年に開始する。Technopoliceの綴りは、イエロー・マジック・オーケストラの曲名(Technopolis)とはわずかに異なっている。「メトロポリス」に「テクノ」をかけた、すでに人口に膾炙して久しい造語の語尾をわずかに変えて、テクノロジーの力によって警察権力が隅々まで行き渡る巨大都市、という新しい意味を生み出したのだ。このキャンペーンではフランス各地における監視資本主義の広がりの報告を市民から集い、監視カメラなどの位置情報が記載された地図 *28 が共同作成されている。

そして彼らはセキュリティ産業がパリ五輪を重要な商機と捉えていることに気づく。フランスで発行されている業界誌『S&D Magazine(セキュリティ&防衛マガジン)』で、 社名から事業内容が明らかであるDrone Voltや、監視カメラ製造を行うAxis Communicationsといった企業が語るパリ五輪に向けた業界の展望が、Technopoliceのフォーラムで論じられたのは2020年7月24日のことである *29 。そしてこの年の10月に提出された「治安関連法(loi sécurité globale)」の法案提出理由書(exposé des motifs)に以下の文面があったことで、LQDNはパリ五輪に反対するグループとの接触を図ったのだ。
本法案は、民間警備部門の位置付けも行うものである(第二項)。急成長を遂げている同部門には多くの批判があるが、2023年のラグビーW杯や2024年のオリンピックなど大規模イベントの開催を控える我が国の治安維持連続体にとって、不可欠な要素となっている *30。
そしてLQDNとパリ五輪反対グループが協力し、前述の意見記事「2024年だけでなく今後もずっと、オリンピック・ビッグ・ブラザーに反対」が生まれたのである。
この法案への抗議行動は大規模なものとなった。けれども上述の『ランディマタン』掲載記事が多くの市民を感化したわけでは、もちろんない。最大の争点となったのは、法案に含まれていた職務中の警官の写真・ビデオ撮影を禁止する条項であった。この条項によって自分たちの職権が制限されるのではないか、と危惧したジャーナリストたちがあらゆるメディアで反対の論陣を張り、フランス全土で議論が盛り上がったのである。そして労働組合や人権団体、アーティストの協会や本連載第4回で批判的に取り上げられた環境団体などが「Stop Loi Sécurité Globale」*31 という連合に名を連ねたのである。最大の動員となった2021年1月16日のデモには、フランス全土で20万人(主催者発表)が参加している。
最終的に「警官撮影禁止条項」は撤廃され、反対運動が勝利したかのようなムードが支配的となった。しかしLQDNのメンバーたちは可決された法律にはまったく不満で、反対運動が警官撮影の問題に矮小化されてしまった、と受け止めたのである。ここでこの程度の食い止めしかできなかったツケはいずれ必ず回ってくる、という予感とともに。
それから約2年を経た現在、「新オリンピック関連法案」に反対する動きが「治安関連法」と同じくらい大きなうねりとなりそうな見込みは、本稿執筆時においてはほぼ皆無である。今年1月14日にLQDNがオーガナイズした「セキュリティ重視のオリンピックによる締め付け強化(JO sécuritaire l’étau se resserre)」と題されたイベントには300人もの人々が集まり、二酸化炭素濃度が上がって苦しいほどだったが、その熱気を政治エネルギーに転換することはそれほど簡単ではない。「新オリンピック関連法案」とほぼ同時期に「反スクウォット法」*32 、「移民法」*33 が議会を通過する見込みなので、この三つの法案に同時に反対する連合を作ろうという試みが、本稿執筆時に水面下で進行しているところである。しかし「Stop Loi Sécurité Globale」の動員の1割にも達すれば望外の喜び、といったところだろう。
ところでパリ五輪の開会式はセーヌ河で行われることが決定している *34 。入場行進の代わりに各国の選手団は船を使って河を下り、IOC委員や各国のVIPが待つトロカデロ広場に到着するという壮大、というか無茶な計画である。警備上の困難を度外視した、テレビ映えしか頭の中にない組織委員会によるこの無謀な提案に、計画浮上時のパリ警視庁総監、ディディエ・ラルマンは反対していた。結局エマニュエル・マクロン大統領の介入によって組織委の希望は通り、開会式の総監督(トマ・ジョリーという新進気鋭の舞台演出家)も2022年の秋には決定し、何より2022年7月に異動したラルマンの後任が反対していないので、この決定が今後覆される可能性は限りなく低い。関係者の間では現在、観客人数の上限(当初案は60万人)をめぐって攻防が繰り広げられているところである。
この開会式では、ドローンやスマート監視カメラが大活躍することだろう。セーヌ河岸に大量に設置されるであろうスマート監視カメラは、大会終了後どこに行くのだろうか?国民議会での審議を待つ「新オリンピック法案」には「2025年6月30日まで実験的に」との記載があるが、LQDNは以下のように論じている。同法成立を待たずしてこの技術はすでに密かに、非合法に使用されている。オリンピックはそれを一般化、陳腐化するのだ。スマート監視カメラ導入には巨額の費用がかかるのだから、投資費用を回収する必要がある。こうして新たな「レガシー」が残されるのだろう。
そしてパリ五輪が残すオリンピックテクノポリスレガシーは、次大会の開催都市、ロサンゼルスにどのような影響を与えるのだろうか。アテネ五輪に大量の政府関係者を送り込んだ実績のあるアメリカが、自国開催の次大会を控えてCIAやFBIやNSAやロサンゼルス市警の幹部級職員をパリに派遣しないはずがない。そしてカリフォルニア州は監視資本主義のお膝元、と言える土地である。
しかしこうも考えられる。サンフランシスコがどこよりも早く警察による顔認証を禁止したように、監視資本主義が爛熟している土地だからこそ議論が活発になるポテンシャルが高いのでは、と。ロサンゼルスとは、ユートピアとディストピアが渾然一体となり煌めくさまによって「水晶の都市(City of Quartz)」とマイク・デイヴィスに呼ばれ、「ブラック・ライブズ・マター」取り締まりのために個人宅のドアに設置されたAmazonの監視カメラ(Ring Doorbell)が映した映像を市警が要求するような *35 、そんな都市である。そうであるからこそ「Olympic Security」批判をどこよりも不可逆的に推し進められるのではないか、と。フランスでだって「新オリンピック法」が可決され、監視資本主義が一歩前進した後になって、ようやく議論が活性化しそうな兆候はすでにあるのだ。
今世紀の最初の20年間は監視資本主義のやりたい放題となってしまったが、今後もそうなるかどうかは私たちひとりひとりにかかっている、と言うのはショシャナ・ズボフだ。
「人間によって作られたものはそれが何であれ、私たちが力を合わせれば人間の手によって作り変えることができる」*36 と。そしてズボフは、監視資本主義と民主主義の未来にとって21世紀のサードディケイドが決定的に重要である、とも繰り返し語っている。
そして21世紀のサードディケイドにパリとロサンゼルスで開催されるオリンピックには、監視資本主義そのものの試金石となりうるポテンシャルがあるのかもしれない。
- パレスチナの武装グループがイスラエル選手を人質にとり、ドイツの警察が救出に失敗した事件で知られる大会。最終的に人質11名、犯人グループ5名、警官1名が死亡という大惨事となった。1936年ベルリン五輪開催の立役者であった、アベリー・ブランデージIOC会長の「The Games must go on!」という絶叫も有名。 ↩︎
- Dominique Clément, ‘The Transformation of Security Planning for the Olympics: The 1976 Montreal Games’, in Terrorism and Political Violence, 0:1–25, 2015, p. 14. DOI: 10.1080/09546553.2014.987342. ↩︎
- Clément, ibid. p. 14 ↩︎
- https://apnews.com/article/f16a2338b493478cb37b89e86407e316 ↩︎
- 電子フロンティア財団のウェブサイトで全文の閲覧可能:https://www.eff.org/fr/document/20150928-intercept-sid-trains-athens-olympics.pdf ↩︎
- NSAがプレスリリースを出している:https://www.nsa.gov/Press-Room/Press-Releases-Statements/Press-Release-View/Article/1636887/nsa-awards-major-acquisition-contract-to-science-applications-international-cor/ ↩︎
- C4Iシステムとは、情報技術の発展にともない前世紀の終わりに各国の軍隊が採用するようになった情報処理システムである。 ↩︎
- 2004年7月30日付でAthens Newsが報道した、シドニー五輪の警備最高責任者で、アテネ五輪の警備コンサルタントを務めたピーター・ライアンの発言。 ↩︎
- オリンピック会場の屋外コンサート会場で爆破事件が起こり、2名が死亡している。 ↩︎
- Minas Samatas, ‘Security and Surveillance in the Athens 2004 Olympics: Some Lessons From a Troubled Story’, in International Criminal Justice Review 2007; 17; 220. DOI: 10.1177/1057567707306649. ↩︎
- Samatas, ibid. ↩︎
- https://www.works-i.com/column/olympic/detail004.html など。 ↩︎
- https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65291520R21C20A0CC1000/ ↩︎
- https://jpn.nec.com/press/202109/20210906_01.html ↩︎
- https://lundi.am/Ni-en-2024-Ni-jamais-NON-au-Big-Brother-Olympique ↩︎
- https://www.lemonde.fr/sport/article/2022/11/23/jo-2024-la-reconnaissance-faciale-ne-sera-pas-experimentee-durant-les-jeux_6151265_3242.html ↩︎
- https://www.nytimes.com/2018/02/09/technology/facial-recognition-race-artificial-intelligence.html ↩︎
- https://www.nytimes.com/2022/05/26/technology/pimeyes-facial-recognition-search.html ↩︎
- 楽曲を認識する音声検索アプリケーション ↩︎
- シリコンバレーでは珍しいトランプ支持者としても有名な、Paypal創業者にして現Palantir社会長のピーター・ティールが同社に投資しているなど、極右思想の持ち主との繋がりが取り沙汰されることも多い。 ↩︎
- 元老院に提出された法案全文は以下で閲覧可能:https://www.senat.fr/leg/pjl22-220.html[ ↩︎
- ジル・ドゥルーズ「追伸──管理社会について」『記号と事件』宮林寛訳、河出書房新社、1992年、366ページ ↩︎
- https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/02/03/projet-de-loi-jo-2024-l-ombre-suspecte-des-drones-plane-sur-les-festivaliers_6160461_3246.html ↩︎
- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%B9 ↩︎
- Hadopi法の正式名称は「インターネット上での創造の流通・保護促進法(Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet)」といい、P2P技術を使用した違法ダウンロードを行った者の電話・インターネットへのアクセスを禁止する、という厳しい規制が盛り込まれていた。実際にインターネットへのアクセス禁止(15日間)を補充刑とした判決はおそらく一つしか出ていない、とされている。2013年に発せられた政令によって同法は事実上廃止されている。 ↩︎
- この標語はLQDNのメンバーが執筆した「団体自伝」の書名となっている。Mathieu Labonde, Lou Malhuret, Benoît Piedallu, Axel Simon, Internet et libertés, Vuibert, 2022. ↩︎
- GDPRについてのLQDNによる総括は以下で読める:https://www.laquadrature.net/2018/05/25/25_mai/ ↩︎
- https://technopolice.fr/villes/ ↩︎
- https://forum.technopolice.fr/topic/610/sd-magasine-l-industrie-fran%C3%A7aise-en-ordre-de-marche-pour-les-jop-2024 ↩︎
- https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3452_proposition-loi ↩︎
- https://stoploisecuriteglobale.fr/ ↩︎
- 法案全文は以下:https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0360_proposition-loi これまで諸外国と比べると寛大に扱われてきた不法占拠に対し、禁錮3年、罰金3万ユーロといった厳しい罰則を可能とする法案。 ↩︎
- 法案全文は以下:https://www.senat.fr/leg/pjl22-304.html 移民審査に職能差別を導入しようとしているため、人権団体などから批判されている。 ↩︎
- 組織委のウェブサイトでイメージ画像を見ることができる:https://www.paris2024.org/fr/ceremonie/ ↩︎
- https://www.eff.org/fr/deeplinks/2021/02/lapd-requested-ring-footage-black-lives-matter-protests ↩︎
- https://time.com/6173639/democracy-big-techs-dominance-shoshana-zuboff/ ↩︎
著者紹介
佐々木夏子(ささき なつこ)
翻訳業。2007年よりフランス在住。立教大学大学院文学研究科博士前期課程修了。訳書にエリザベス・ラッシュ『海がやってくる――気候変動によってアメリカ沿岸部では何が起きているのか』(河出書房新社、2021年)、共訳書にデヴィッド・グレーバー『負債論――貨幣と暴力の5000年』(以文社、2016年)など。