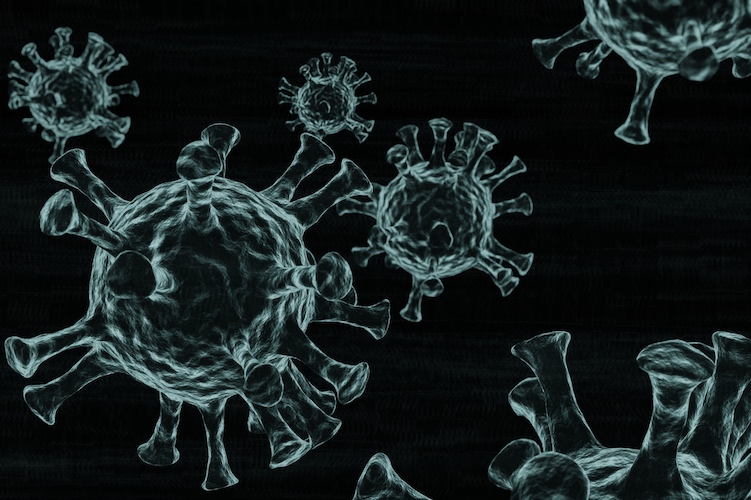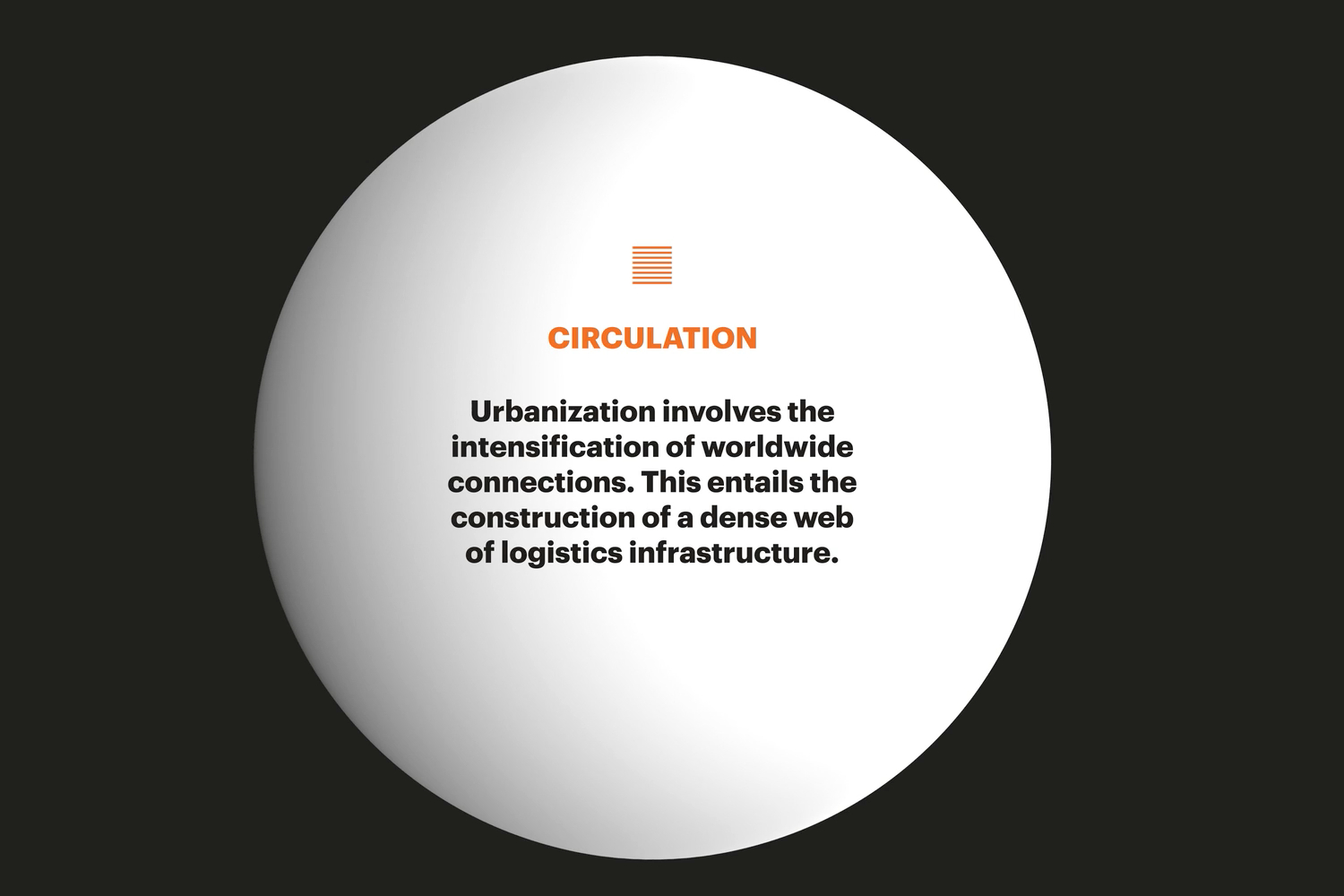コロナ後の世界と「ブルシット・エコノミー」(片岡大右訳)
デヴィッド・グレーバー

訳者まえがき
以下に読まれるのは、デヴィッド・グレーバーがフランスの日刊紙『リベラシオン』の2020年5月28日紙面に寄せた論考(「David Graeber : vers une « bullshit economy »」)を、著者自身が公開した英語原文に基づき翻訳したものである。読みやすさを考慮して、段落分けは仏語版を参照しつつさらに増やし、見出しは独自に補った。
人類学者はこれまでも、コロナ禍のただなかでの状況的発言を散発的に行ってきた(「魔神は瓶に戻せない」)。談話ではなく書き下ろしの原稿としては初めてのものとなる本稿は、それらと同じくおおむね『ブルシット・ジョブ』(原著2018年、日本語訳は岩波書店より2020年7月刊行予定)での論争的な問題提起の延長線上にあるけれども、「経済」というコンセプトの歴史を振り返り、その自明性を解きほぐしつつ、再定義の──さらにまた、それが不可能であるなら端的な放棄の──必要性を示唆するという点で、一歩踏み込んだ議論が展開されている。
「ほんの3か月前には、GDPが1%でも下がれば容赦ない破局が訪れるものと、誰もが決めてかかっていたものです。経済のゴジラのような何かに、みんな踏み潰されてしまうんだ、といったふうでした」──本稿に先立ち5月半ばに公開されたあるインタヴューで、グレーバーはこのように振り返っている。ところが今回の危機を前にして、各国政府は経済活動の大がかりな停止に踏み切ったのであり、そしてわたしたちは……今なお生きている。そうであるなら、「経済」の回転こそが人びとの死活の利益に関わっているという通念は、いったい何だったのか。いやそもそも「経済」とは、いったい何なのか。「パンデミックのおかげで、わたしたちにはこうしたことが、これまで以上にはっきりと見えるようになってきたのです」──同じインタヴューではこう述べられている。
もちろん、「経済」なる自律的領域の持つ歴史的性格は、何よりすでに『負債論』(原著2011年)の壮大なパノラマのなかで繰り返し検討に付されていた。ここでは、同書が途方もない国際的反響に迎えられたのちの2014年版あとがきに書きつけられた自問を引くことにしよう。
まさに今日、生まれた子どもたちは、もはや「経済」がなく、それらの問題がまったく異なった言語で検討される日を経験するだろうか? そのような世界はいったいどのようなものだろうか? わたしたちの立っている現在の地点からは、そのような世界を想像することさえむずかしい。だが、もしわたしたちが、一世代かそこらのあいだに人類全体を一掃してしまう危険のない世界を創造しようとするならば、まさにそのような規模でもろもろの事柄を想像し直しはじめねばならないだろう(酒井隆史監訳、以文社、587頁)。
グレーバーのみならず少なからずの人びとにとって、パンデミックとロックダウンの日々は、まさにこの「そのような世界」を想像し、垣間見、ひととき生きるための契機となったように思われる。
とはいえ事態は──グレーバーが念頭に置いている欧米について見ても──まったく楽観的な展望を許すようなものではない。本稿はまさに、コロナ禍を経た世界が結局のところ以前の世界への単なる回帰となるのではないかという危機意識のなかで書かれている。
2020年6月1日 片岡大右
経済とは何か
英国と米国では、「経済再始動」とか、「わたしたちの経済を再び立ち上がらせ、走り出させる」とか、その種のことがずっと語られている。
こうした物言いは、経済とは、ブンブン音を立てて回る巨大なタービンのようなものであって、一時的に停まっていたけれどもまた動かさなければならない、といったふうに聞こえる。このところわたしたちは、経済についてこんなふうに考えるよう促されることが多い。
けれどコロナ危機の前にわたしたちが聞かされてきたのは、経済とはほとんど、ひとりでに動くマシーンのようなものなのだ、ということだった。「一時停止」や「オフ」のスイッチなど、あるはずもない。あるいはあるとしても、そんなスイッチを押すならただちに破局が引き起こされずにはいない、ということだったのだ。
実際のところ、スイッチは実在していたわけであって、これはこれで、もちろん興味深い事実だ。けれどわたしたちは、さらに深い問いを投げかけることができる。そもそも「経済」とは、厳密に言って何を意味する言葉なのか。
要するに、もしも経済というものが、単に人びとが生きていけるようにするための手段なのだとしたら、つまり食べ物や衣服や住まいを、さらには楽しみの糧を与える手段なのだとしたら、わたしたちの大部分にとって、経済はロックダウンのさなかにも、完璧に動いていたということになる。
もしも経済というものが、生きるために必要な財とサービスを用意することでは ない のだとしたら、いったいそれは何だということになるのか。
明らかに、コロナ下の社会生活のなかには、まっとうなひとなら誰もが再び動き出してほしいと願うはずのものがたくさんある。カフェ、ボウリング場、大学といったものだ。けれどこうしたものは、ほとんどのひとが「生活」の問題とみなすものであって、「経済」の問題ではない。
生活=生きること=命(ライフ)。これが政治家たちの優先課題ではないことはまず間違いない。けれども、政治家たちは人びとに対し、経済のために命をリスクにさらすよう求めているのだから、経済という言葉で彼らが何を意味しているのか、理解しておくことが重要だろう *1 。
経済の成立と現段階
今日では当然の事実のようにみなされているけれども、「経済」と呼ばれるような何かが存在している、という発想それ自体が、そもそも比較的最近のものにすぎない。この言葉はルターやシェイクスピアやヴォルテールにとっては何の意味も持たなかった。経済なるものの存在が広く受け入れられるようになってからでさえ、それが何を指し示しているのかをめぐり、人びとの理解はゆらぎ続けた。
例えば、「ポリティカル・エコノミー」という言葉が一般に用いられるようになった19世紀初頭、「エコノミー」という観念は「エコロジー」に非常に近いものだったのだ(両者は語源的に結びついている)*2 。つまりどちらも、自己調整システムとみなされる何かを指し示しており、この自己調整システムは、自然なバランスのもとに作動するならば、何らかの余剰を産み出すものとされた。利潤、成長、自然の恵みといった、人間たちが享受できるような余剰だ。
ところが今や、わたしたちは新たな段階に到達してしまったようなのだ。ここではもはや、「経済」という言葉は人間の様々な欲求、さらには欲望に応える供給のメカニズムを指し示すのではない。この言葉はほとんど、ただ頂点に付け加わった余剰の部分のみを指し示すようになっている。つまりGDP増加によって生じるものだけが「経済」とみなされるのだ。けれども、ロックダウンの経験から最近わたしたちが学んだように、こうした考えは手品めいたごまかしでしかない。
別の言い方をしてみよう。わたしたちの現段階においては、「経済」とはおおむね、ブルシット・エコノミーを意味する暗語となっている。そこでは余剰だけが問題となる。余剰物と言っても、かつて貴族たちが生み出したもののように、無益であるというまさにそのことのために称賛される何かではない。ここでの余剰物は、「必然の王国」*3 に属するものとして、つまり「有用性」や「生産性」を掲げる頭の硬いリアリズムに従うものとして、執拗に追求される何かなのだ。
「ブルシット・セクター」の現実
ともあれ、「経済」を再始動するという表現がなされる時、わたしたちが再始動するよう求められているのはブルシット・セクターにほかならない。
経営者が他の経営者を管理するこのブルシット・セクターは、広報コンサルタントやテレマーケターやブランド・マネージャー、戦略主幹や創発部長(および彼らを取り巻く補佐役の一群)、学校や病院の理事たちの世界だ。そしてまた、ピカピカの社内報のグラフィックデザインで結構な収入を得る人びとの世界でもある。社内報にそれだけの金をかける企業の現業スタッフは能率アップを迫られ、人減らしの対象とされ、果てしもない無用な書類仕事に追われているというのに。
ブルシット・セクターに属するこれらすべての人びとが仕事をしているのは、要するにただ他人に対して、自分たちのような仕事が存在しているのはまったく馬鹿げたことでもないのだということを納得させるためでしかない。
企業の世界では、ロックダウンが始まる前からすでに、働く人びとの多くは内心、自分は社会に何も貢献していないのだと承知していた。彼らの大部分は、自宅で仕事をするようになった今、現実に向き合うことを余儀なくされている。自分の仕事のうち、意味のある部分は1日15分で終わってしまうという現実に。さらにまた、社内で行わないわけにはいかない仕事は(そうした仕事があるとしても)、自分がいないほうがずっとスムーズに進んでしまうという現実に。
こうしてヴェールが持ち上げられ、真実が姿を覗かせた。「経済再始動」の呼びかけは何より、不安に慄いた政治家たちの声にほかならない。ヴェールがあまり長い間持ち上げられたままなら、背後に垣間見られた真実を忘れさせることができなくなってしまうではないか。
金融化と権力
この問題がとりわけ政治家たちにとって重要なのは、それが究極的には権力の問題と関わっているからだ。
わたしが思うに、召使いやチェック要員やガムテープ係といった一群の人びとは * 4 、封建時代の従僕の現代における対応物とみなすのが一番よい。こうした人びとの存在は、金融化の論理的な帰結だ。つまり企業利益が何かを生産することに──さらには何かを売ることにさえ──依拠することを次第にやめていき、企業と政府双方の官僚的制度が連携を深めつつ(両者は相互に絡み合い、次第に区別し難いものとなっている)、人びとに私的債務をつくらせることで利益が生み出されていくという金融化のシステムに伴って、こうした職種も生み出されることになるのだ。
どういうことなのか、具体的な例をひとつ示そう。
最近、わたしの友人のアーティストが量産マスクを買い取って、最前線で働く人びとにただで配ろうとした。彼女はただちに通告を受け取った。それによると、ただであろうと彼女にはマスク配布の資格がなく、非常に高額の許可申請が必要なのだという。そのためにはふつう、事前の借り入れが必要になる。要するに、ここでは単に事業の営利化が求められているのではない。真に求められているのは、金融システムが今後の収益の上前を受け取れるように計らえ、ということなのだ。
当然ながら、ただ金を吸い上げていくだけのシステムというものは、人口の一部からの忠誠を確保するために、もうけの分け前を多少とも分配しなければならない。人口の一部とはこの場合、マネジメント階級ということになる。こうしてブルシット・ジョブが生み出されていくのだ。
2008年の経済危機が明らかにしたように、グローバルな金融市場とは要するに、将来のレント吸い上げの見込みをめぐる投機の手段にほかならない。このシステム全体は、究極のところ、米国の軍事力に支えられている。
じっさい、2003年にはイマニュエル・ウォーラーステインが、1990年代のワシントン・コンセンサスとは結局のところ、このような現実に関わっていたのだとさえ論じた *5 。ワシントン・コンセンサスとは、帝国としてのアメリカが、自国の産業的優位の喪失と欧州、東アジア、BRICsの急速な発展によりパニックに陥って、競争相手の勢いを押し留めようと企てた窮余の一策だったというのだ。そこでは「市場改革」の意義が強く説かれたけれど、この改革の主たる効用はと言えば、米国実業界にかねてから存在してきたのと同じ馬鹿馬鹿しく無意味な官僚的システムを、競争相手国にも押し付けることでしかなかった。
そしてドナルド・トランプやボリス・ジョンソンが仕事を再開してほしいと求めているのは、こうした官僚的システムに関わる人びとにほかならない。彼らにとって重要なのはマスクをつくる人びとではなく、許認可の料金制度をデザインする人びとなのだ。
ケア労働の逆説
もちろん、仕事の中断を余儀なくされている職種のなかには、その再開が望まれるものも多い。けれどもたぶん、ないほうがよい仕事のほうがずっと多いだろう──特に、気候変動による全面的破局を避けようと望むのであれば。
(配下に自宅勤務を許可するよりも光り輝くオフィス・タワーで指図をしたいという企業官僚たちの虚栄心を満足させるだけのために、どれだけの二酸化炭素が大気中に撒き散らされ、どれだけの生物種が永遠に失われることになるのか、考えてみたほうがいい。)
もしもこうしたことがまったく当たり前のようには思われず、経済再始動の論理が何らかの意味を持っているように聞こえるのだとしたら、それはわたしたちが、「生産性」という古き20世紀の規則に従って経済を考えるようにと教えられてきたからだ。
現在、言うまでもなく、多くの工場が(すべてではないけれど)閉まっている。冷蔵庫や革ジャケット、プリンターのカートリッジや洗剤などの在庫は、いずれ補充されなければならない。けれども、わたしたちが今回の危機を通して深く実感することになったのは、今日では、最も必須の労働の大部分は、古典的な意味で「生産的」なものとは言えない──要するに、それまで存在していなかった物理的対象をつくり出すことと結びついたものではなくなっている、ということだ。
今日の必須の仕事(エッセンシャル・ワーク)のほとんどは、何らかの種類のケア労働であることが明らかになった。他の人びとの世話をし、病人を看護し、生徒に教える仕事。物の移動や修理、清掃や整備に関わる仕事。人間以外の生き物が繁栄していけるための環境づくりに取り組む仕事。
こうして人びとは、現在のわたしたちの報酬システムが、とんでもなくおかしなものだということに気づき始めている。あるひとの仕事は、それが明らかに他の存在をケアし、利益をもたらしさえするようなものであればあるほど、見返りが少なくなっていくのだから。
経済の再定義は可能か
「生産性」の崇拝は、主としてこうした報酬システムの正当化の役割を果たしている。とは言え、こちらはそれほど気づかれていないことだけれど、この崇拝は今や自己破壊の地点にまで到達してしまった。
すべては生産的でなければならない、ということから、米国では、連邦準備制度の統計は不動産の「生産性」(!)さえも評価の対象としているのだ。これは少なくとも、「生産性」という言葉が「利益」を意味する婉曲な表現としてどれほど頻繁に用いられているのかを明らかにしてくれる事実だ。
ところで連邦準備制度の統計はまた、医療や教育部門の「生産性」が低下していることを示してもいる。理由を問うなら、増大するばかりのペーパーワークの大波に最もさらされてきたのがこれらケア部門だからだ、ということがわかる。こうしたペーパーワークは要するに、質的成果をエクセル・シートに記入可能な数値に変換することで、自分たちの仕事がともかく何かを「生産」しているのだと証明するためのものだけれど、もちろんこんなことをしていては、教えることや看護すること、つまり実際にケアをもたらすことはどんどん難しくなっていく。
パンデミックのあいだ、経理屋や効率専門家は真っ先に病院から逃げ出してしまったので、最前線で働く人びとの多くは、そして患者たちもまた、彼らがいないと物事がずっと効率的に進むということを実地に経験することができた。
「経済再始動」への呼びかけは、だから要するに、経理屋を職場復帰させるために、わたしたちは死のリスクにさらされなければならないという求めなのだ。どうかしているとしか言いようがない。
もしも「経済」なるものに何か実質的な意味があるのだとしたら、それは当然、人間が──命を守るためにも、活気ある生活のためにも *6 ──互いをケアする手段を指し示すものであるはずだ。こうした観点に立って経済を定義し直すなら、どういうことが生じるだろうか。どんな指標が求められるのだろう。あるいはそもそも、指標なるものの存在すべてと縁を切ることになるのか。
そうして、もしも再定義など不可能で、経済というコンセプト自体があれこれの間違った仮定に塗れ、汚れすぎていることが明らかになるようなら、わたしたちは思い出すべきなのだろう――そう遠くない昔には、「経済」などというものは存在していなかったということを。たぶん経済とは、もはやその役割を終えたアイディアなのだ。
注
- 「カフェ、ボウリング場、大学」の再開を「経済」の問題ではなく「生活」の問題として論じ、そのうえ「生活」の問題をただちに「命」の問題と結びつけるグレーバーの言葉づかいは、日本語世界のなかでは違和感をもって受け止められるかもしれない。
大学はさておき、カフェを含む飲食店、ボウリング場やさらにはパチンコ店のような運動・遊技施設の休業は、わたしたちの列島ではまさしく「経済」の問題として議論され、しかも「命」を守るために犠牲を求められるこの「経済」こそが、「生活」または「暮らし」を支えるものとしてイメージされているのだから。
言うまでもなくここには、「補償なき自粛」の政策(あるいは無策)が経済なき生活維持を困難なものにしている日本の事情が深く関わっている。そのうえで指摘するなら、「ライフ」という言葉の持つ意味の広がりに依拠することで動物的な生命維持の次元と人間的な生活の次元をわかちがたい連関のうちに置くグレーバーの選択は、コロナ下の議論においてはしばしば見受けられるものだ。例えばスラヴォイ・ジジェクもほとんど同様の論理に基づき、動物的水準での「生き延び」と人間的な生の営みの結びつきを強調している。
この点については、本稿の訳者によるジジェク「人間の顔をした野蛮がわたしたちの宿命なのか──コロナ下の世界」の翻訳と解説「生き延びのための「狂気」の行方」を参照(『世界』2020年6月号)。 ↩︎ - 「エコノミー」の語源はギリシア語 oikonomia であり、oikos(家、環境)と nomos(管理、法)を組み合わせたこの語は元来「家政」を意味していた。この言葉の意味を政治的共同体の枠組みにまで拡張するために考案されたのが「ポリティカル・エコノミー」という表現であって、それゆえその意味は、今日形容詞抜きの「エコノミー」が担う意味と多かれ少なかれ重なる。「エコロジー」はすでに見たギリシア語 oikos に「〜学」を意味する -logy を結びつけた語で、19世紀後半に「エコノミー」を踏まえて考案された。 ↩︎
- マルクスが『資本論』第3巻48章で「自由の王国」と対比的に用いた語の自由な借用。 ↩︎
- 「召使い」、「チェック要員」、「ガムテープ係」は、グレーバーが「ブルシット・ジョブ」の5類型として提示するもののうちの3つ。さしあたりは『フォーブス ジャパン』の記事の説明を参照されたい(本稿の訳語もここでのものに従った)。 ↩︎
- イマニュエル・ウォーラーステイン『脱商品化の時代――アメリカン・パワーの衰退と来るべき世界』山下範久訳、藤原書店、2004年。 ↩︎
- 原文は、1語を除いて直訳するなら「alive(この言葉のあらゆる意味で)であり続けるために」となる。訳注1で指摘したのと同じ論理に従い、ここでもグレーバーは、生命維持の問題と人間らしい生活の問題を対立的にではなくわかちがたく結びついたものとして論じている。 ↩︎