アニミズム、レヴィ=ストロース、構造主義
春日直樹 × 奥野克巳 × 清水高志
はじめに
アニミズムの現代性を文化人類学・哲学から探究する『今日のアニミズム』。今回、第16回日本文化人類学学会賞を受賞された文化人類学者・春日直樹氏(一橋大学名誉教授)をゲストに招き、著者の奥野克巳氏、清水高志氏とともに出版を記念した鼎談を実施いただいた。
春日氏はオセアニアにおける人類学的研究でも著名ながら、ポストモダン人類学から存在論的転回へと至る人類学の最先端の理論を批判的に検討、近年では数学や物理学を民族誌の手法に導入するなど、新たな挑戦を続けている。
なお本鼎談は、春日氏から事前に民族誌と圏論に関する論文草稿をお送りいただき、そのうえで行われた。同草稿は、日本文化人類学会の機関誌『文化人類学』(86巻4号)にて掲載・発表予定である(以文社編集部)。* * *
トライコトミーと二項対立、そして圏論
春日:もともと奥野さんの本、清水さんの本は、一読者として大変面白く読ませていただいています。ただ、その一方で、お互いの立場はそれぞれ、全くと言って違うのではないかと思います。全体としてはとても肯定的に受け止めるけれども、立場の違いはあるなと感じていまして、それがどういうふうに異なるのか、鼎談の依頼をいただいたことを良い機会と思い、自分なりにも整理をしてみたいと考えました。
本書『今日のアニミズム』にまとめられた論考は、いずれも力のある論考で、とりわけ宗教について深い場所から取り出そうとしている。やはり今日の世界状況で、人間や社会、世界を考えていくためには、私たちのあり方や知識のあり方を含めて、どのように生きていけばいいのか、その全てを見直さざるを得ないようなところに差し掛かっている、ということを感じさせられました。それをやり始めたら当然、宗教的な次元へ向かうし、アニミズムの話を含むことになるでしょう。これはタイムリーなトピックであるし、私たちのあり方の根源を考えさせるための手掛かりになる書物だと積極的に評価します。
清水:ありがとうございます。
奥野:ありがとうございます。『今日のアニミズム』は、そもそもアニミズムが宗教の起源との関わりで論じられたように、主題となっているのはおっしゃる通り「宗教」です。人間、社会、世界、知識などの今日的課題を考えていくための手がかりとしてのアニミズムです。
この本の企画をいただいてから清水さんと数年間ご一緒する中で、以文社の別の企画になりますが、私は「マルチスピーシーズ人類学」も進めてきました。マルチスピーシーズのほうは、動植物、あるいは物質それ自体といった「物質性」との関わりを含んでいます。一方、『今日のアニミズム』は「精神性」の問題に対応している。そして、そのふたつのテーマはいずれも、世界から人間の力や存在を減じるとでもいうべき問いを孕んでいる。今振り返ってみると、私自身はこの10年程は、そういう研究関心でやってきました。
『今日のアニミズム』では、人類学のアニミズムの議論はせず、清水さんが仏教やインド哲学について議論されているのに少なからず影響され、私自身ももともと持っていた仏教への関心を新たに開眼させられました。清水さんも私も本書の中で岩田慶治を最も重要なアニミズムの論者として扱っているわけですが、岩田のアニミズムに喰らいつきながら、仏教のほうへと足を踏み入れることになったのだとも言えます。
人類学における古典的なテーマであるアニミズムは、1990〜2000年代に復活を遂げたのだと言えます。しかし本書で私は、あえて人類学の議論を中心に扱うのではなく、岩田や哲学者の梅原猛、中沢新一さん、そして浄土思想との関連では、評論家の吉本隆明、国民的作家である五木寛之さんなどに導かれて自分の論考を書き上げました。春日さんが今、おっしゃったように今日的な限界状況を見据えながら、宗教的なるものをアニミズムから考えようとしたときには、もはやひとつの学問領域だけに止まっていることはできないだろうと考えたのです。
私の中では、アニミズムだけではなく、マルチスピーシーズ人類学にも共通するテーマとして重要だったのは、人間本位でつくり上げられてきた世界を今後どのようにしていくのか、あるいは再主題化するのかということでした。その点に関して言えば、人類学こそが、最も人間中心的だったということです。人類学は、特にアメリカでは、形質・考古・言語・社会文化という四領域を統合したところに構想された学知であったわけですが、その中で文化相対主義の御旗を掲げた「文化人類学」のが肥大化した結果、人類学は、人間に関わることだけしか取り扱うことがない学問になってしまった。
人間を知るには人間のことだけ探っていて不十分ではないかと考えているうちに、21世紀になると「人新世」という地質年代区分とともに、地球の環境危機が叫ばれるようになり、私自身は、マルチスピーシーズ的な思想に接近していったわけです。マルチスピーシーズ(多種)の人類学は、ヒトという種を多種のひとつに過ぎないと考えます。他方でアニミズムもまた「地球上で人間だけが主人なのではない」という、人間を世界の中心には置かない思想で、そうした流れにおいて、私自身は、『今日のアニミズム』の執筆を進めてきました。
清水:哲学者の僕がなぜ、アニミズムについて考えるようになったのか、簡単にお話ししますと、それはもちろん現代性があるということもそうなのですが、僕は哲学における《幹-細胞》的なもの、つまり多様な細胞に分化していく前の、ちょうどニュートラルな核になるものを取り出すということを、『実在への殺到』(水声社)を書いた頃から試みていました。さまざまな宗教がおこり、これだけ人類の文化が多様に繁茂した中でその《幹-細胞》のようなものを考えられるとしたら何かというところで、それはアニミズムではないかと思ったのです。
ヨーロッパの哲学、思想というのは古い時代から非常に一貫性があり、聖典的なテキストを定め、ニュートラルな形や一般的な解釈をもとめて、無駄な概念を削ぎ落として議論していくわけですが、それとは逆に、仏教や東洋思想というものは、さまざまな聖典や解釈のバリエーションを際限なく増殖させていきますよね。そこをヨーロッパの人々がやったように、いったん絞って考えたほうが、われわれの現代の文明だけじゃないものも深くまでわかるのではないか、ということなんです。
それともうひとつ、僕自身の思考の傾向なのですが、大体三つくらいのことを三題噺のように同時に考えるというのが、なぜか僕は好きらしいんです(笑)。処女作の『セール、創造のモナド』(冬弓舎)では、ミシェル・セールと西田幾多郎、ライプニッツを同時に扱っていた。あるいは、「ヴィヴェイロス論」を書いているのに、その中でヴィヴェイロス・デ・カストロだけではなく、ブリュノ・ラトゥールやライプニッツが出てきてしまったりします。そのように三つくらいを回しながら考えるという発想のパターンがあり、それでとうとうトライコトミーという方法論を『今日のアニミズム』で考えるに至ったのです。
今回、春日さんとお話しすることになり、レヴィ=ストロースの著作などあらためて自分なりに読み返してみました。人類がいろんな形で物事と物事の関係をつける、春日さんの圏論を導入した最近の考察もそうだと思うのですが、その中で二項対立ということが非常に重要な思考の鍵になっている――レヴィ=ストロースも、色々な文化の内部で考えられてきた二項対立を、複雑に読み解いて考察していますよね。――ところで、21世紀になって明らかになってきたのは、そもそもヨーロッパの文明自体も、そのように二項対立を複雑に結びつけて人類が世界を意味づけてきたことのバリエーションのひとつだったのではないかということです。フィリップ・デスコラの仕事が示唆しているのもまさにそうしたものです。レヴィ=ストロースはあくまでも異文化を理解するために深く踏み込んでいったわけですが、気がついたらヨーロッパの文化もその探究の範囲に入っていたというようなところがあると思います。
それで、もっと哲学の側からもそれを真剣に受け止めて考えなければならないと思い、何種類かの二項対立を、あらかじめ絞ったうえでお互いに結びつけたり、媒介させたり、第三項的な媒介者の位置を循環させたり、そうした循環の縮約されたモデルをミニマムで考察し、その哲学的な意味を解き明らかにしようとした。それがここで提示された、三種類の二項対立の組み合わせからなるトライコトミーというものです。
春日:『今日のアニミズム』では、清水さんは「主体/対象」「内/外」「一/多」とされていますが、トライコトミーとはこの三種類の二項対立だと考えていいのでしょうか。
清水:二項対立を複数扱い、二種類の二項対立でなくさらにもう一種類を組み合わせるというのは、ある意味では古くからある考え方で、たとえばライプニッツのモナドロジーは「一/多」、「内/外」(含まれる、含む)、「形相/質料」の三種類の組み合わせによって成っていると理解することができます。このうち特に「一/多」、「内/外」(含まれる、含む)は重要で、二項対立の中ではある種「王者」なんですよね。三つ目はむしろさまざまなものを代入できるのではないかと思っています。二項対立の問題は、西洋哲学ではイデア的世界と感性的世界が分離してしまうことをどう克服したらいいのか、という課題があって、そこからその重要性が前景化してきた歴史があるんです。二項対立はだからイデアと関わるものなのですが、「内/外」(含まれる、含む)は、分有されるものであるあらゆるイデアに共通した普遍的性質であり、重要ですがそれだけだと抽象的過ぎる。それをもう少し感性的なものにした二項対立が「一/多」で、後期プラトン、たとえば 『パルメニデス』や『ティマイオス』は、こうしたものに他の二項対立を組み合わせるという議論ばかりやっています。
僕はミシェル・セールの学問に多年傾倒しているんですが、彼自身にはジョルジュ・デュメジルの神話学の影響が強くあり、そこでは「聖なるもの」と「戦闘」と「豊穣」という、別の三機能がとても重視されている。聖なる神としてのジュピター、戦の神としてのマルス、豊の神クィリヌスといった機能ですね。これらは三位一体であるようで、互いに順繰りに前景化してくるものとしてあります。よく知られているようにデュメジルは、レヴィ=ストロースに先駆けて、ある種の構造的思考を神話のうちに見出した人です。それらの機能の咬ませ方や崩し方は、トライコトミーで僕が考えたこととも重なってきます。今回仏教を読み解くという意味で、「主体/対象」「内/外」「一/多」の三種類を取り上げましたが、くっつけたり、ひっくり返したり、相互包摂したりする関係をつくり、多極化するというのは、元来さまざまなものに応用できるものです。こうした操作を経なければ、ひとつのオブジェクトに集中するような社会構造がすぐにできあがってしまう。それは貨幣経済などもそうでしょうし、ヨーロッパの近代的と呼ばれる政治的システムもまた同じ偏りを持っています。そのようなものも含めて文明を再考する際には、一度、シンプルな形に戻す必要があり、その中でアニミズムを考えるということを、民族誌的な事例も含めて奥野さんから刺激を受け、それを吸収しながら本書にまとめたという感じですね。
二項対立を考えるということについて、今一度、ここであらためて人類学者の方々にうかがってみたいと思うのですが、人類学ではさまざまな民族の文化を調査研究していくわけですが、なぜそこでは二項性というものを重視しがちなのか、あるいは異なる二つのものを関連づけるということが、ある文化を考える上でなぜ本質とみなされるのでしょうか。哲学ではこうだという理由については述べましたが、人類学の側からはどう説明されるのでしょうか。
春日:必ずしも二項対立を本質的なものと考えるわけではないと思いますが、私の知るところの二項対比を押し出した議論といえば、1920〜30年代にロベール・エルツというフランスの社会学・人類学者が『右手の優越』(ちくま学芸文庫)という本を書き、それが70年代に入って再考されたという流れです。当時はオクスフォードのロドニー・ニーダムが中心となって『右と左』という本が編集され、そこには綺麗に右/左、男/女、乾いたもの/湿ったもの、太陽/月といったものが並べられ、二項対比的に整理されていった。そんな時代でした。最終的には右側は社会構造へとまとめられて、左側は象徴構造へというような綺麗な対比によって社会的なものと文化的なものが節合して、整合性を持たせるというような分析を行う、いわゆる機能主義人類学の末期の時代でした。そのような議論には私も馴染みがあります。
もちろん、清水さんの指摘されるように、レヴィ=ストロースを忘れるわけにいきません。ただし、私にとってレヴィ=ストロースはどうしても数学と不可分です。彼は彼なりに数学を自在に使い、活用していった人だと思います。圧巻はやはり『神話論理』(みすず書房)で、特に3巻と4巻です。「食卓作法の起源」から最後の「裸の人」までにかけてのところは、非常に複雑な構造が出てきます。そこでは二項対比が当然使われるわけですが、いかに対応を見出していくかが重要になってきます。レヴィ=ストロースはこのような言い方はもちろんしませんが、たとえば、主体と対象があるとしましょう。そして、一と多があります。すると主体と対象の関係を、一と多の関係に関連づけることができます。さらにその関連づけた対応性が、内と外の関係へと対応づけられます。そしてその対応は今度は別の方へ、たとえば『神話論理』の1巻で述べられた「生のもの」と「火にかけたもの」の対応へ、さらには火と灰へと対応をつくることができます。このように対応関係を入れ込みながら、どんどんと増殖させて構造化していく。そこには感覚的なものも入ってくる。いわゆるレヴィ=ストロースの言う感覚的にして論理的なものの生成であって、その論理が何かというと、対応関係の構築ということだと思います。
彼の構造化がどこまで正しいかはともかく、そのように言語化して提示できるというのは、私としては非常に魅力的です。感性を働かせて、深い意識、ないし無意識のギリギリのところから論理をつかみ出している。フロイトの精神分析は私にはあまり合わない感じがするのですが、レヴィ=ストロースの『神話論理』にかかると、もっていかれてしまうところがありますね。

photo by Raphael GAILLARDE
清水:僕も自分の論考の注に書きましたが、そのようにレヴィ=ストロースが鮮やかに読み解いていく複雑な関係づけがあり、またそれに対する、彼自身によるメタ言説もありますよね。――有名な論文で、彼は神話変換の「公式」というものを出してくる。神話の中ではなんらかの関係が描かれ、その関係をつくる複数の項があるわけですが、項と項によってつくられたはずの関係が、また項と同じレベルのステージに立つ、その位置に繰り込まれるということが神話というものを成立させているという。その表現が神話変換の「公式」なんですね。これは非常に面白いと思う。
そもそもモナドロジーというものはアトミズムに対する転倒なんですね。アトミズムとは何かと言えば、部分からボトムアップで全体がつくられていく、理論もエビテントなものをつないでつくっていった果てにあるものが合理的であり、そうやって最後に外在的な対象にアプローチするのが正しいという考え方です。これを転倒させるためのものがモナドロジーだったし、だからライプニッツも「諸部分からの構成に先立つ」単一体としてのモナドというものを持ちだして世界を考えようとしているんですが、レヴィ=ストロースが神話公式でやろうとしていることもやはり同じ転倒だと思うのです。諸部分と全体がフラットになるというのが、ここでは一番重要なわけです。
春日:最近の言葉で言えば、フラクタルを想起します。数学をやっている人がどこまで考えているかは知りませんが、数字で1、2、3、4と増えていく反復の関係があり、「べき」乗というか、一度出したものをまた入力して出力し、また入力して、と同じことをずっと繰り返していくわけですよね。あれは方向性があると言えばあるし、ないと言えばない。どっちにも同じように戻っていける。
『今日のアニミズム』の議論の中では、奥野さんが指摘をされているシンクロニシティにつながります。時間がないということ、「無時」の時間です。因果というものをそのように考えるならば、実は数学で表していることも結局は同じではないかとも思います。
清水:そうですね。先ほども触れた春日さんが圏論を導入された論考では、繰り返される関係づけの変換の中で、フィードバック構造が描かれているわけですよね。哲学者の田口茂さんが数学者の西郷甲矢人さんと一緒に、哲学と圏論とで何年にもわたる理論的対話を行い、その成果をまとめた『〈現実〉とは何か』(筑摩選書)という本が先年出ましたが、非常に面白くて僕は感心して読みました。その本の中で、圏論の構造というのは最初任意の非-基準的な選択というものがまずあり、そうした選ばれたものについてもろもろの要素による変換のフィードバック・ループができあがり、そしてそのループの中で法則性が定義されてくるものであるという機序が丁寧にたどられていました。これがひとつには圏論のあり方で、サイエンスも広く見ると、皆そのようにしてつくられてくるのだと述べられていたのが印象的でした。呪術の実践という主題が扱われた春日さんの論文でも、A(生者の領域において呪術を構成する集合)からB(霊の領域において呪術を構成する集合)へ行き、またBからAへと戻ってくるという関連づけが、変換とフィードバックを通じて、圏論でいうカテゴリーを形成していくさまが分析されていますね。
外的対象として、たとえばサイエンスの対象が厳然としてあるのではなく、人間との関与の中でできてくるというのは、ラトゥールもしばしば指摘していることですが、圏論がやっているのは、そのような形で変換操作と介入を通じて生まれてくるものとして、数学的対象の成立を一々定義してやることなんじゃないか。科学技術論(STS)においても、技術のイノベーションは、人間からの関与とつくられる物からくる独立した作用(agency)のフィードバック・ループで起こってくるという議論が一般的になってきています。双方にフィードバックがあるからこそ、かえってモノにエージェンシーがあることがはっきりするということなのですが、数学の対象を生みだしながら、圏論がやっていることもまさにそうですよね。圏論的なテーマを展開すること自体がそういうことなのだろうと思います。圏論的なカテゴリーの形成と、ある習俗の中で呪術として行われていることを重ねていくのが、なんらかのエージェンシーを持った対象創造が行われるあり方を、非自然言語をも用いて明確に定義するためなのだとすると、なるほど面白いと思いました。
自然言語を超えて記述すること
春日:宗教の話から入りましたが、他方で科学を考えるとどうしてもシステム的と言いますか、システム化を必然にしていくところがあります。知識の方向づけという点では、人文系、社会系のいずれの学問も一応は科学に従っている形をとっていますね。これに対しての宗教には科学に対するメタシステム的なところがあるのですが、それをどのように論理化して表現するかが大きなテーマになると思います。科学の場合には、論理と言っても基本的に記号論理やブール代数の次元にとどまるので、文系の議論ではたとえば論理を内破する形での論理的な運びで、論理のアポリアを明らかにするという手法がよくとられます。いわゆる否定神学的な構造化であって、ドゥルーズ=ガタリあたりも私は同様だと思っているのですが、一言でいえば二項対比を通じて二項対比を無効化するスタイルです。もうひとつの方向性は、メタ論理を最初からメタ論理の原則をさだめた上で展開するというもので、それならば独特の論理を持ってきてもいいし、独特の言語をつくってもいい。清水さんの議論ではその二つが両方とも使われている気がします。
要するに『今日のアニミズム』には、通常の記号の論理、言い換えるならば「手堅い」論理で読んでいくと読めないところがある一方で、そうではない部分もある。私は論理が辿れないと言いたいのではなく、逆に関係を自分流に定義づけているように読めると指摘したいのです。つまり、定義づけを通じて、新しい論理の使用方法を示していくという論法です。それは何も清水さんに限った話ではなくて、現象学をのぞいて大陸系の哲学者に認められる書き方なんですよね。最近はカンタン・メイヤスーやマルクス・ガブリエルというようなとてもわかりやすい哲学が登場していますが、私は論理演算を使うと計算間違いがチェックできるような哲学というのは、本当の哲学ではないと思っています。そうすると哲学というのは、もともと清水さんスタイルの議論からつくられているものだと思います。
で、ここからは私が少し違和感を持つところに入ります。『今日のアニミズム』で行われる哲学的な議論というのは、全て自然言語で行われています。自然言語でメタシステム的な思考のできることは、どうしても隠喩や逆説、アナロジー、というような文芸的なものになりがちです。奥野さん、清水さんお二人とも文学への言及もされているし、文芸のセンスがあるから、そういう意味ではぴったりなわけですけれども。
もともと、私はたとえば岩田慶治に対しても偏見がありまして、あまりいい言い方ではないけれども、エンドルフィンが分泌して、知的に低い水準で多幸感が得られるところに収まっていくような、そんな先入観があったのです。けれども、奥野さんや清水さんの議論を読み、そこに複雑な構造を読み取っていこうと努力をすると、確かに一定の説得力がある。岩田は理解しにくい構造をなるべく簡潔な自然言語の表現を通じて理解しようとしているのかと改めて読み返すと、確かにそう読めることに気づきました。これは『今日のアニミズム』を通じて、学ばせていただいたひとつで す。
しかし、お二人の論じ方にはそれでも少し違和感があります。議論の出発点は面白いのですが、「相互包摂」や「相依」というような表現に落とし込まれていって、いつも同じ論理が繰り返されて、その先にどこへどのように展開できるかがわからない。本書の中で、岩田の文章は何を読んでも同じようなことが書いてあると述べていたように思いますが、結局、少しずつ解釈の対象を変えて、同じ議論を反復していくだけではないか。率直に申し上げると、そのようなまどろっこしさが感じられなくありません。
では、「お前はどうするんだ」と言われると、自然言語でなかなかつかまえることができないのだったら、手近なところにあるのは数学的な言語なので、それを使いながら議論を組み立てていいのではないかと思っています。もちろん、数学的な言語の限界はあるわけですし、数学に全て従う必要もないわけですから、たとえば、それを一種の、否定神学的に示していくという手法もあってもいいわけです。私だったら、そのような方向を目指すだろうというところです。今回の論文も、数学の論理を貫きながらその論理を逸脱する側面をあぶりだしてみました。
清水:記号の「手堅い」論理では繋がっていないという指摘がありましたが、実際にはまさにこれがライプニッツ的哲学の構造なんです。デカルトみたいにエビデントなものが鎖のように繋がっていない。そのために、ざっくりと似た構造をとってきてそれらの照応を考えるという形になっているわけですが、これはミシェル・セールもやはりそうです。彼の時代は、数学じたいがそういう方向に向かっていた。ヒルベルト流の公理主義が破綻して、高等師範でアンドレ・ヴェイユらのグループ、ブルバキが活躍していた時代で、集合論に基礎を置きながら新しい数学のあり方を模索していた時代です。そこではややつまみ食い的に、あちらこちらで見出された数学的構造が別の対象についても語れるということが、手がかりとしてきわめて大事だった。
それともうひとつはトポロジーから、位置解析の考案者であったライプニッツに遡行していったのがセールです。科学を体系的に説明するというようなことは、たとえばデカルトなら幾何学から代数へ、代数幾何から物理へといったものが延々とある。そのように体系づけるというのはオーギュスト・コントくらいまではやっていたのですが、現代においてはもろもろの学問の全体をそんな風に体系づけることはできず、照応とモデルの貸し借りから考えていかないといけないようになっていますよね。
春日:いえ、体系づけるということではなく、自然言語とは別の言語を用いることで、今の議論をさらに進めて新しい議論の展開ができるということです。勝手なイメージで話しますと、たとえば圏論でいうトポスに置き直してみると、論理学と幾何学が結ばれていく構造に出会います。あるいは、奥野さんが「メビウスの帯」を扱ってらっしゃるけど、トポロジー幾何学そのものを積極的に活用するとか、ライプニッツに入って無限の話や超準解析から出発するとか。そうすると、現在、生成中の数学的な議論がもっとふさわしいのかもしれないけれども、どこか余裕を持ちながらそれを活用する議論をしていけば、私からすればもっと面白くなる、というような感想なんです。
清水:中沢新一さんが『レンマ学』(講談社)で数学を用いているように、自然科学がもっと入ってきたほうがいい、ということなんですね。それについて言えば、それは本当にそうだと思います(笑)。セール自身、自然学の人であり人文学の人でもあった。それはそうだとしか言えないけれど、どちらかというと自然科学と人文科学の対話というのは、セールがやった仕事なので。その重要さはもちろんなのですが、一方で彼があまりやらなかった部分もあって、それはやはり「東洋」と「西洋」との対話、またいわゆるプリミティブな文化とヨーロッパの文化との対話だと思うんですね。僕はそういうことをもっとやりたい。
デスコラについてセールが書いたときに、デスコラは分析する諸文化のバリエーションのひとつとしてヨーロッパの文化を含めたんですが、さらにそれをセールが推し進めるようなことをしたんですよ。西洋の文化を代表する幾人もの天才たちを採り上げ、デスコラがナチュラリズム、アニミズム、アナロジズムといった四象限で考察した性質を彼らが個人で複数体現していることを分析し、そこから文化創造の問題を考えたんです。読んでいて惹かれるとともに、変わったことを始めたなという印象だったのですが、最近セールは最初からそうだったんじゃないかという風に思い直したんです。一番初期に、みずからの手法として「ロゴス分析」という言い方をしていたときから、つまりプラトンやミシュレについて書いていたあの時点から、セールはギリシア以来の西洋の自然科学的、人文的な文物を扱いながら、それが生成する背後にある、レヴィ=ストロース的な意味での「無意識」を読もうとしていたのではないか。つまり西洋文明に潜流する野生の思考を読もうとすることが、「ロゴス分析」だったのではないかと思うようになりました。
そこに淵源する人類学的な方法は今、ラトゥールたちを経由して、あらゆるところへ散らばっています。個別的なイノベーションの場というのは、ラトゥールがやったようにそこではうまく分析できているのですが、その全体のつながりを見るためには、先ほども話したようにメタ論理が必要だろうと思います。それは特定の出発点から演繹するものではなく、多数のアプローチがあって対照できるけれども、それによってつくられたものもまた別の結節点に動員される、そうした構図があるというものです。これは西田哲学でいうと、「作られたものから作るものへ」という、裏返しの操作ですよね。先程のレヴィ=ストロースの話に戻ると、項と関係が同じスケールフリーになって神話ができているということと同じです。これはメタ的にも言えるんですが、それについて言及する場合には、個別の項から離れた普遍的な縮約モデルをつくらなければいけないため、かなり抽象になっていく。その抽象の形を理論化したのが、一面でまた仏教でもあって、先ほども出た「相依性」とかテトラレンマというのもそうした意味での縮約のモデルだったのではないかと思っています。
感性的なものを自然言語ではない形でロジカルに表現したいという衝動はわかりますし、当然、僕にもあります。じつは以前、圏論で西田をすっかり語れるんじゃないかという企画が持ち上がったことがあって、ある人が数学者の森田真生さんを紹介してくれて、一度京都まで行って、対話をしたことがあります。僕は僕で自分の論理を展開して話したのですが、森田さんは「いや、それは別に圏論にしなくていいのでは?」と言うんですよね。こちらの論理展開のほうが「それはそれで筋が通っているし、変にやらないほうがいい」と言われて帰ってきたことがあります(笑)。また、僕自身、そこまで数学でできるのかというと、自然言語よりはるかに難しいでしょうね。

科学を含み込む普遍的なものとしてのアニミズム
奥野:春日さんから頂戴した草稿は、日本文化人類学会の機関誌『文化人類学』に掲載される予定の論文ですね。非常に面白かったです。かつて浜本満さんらが40年前に呪術研究の新機軸となるような論文を発表されてから(浜本満・加藤泰、1982年、「妖術理解の新展開についての試論」『東京大学教養学部人文科学科紀要』)、かなりの年月が経ちましたが、この論文は呪術論としては、それ以来の衝撃です。結語として書かれている「21世紀の構造主義」を名乗るのにふさわしい論文として展開されていると思いました。
春日:ありがとうございます。
奥野:圏論について私は明るくないですが、春日さんの草稿に書かれている内容は、本書でやったこととそんなに隔たっていないのではないかと感じています。そこで二項対立的に語られているのは、「目に見える世界」と「目に見えない霊的な世界」です。そのような二項対立が、中沢新一さんが、二項の対称性や非対称性の観点から探られている「バイロジック(複論理)」的なものに通じるのではないかと理解しました。また、レヴィ=ストロースに言及しながら関係論的に論じていらっしゃいます。春日さんの論考は、『今日のアニミズム』で、私のパートで扱った「メビウスの帯」、あるいは仏教で言えば、吉本隆明が「還相論」と呼んでいる、「穢土」と「浄土」を往き来する浄土思想、つまり二項対立を無効化する無始無終の往還運動でやっていることにも似ているのではないかと思いました。
こんな丸め方は失礼かもしれませんが、向かっているところは、『今日のアニミズム』で論じたことのある種の相似であるように思います。先程のお話では手段や手がかりにするものは確かに異なっていますが、よく似た部分を探っているように思います。
ところで、この鼎談の冒頭でおっしゃったように、清水さんと私のアプローチはまったく違っているというのは、その通りだと思います。私の場合、「未開人」たちが考えていることを「一と多、同と異は、その一方を肯定する場合、他を否定する必然を含まない」と表現し、それを「融即律」と呼んだ、ルシアン・レヴィ=ブリュルを導きの糸として、アニミズムを考えました。これが表と裏があって、表と裏がないという「メビウスの帯」という、私のアニミズムのモデルを引き出してくる元々の流れにあります。
他方、清水さんは、この2500年という人類の思想の系譜から辿っておられます。古代ギリシアの二項対立の問題検討を踏まえ、それを大乗仏教哲学の集大成としてのナーガールジュナの『中論』と対比しながら語られています。融即律とは、一でもあり多でもあるという意味で「第三レンマ」的ですが、そこからその先に、一でもないし多でもない「第四レンマ」にまで踏み込んで、二項対立の問題を解こうとされている。二項対立に第三レンマを繰入れて、第四レンマを生み出す地点にまで進んで行って、一と多が、もうひとつの二項である主体と客体とツイストするだけでなく、含まれるものと含むものという内と外をさらに交差させることによって、ダイコトミーではなく、トライコトミーという考えを導き出されています。そのことによって、清水さんの言葉を借りれば、《幹-細胞》が、より明確な形で捉えられるようになったと思います。
ここまで述べてきて何なんですが、どちらかというと、二項対立、さきほど春日さんが述べられた人類学の主題として重要なのは、自然と人間の二元論ですが、それを乗り越える切り札のひとつこそが、アニミズムなのだろうと私は考えています。清水さんも述べられたように、《幹-細胞》の正体はアニミズムなのではないかと思います。
清水:春日さんの論文では、圏論とパプア・ニューギニアがいきなり繋がっている。それはとても凄いことだと思うのですが、アニミズムのあり方そのものも本来じつに多様なので、僕の場合仏教という形での縮約モデルをワンクッション挟んでおかないと手に負えないなと思って、『今日のアニミズム』ではそうなっています。仏教は仏教のほうで、仏教学者との対話を続けていて、仏教論理学と比較哲学の研究という形で正式に発表しようということになっています。科研費も得て、仏教というものを現代の思想としてアップデートするという試みです。
春日:なるほど、以前に『モア・ザン・ヒューマン』(以文社)の中で、清水さんは仏教学者の師茂樹さんと対談されていますね。元々は禅の話が主だと思いますが、やはり最初は、超論理とかいうスタイルで済ませていたのでしょうか? 自然言語の体系を、さらに自然言語によって崩していくというような形で。
清水:ずっとそうですね。言ってしまえば、井筒俊彦までずっとそうなんですね。僕からすると「一/多」の問題がクリアされていない。二項対立の問題を、あらゆるものが分節する以前の「不二」という、「一」のほうで解いてしまっている。そうすると、その「多」の問題が後から宿題になって残ってくる。ポストモダンまでずっとそうです。
春日:ポストモダンについては本書でも書いてあったけれども、そのとおりだと思います。
清水:井筒もそういうところがあるので、そこを本当に組み替えないと「禅というのは知性じゃない」みたいな話になってしまうので、ちゃんとそれもロジックなんだと言いたい。先程、自然言語だけでは駄目だというような話がありましたが、仏教などの東洋思想があまりにも非理性の側に割り振られているので、そこをもっと復権したい。復権して形をつくっていくと、それに絡まり合っていたアニミズムがもっと浮上してきて、はっきりとつかめるのではないかと思うのです。
春日:数学の話をしましたが、そもそも科学とは何かというのは大変難しいけれども、やはり数学と繋がれているところがある。数学に近い関係にある。数学的な思考と比較的、近い関係にあるというふうに私は考えています。それを踏まえてアニミズムとは何かと考えたときに、奥野さんはアニミズムとは「西洋の理性と科学的な知識では捉えきれない何かだ」というようなことを述べていたと思いますが、私はむしろ、西洋の理性や科学的な知識が立脚する原初的な思考様式として、アニミズムを考えてみたい。これはお二人とも反対するところではないと思います。
私にとって、レヴィ=ストロースはこの点でもよい見本です。お二人が本書でテーマとしているように、人間の思考そのものの差異を超えて普遍性に向かうところ、しかもそれが時間や空間の枠を超えて、意識や反意識の水準を押さえて広がるところに、おのずと宗教的な話やアニミズムというものが出てくるというのはよくわかります。しかし、それだけではなくアニミズムが、広い意味での「構造」――私はそれを「構造」と呼びたいのですが――として語り得る水準というものがあって、それは清水さんにとっての論理と無縁でない、と思えるんです。「構造」は科学の記述を生むだけでなく、タンポポの花や鉱物の結晶や猫の瞳を結びつけるし、神話を語る人も、さらに神話を分析する人も一緒につなげていきます。関係性を描く本人がその一部として入っていくときに見出すものとしての「構造」です。
もうひとつ。アニミズムと他力という奥野さんの主張につながるのですが、アニミズムは私たちの根底的な無力さが染み入るような場で現れる思考だという気がします。宇宙もそこにあるはずの実在も、そして実在するはずの自分も、ことごとく捉え難い対象であるという無力な認識があって、それでも大切な実在について言語化していいというか、言語化し対象化ができるという思いが否定できないときに、その感覚の保証人となるのが「構造」ではないでしょうか。外から与えられる、授かりものとしての「構造」です。アニミズムとか宗教的なものはそこにこそ現れる、と私は思うのです。
「神」とか「霊」とかの観念は、私にとっては「構造」から見て二次的なものです。実在と記述は別なので、記述できたといっても実在を示す保証はないのだけれども、それでも記述ができて、それなりにありがたみを感じることができるというところが、私にとっては出発点です。その証をよく示してくれるのが、レヴィ=ストロースの提示する「構造」なんです。それが正しいか間違っているかはわかりませんし、数学だって正しいか間違っているかはわかりませんが、私にとってはそういうものとしてあります。科学を傍流として含む大きな普遍としての構造の中にアニミズムがあるんだという認識です。
ノーベル物理学賞やノーベル生理学賞を受賞した著名な科学者たちが、宗教的な感情を本にまとめて出版したりしていますが、大抵の場合、キリストの神のように至上の存在を前提とするのだけれども、やはり脱主体とか脱個体と呼ぶべき変換と結びつけて書いています。そうした変換によって人間という存在を周りの諸物との関係の内部に溶解させていくし、諸事諸物が不可思議な力を持つような世界を浮かび上がらせるという点で、アニミズムに通底しているなあと思います。
この本の中では科学というものはどちらかといえば仮想敵のようになっているけれども、こう考えるとアニミズムの中で成り立っているのでないか、という気がするわけです。
清水:そうですね。サイエンスとの融和は非常に大事だと僕も思っています。アニミズムと仏教的な世界観や自然の捉えかたとサイエンス。南方熊楠ではないけれども、そこまで含めた体系をつくらないといけないと思っています。
レヴィ=ストロースの神話公式や「構造」というものを考えたとき、最近僕はよくプラトンを読むのですが、じつは『ティマイオス』の時点で、人類はそうした公式化や記述の試みをすでに何度もやっているんですよね。たとえば火や土などといった元素を挙げて、「二つのものは、第三のものなしにはうまく結びつかない」、第三項が媒介として必要だということを主張しながら、その役割を一番うまく果たすのは比であるという。そして等比数列を例に挙げて、初項と中項と末項の位置を順繰りに入れ替えても等しいという関係が成立することに注意を促したりしている。そこで語られているエンペドクレスのような人も、風土水火というように複数の対立二項に注目し、それらは反対物なんだけれども、乾と湿とか、熱と冷とか、もう少し感性的な対立二項を採っていくとそれらが第三項的な媒介を行い、全体がつながるということを考えている。この第三項の位置も一巡するわけで、これはまさにレヴィ=ストロースのいう縮約のモデルです。プラトン以前の自然哲学、西洋の自然科学的思考の基礎にも、野生の思考が脈々と息づいている。これが分からなかったら、逆にプラトンも分からない。
エンペドクレスは「愛」と「憎しみ」と四大元素で世界を説明したと言われるけれども、対立二項と、中間的な第三項によるその融和の両方を織り込むことによって、マリリン・ストラザーンではありませんが、間接的で部分的なつながりをつくっている。それを当時の言葉で「愛」とか「憎しみ」とか呼んでいるわけです。
そんな風に、本当に古くから人類とともにイデアリズムの思考とか二元論的思考とかが存在し、イデアそのものと感性的な世界が分離しないように世界をどう捉えるかということが、あらゆる地域でずっと試みられてきたわけですから、春日さんがおっしゃるように現代科学もまたその中のひとつの傍流、その一部と位置づけられるような、個人や個々の文化を超えた巨大な「無意識」や、「構造」というものがあるはずだ。それを記述しきれない無力さというものとも、当然それは表裏一体なわけですが、ひとつにはそこで深く感じられているのがアニミズムでもある、というのは話をうかがっていて本当に共感しますね。

肯定的なアニミズム/否定的なアニミズム
春日:先程、仮想敵と言いましたが、大学を辞めて在野の研究者になってつくづく思うのは、今、一番の仮想敵というのはやはり専門主義でしょうね。役立たずで崩れ去ろうとしている専門主義というものが未だに存在している。大学を去って半年もすれば、その馬鹿らしさがよくわかります。
清水:だんだんとそれぞれの学問の足場が小さくなってきていますから、本当はもう一度、横断的にやっていくしかないわけですが、春日さんのようなベテランの方のほうがチャレンジャブルで越境的にやっている。一方で若手は、ポストがなくなるかもしれないと思って、どうしても専門主義に陥らざるをえない傾向がどこにも見られますね。奥野さんのマルチスピーシーズ研究会のほうはのびのびと横断的にやっていると思いますが、哲学業界は西洋哲学の幾人かの大家を研究する学会がばらばらにあって、それらどうしですら対話がほとんどなく、空中分解したような状態になっている。
春日:奥野さんのマルチスピーシーズ人類学だって、奥野さん自身が存在感があるから目立っているけれども、文化人類学の学会内部からみるといろいろ大変ですよね。
奥野:ええ。特に日本の文化人類学の学界内では、自然を扱う人類学の諸派からの拒絶観のようなものを含めて、軽視されてしまってますね。まあ、文化人類学は、人間を主題化するという考えが主流ですから、特に気にしていません(笑)。
春日さんが専門主義の問題に気づかれたというのは、大学の教育研究職から離れて、いわゆる在野の研究者になられたから、ということですよね。専門主義にこそ、現在の学問の閉塞的な状況に対する大きな問題があるということですね。たとえば人類学で言えば、人類学界そのものがある種、論文の書き方や民族誌の書き方を形式化・制度化してしまっているというようなことも含めて、ということですよね。
春日:ええ。基本的にそういう点です。論理とか言い回しも含めて、形式主義的に行われているし、それで確かめ合っているという感じですね。
奥野:若手や中堅がなかなかそこに気づくことができないわけですし、かといって、鋭くそのことを察知して、外に出て在野に逃れてしまっては、内側から突破することはできなくなってしまうわけですね。それはそれとして優れた感受性だと思いますが。
いずれにせよ、学問自体が孕む専門主義の問題を抱えながら、学知をどうすべきかということこそが大きな問題です。それに関して少し思い当たるのは、2021年に出たティム・インゴルドの『Correspondences』(日本語訳は亜紀書房より刊行予定)というエッセイ集です。そこでは、彼自身非常にのびのびと自分の考えを語っている。
これまで、インゴルは『メイキング』(左右社)であれ、『生きているということ』(左右社)であれ、前書きで、大学関係の仕事が忙しすぎて、まともな研究ができないという愚痴をこぼしてきました。「休暇はかなりの量の残務処理をかかえてはじまった」(『メイキング』)、「私が読んだり、考えたり、書いたりする時間は、事務作業の容赦ない要求によって、再び脇へと追いやられてしまった」(『生きているということ』)という具合に。しかし、『Correspondences』では、そういう言い方がすっきりとなくなって、非常にのびのびと、「メッシュワーク」(インゴルドが用いる概念)的な動きの中で思索を進めている印象があります。大学の教育研究職から離れて、何かが吹っ切れたようにも思えるんです。インゴルドからは今後しばらく目が離せません(笑)。
これは教育研究に関わる雑務の話ですが、それは拠点を大学に置いているため、まあ仕方ないと言えば、仕方ありません(笑)。それより問題なのは、学知の制度や形式化のほうかもしれません。春日さんがおっしゃっている、それによって確かめ合っているような学問の形式主義。すると、学知というある種、狭い世界の中にいることに気づかないでいる専門主義みたいなものが、仮想敵でもあるということになりますね。先程、春日さんは『今日のアニミズム』では仮想敵は科学ではないかとおっしゃいましたが、本書における専門分野の横断性を考えますと、そもそも『今日のアニミズム』は、そうした専門主義のようなものを仮想敵としていたとも言えるのではないでしょうか。
私自身、アニミズムを考えるとき、仏教のほうにかなり軸足を踏み込むことによって気づいたことがたくさんあったわけです。専門主義に陥らずに、わりと自由にああだこうだと考えてみる。この前の加藤さんとの鼎談(以文社HP掲載、加藤学氏との鼎談「参与と融即のアニミズム」)で申し上げましたが、アニミズムとは神道ではなく、仏教だということです。その見方に応じて、清水さんは、もともと日本には本覚思想のようなものがあり、それがある種のアニミズム的なものだったのだけれども、それが古代からずっと綿々と続いてきたというわけではなく、仏教が入ってきたことによって統合されていったのだろうと述べられていたと思います。
たとえば、道元の『正法眼蔵』には、「山水経」という巻があります。そもそも山川草木がお経そのものなんだということです。今から800年前には、山川草木そのものがお経だと言っている。「山水経」には、有名な「青山常運歩(せいざんじょううんぽ)」のくだりがあります。山が運歩するのは、人間が歩くのと同じではないからと言って、そのことを疑ってはいけないと。そうか、これは確かにアニミズム「的」だ。道元の言っていることを理解するには、歩くのは動物だけだという考えに凝り固まっていることからまず自由にならなければならないわけだ、と。要するに、専門主義を超えて、どんどんとこういったところにも踏み込んでいかないと、なかなか見えてこないものがあるのではないかと思います。
先程、春日さんは、西洋の科学では捉えきれない何かがアニミズムというように二者を切り離すのではなく、アニミズムは西洋の理性や科学的知識が立脚する思考様式だとおしゃいましたが、普遍的なものへとつながるのは、当然、科学だけではなく、仏教にも言えることであって、『今日のアニミズム』は、科学ではなく仏教を通じて、普遍的なものを思考していったということではないかなと思います。
春日:そのことによって科学批判を感じる読者もいるかなとは思います。もうひとつ。これは質問にもなってしまうのですが、『今日のアニミズム』自体がやや楽観主義的に読まれてしまう可能性もあるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。アニミズムというのは魅力だけではなくて、当然、危うさや暴力性というものも含まれるわけですよね。あるいは権力との関係で、相互包摂によって権力の基盤が整うこともあるわけです。もちろん、それはまた別の分析になるだろうとは思います。ただ、アニミズムの良い一面だけを積極的に喧伝しているわけですが、それに対する批判は当然出てくるだろうと。私自身は積極的なメッセージとして受け取りますが、そうでない人からすると、ある種、怖いところもあるでしょう。
生命というのは生々しいものですから、さまざまなことがあると言い切ってもいいのですが、せっかく多元的、多層的に、理論を組み立てていっているわけですから、現実についても「こういうふうな世界なんだな」とわからせて欲しい気持ちがあるわけで、その点やや一面的に感じられてしまうと思いました。
奥野:なるほど。特に、私の議論では、確かにアニミズムをとてもポジティブなものとして捉えていますね。アニミズムの今日的な意義として、私は、今日さまざまな次元で問題視される人間本位の見方で物事を考えていくことを乗り越えることができるのが、アニミズムではないかとしきりに語っています。アニミズムの「連絡通路」を空けておくことを肯定的に考える傾向は、私の論考では強いのかもしれません。
春日:たとえばレヴィ=ストロースは、なかなかショッキングな事例を出してくるわけですが、それを何気なくすっと構造に収めてしまう。その辺は見事ですよね。食べたり殺したり切ったりという、書かれている事例は非常に凄まじいわけですが、それを使った論理的な分析に知性が見えるというのでしょうか。そうした「技」は私たちにはなかなか難しいわけですが、何か工夫しなければならない。私もどうしていいかわかりませんが、課題としてあるのではないかと思います。
清水:そのお話を聞いていて、僕は納得しましたね。基本的に僕はライプニッツ、ミシェル・セールのラインなので、オプティミスティックでおめでたいんですよね。その肯定性というものがある。系譜的に言えば、あいだにブリュノ・ラトゥールが入るわけですが、ラトゥールは逆に批判ばかりしていて、何だかよくわからないというようなイメージがありますよね。僕から見ると、ラトゥールが語っているのは、ミシェル・セールの学問の中の部分構造、つまりもろもろの学問のネットワークの一部を取り上げて語っているので、それをまた全体構造に戻したくて、それで肯定的にもしたかったというのがまずありますね。
僕の論考について言えば、もうひとつ、これは読み比べればわかると思いますが、かなり西田哲学が入っているんですね。ベースとして近いのは西田哲学です。西田幾多郎も土俗的なもの、仏教的な理論を吸い上げながら西洋の哲学と対話して自分の哲学をつくっています。けれども、それは華厳くらいまでで、もっと密教まで抜けると東洋文明を日本が吸収してきたみたいに、西洋文明じたいを習合できるのではないか。そういう形で溶け込ませようと思って、『今日のアニミズム』での議論を考えているので、融和のイメージが強いというのはあるでしょうね。
もちろん、語られる対象について批判的な視点もあっていいと思います。僕も批判はしていますが、そういう批判的な部分はたとえばポストモダンをスパッと切ったところですね。あれはあまりに簡単に切ってしまったので、むしろあまり気づかれず、あとは大体おめでたい話をしているという(笑)、そんな感じになってしまったことは否めないかもしれません。そこはもう少し工夫しなければならないところですね。
春日:難しいけれど非常に重要な課題だと感じます。

専門主義の「壁」を超えて、外側へと出ていく
春日:私が専門主義に入ろうと大学院に進んだときには、岩田さんがまだ健在でした。でも、ああいうやりたいことをやっている人もいるんだという思いで、それはそれとしておいておくという感じでした。ですから、今回『今日のアニミズム』に触れて岩田さんの本を読み返してみて、因果関係を強調しながら表の空間というか、ひとつのリアリティを持った空間があり、けれどもその背後にはもうひとつ別な空間があって、その両方が合わさって世界が成り立つという、お二人と同様な議論に触れることができました。このような認識は宗教的な観点からは当たり前と言えるし、イデアリズムからしても当たり前ですが、非常に大事だと思います。現代において、こうした認識にリアリティを持たせるにはどうすべきかと考えたとき、先日、東京大学を退官された田辺明生さんの指摘が重要なのではないかと思います。
インドを調査研究している人類学者の田辺さんは、まだ定年を迎える前に大学職を退くということで、先日、最終講義がありました。今後はインドのアシュラムで霊的修行に専念したいそうで、ミシェル・フーコーを引きながら非常にスケールの大きな話を展開してくれました。学問が真理を探究する思考様式であるのに対して、その真理に至るために自己変容を探求するのが霊性であり、その実践に関わっていくんだそうです。真理の探究は本来、学問と霊性と芸術を統合する形で進められなければいけないけれど、今それを大学で行うのは難しい、ともおっしゃった。最終講義は若い聴衆も多かったようで、こういう話を退官の前にするのはとても意義あることだと思いました。
彼が提示した現代世界の分析で、四つの繋がりが曖昧になっているという指摘が印象深いです。ひとつ目は、グローバリズムに代表されるように多元的な諸地域の繋がりがあやふやになってくること。二つ目は、人間と自然の繋がり、そして三つ目は地球と宇宙の繋がりのあやふやさですが、意味深いのは四つ目です。彼が挙げるのは、この世とあの世の繋がりで、その境界があやふやになっている点を強調しているんですね。
これは一体どういう意味なのかをいずれご本人にうかがうつもりですが、田辺さんが現代世界を捉えるために挙げたキーワードを手がかりに、私なりに考えてみました。ひとつはアルゴリズム。もうひとつはサバライリズム(survivalism)、つまり「生き残る」という意味での「生残主義」というもの。これはいわゆる社会運動として災害に備えるような運動で「プレッパー」と呼ばれる人々を指すのではなく、文字通り、「生き残るため」という意味です。経済学で言えば資本の論理であるとか、政治で言えば力の論理であるとか、あるいは衛生面で言えばまさにコロナ対策ではないけれども、生き残るための論理が暴走していることで、ジョルジョ・アガンベンやフーコーの議論とともに考えれば、生残主義にはそういう機能を果たすと解釈できます。
前者のアルゴリズムについては、私自身、今から書籍にまとめたいと思っているテーマです。数学と計算を別々に置いて、あらためて関係を考えることをこれから計画しているのですが、田辺さんはアルゴリズムと生残主義が合わさった状況を考えている。この世というのは、まさに生残主義ですよね。生き残るというのは取りあえずの充足条件ですから、この世のものです。生残主義は隠れた部分、背後にある根拠づけには一切触れないままに、みずからその領域を侵略しそうな勢いです。まさに、気がついたら生残主義以外に現実がなくなっているような、そういう怖い印象を受けますね。実際にそういうものが徐々にできあがってきている気もします。
こうした観点からこの世/あの世の境界を考えるならば、この世があの世に替わるというか、見える領域が見えない領域を徐々にまとめて扱い始めて、アルゴリズムの潜在的対象にしていく、と言えるのではないでしょうか。この現象は科学にも及んでいそうです。科学者の知人は予算配分の問題に直面していて、「短期的・集中的にものを作れ」「結果を出せ」という生残主義に浸されていることを愚痴ります。隠れた領域は科学も含めて圧縮途上にあり、アルゴリズムとサバライリズムに侵されていく。田辺さんはこんな状況を語っているのではないかなと思うのです。
清水:可視化されている領域というのは、非常に狭いですよね。そして、共有されていない。コロナ禍での大学というのは、本当に学生一人ひとりの見ている世界が全く違うんですよね。生簀の中の魚のような状態になっていて、時々ルアーのようなものが下がってきて、そこに多くの人の行動が殺到するような、そんな状態になっている。そこでは中心にはキャンセル・カルチャーがあったりとか、非常に危険な状態ですよね。それこそ、サクリファイス的な構造とか、サバイバルの構造でしかものが見えなくなっている。そうではない共存の形を考えるという意味でも、『今日のアニミズム』で問い直したことは大事なのではないかとも思っています。
奥野:生残主義というのは、『進みと安らい』(サンガ)や『人生科読本』(柏樹社)などの著書のある、20世紀を生きた内山興正禅師が、死を生に組み入れながら生きる「生命地盤」的な見方と、生きることの内側でどうすればうまく生きていけるのかということだけに汲々としている「生存地盤」的な見方に分けているのですが、話をうかがっていて、そのうちの生存地盤というアイデアととても近いように思いました。生存地盤で生きるとは、死のことを忘れて、生き残ることだけに何の根拠もなく躍起になっている人間の愚かな姿のことであり、ある意味で、学知は、その点に関して一顧だにしていないと言えるのかもしれません。
田辺さんは定年まで何年か残して大学を去り、インドに行かれるということですね。しかも真理を求めるために。逆に言えば、我々が大学で日々やっているような学知、あるいは大学における知の探究ではそれができないか、難しいというようなことがあるわけですね。だから、インドへ移って実践的に考えてみたい、と。それはまた、先の話にも繋がりますが、大学に代表されるような専門主義がかなり限界にきているということであるとも受け止められます。人類学者だけでなく、人文系の大学の研究者で、最近大学を辞めて、在野に移った方が何人かいますね。
田辺さんのお話からは、所与の制度の中でぬくぬくと居座り続けるだけでは、人類学者としては不十分だというメッセージを感じ取りました。その点で、私自身恥じ入るところがありますが、とても小さな試みとして私自身がやっている専門主義からの脱出は、コロナもあって海外のフィールドに行けない状況の中で、国内のフィールドワークを手探りで始めているというものです。
環境危機の問題とも関わるのですが、日本国内の産廃やゴミ問題などに関連する地域や施設などを巡っています。緊急事態宣言が開けた昨年の11月から毎月出かけています。ここ2年間フィールドに行けなかったわけですから、まさに「野(フィールド)に放たれた」と言いますか(笑)、フィールドに出ることは、現実に対して目を見開かされる機会だということだけではなく、こんなに楽しいことだったのかと改めて気づかされました。
何が専門主義からの脱出かというと、秋田公立美術大の芸術人類学者の石倉敏明さんが「共異体」という言葉で表現していますが、研究者と、研究者ではない実践家たちと一緒に本を読み、出かけて、異なる専門性を突き合わせて、いろいろ意見交換する中で、見えてくるものをそれぞれの作品や論文にするという試みだからです。具体的には漫画家や写真家と一緒に行動して、そうしたプロセスの中で出てきたアイデアや疑問を考えていくというやり方です。そうしたやり方は、そんなに新しいやり方でもなさそうなのですが、学知の内部で何かできるかというと、そういうことではないかと思って始めたわけです。
ただ田辺さんの話に比べて、それは、既存の学知をそのままにして、できうる範囲の揺さぶりであり、特段ラディカルなものではないので、別の角度から少しだけ述べさせて下さい。人類学で最近よく使われるようになったのか、たまたまなのか分かりませんが、“flip”という言葉が気になっています。エドゥアルド・コーンが『森は考える』(亜紀書房)で、人間と動物、動物どうしの捕食と被捕食の関係がひっくり返るエピソードを語るときに、“flip-flop”という表現で論じていました。それはかかとがないビーチサンダルのことでもあるのですが、ぺらぺらとめくれてひっくり返るということだと思います。MITの人類学者S・ヘルムライヒは最近“Flipping the Ship: Ocean Waves, Media Orientations, and Objectivity at Sea”という論文を書いています。船をひっくり返すという題の、波科学をめぐる研究です。
“flip”には、逆転させる、反転させるというような意味合いがありますが、そういう言葉が使われる背景には、人類学者たちの“flip”への「渇望」みたいなものがあるのではないかと睨んでいます。そんな言葉が使われるのは、端的に、人類学に“flip”性みたいなものが足らないからなんではないかと思っています。
何か価値観を反転させる、ひっくり返すというのは、人類学の「お家芸」だったはずです。ある種の「ちゃぶ台返し」。当然のこととして共有されていることを、最初からは共有しませんよ、という高らかな宣言こそが、人類学の人類学であるほぼ唯一かつ特大の「効用」のようなものだったはずです。そんなことないよという人がいるかもしれませんが、私自身はそう考えています。それは先程の生残主義とアルゴリズムの話とも関連しますが、既存の制度や枠組みの中で安んじて日々を送り、物事のエッセンスや真理を探究することを忘れてしまっている、いや最初から放棄してしまっているような学知は、人類学とは言えないということです。
もしかしたらそのような探究の営みは、人類学以外の人が実践するようになっているのかもしれません。先ごろ、NHKラジオの日曜カルチャー「人間を考える~現代を見つめる~」シリーズで、探検家の角幡唯介さん、経済思想家の斎藤幸平さん、そして私が順に話す番組があったのですが、それを聞いていて思ったことがあります。また、角幡さんは『極夜行』(文春文庫)という本を書いていますが、彼は北緯66度以北の一年のうち太陽光がない期間が4ヶ月になる地域を犬ゾリで旅して、闇の中で暮らす生活を送り、光がどういうものであるのかをいわば確かめに行ったのです。斎藤さんはご存知のように近年、彼の著書『「人新世」の資本論』(集英社新書)がベストセラーになりました。
私は個人的に角幡さんに強く共感を覚えたのですが、それは自分の持っている世界観や認識という前提そのものをひっくり返してしまうような発想であり、やり方です。他方、斎藤さんの場合、あくまでも資本主義の世界を前提として、コロナの次にやって来る気候危機をどのように乗り越えていくのかという問いなのです。資本主義からは一歩も外に出ていない。それは当たり前かもしれませんが、経済学者であり、経済思想家の正しい態度なのでしょう。
反対に、そういった学知にまったく染まっていない角幡さんは、光がない闇の世界に自ら出かけて行って、自らの全身全霊を賭けて「光を見るとはどういうことか」を探求している。前提の外へと、果敢に、いや無謀に歩み出ていく。どこかで命を危険に晒す危うさのようなものが感じられて、過激でもあるのですが、私は学問、とりわけ人類学に欠けているものが、これだと直観しました。おそらく人類学も元々はそのような学問だったはずなんです。戻って来れるかどうか分からない「蛮地」に出かけて行って、とにかく暮らしてみることができるかどうかを試すというような。
何が言いたいのかと言うと、専門主義が仮想敵だとすれば、田辺さんのお話とも関連すると思うのですが、人類学が持っていた“flip”性というか、「反転する力」を実践する学問たることに自覚的であることが大切だと思うんです。専門主義にていよく回収されてしまわないために。角幡さんのように、闇だけの世界で暮らすというのは非常に困難を伴うわけですが、それでもやる。そして、そこで根源から世界を問うわけですよね。それは、我々の暮らしの土台となっているある前提条件の上で物事を考えるようなやり方とは一線を画する学知です。
春日:確かに、私が大学院で人類学を学んだ70年代後半から80年代初頭にかけては、フィールドワークに対してそういうイメージがありました。とにかく「行け」と言われた。そして、帰ってくるときに何かある。何になっているか分からないけれども、何かあるんだというような、今みたいに調査用の保険なんか抜きで探究に向かうところがありました。少なくとも、フィールドへ行く前に博士論文の骨格をつくるという話ではなかった。
奥野:そういう意味では、『今日のアニミズム』で、人類学と哲学の対話を行ったように、人類学と哲学をツイストさせながら、それらの外側に出ること、外側を見ること、それはある種の「探検」のようなものだと思うのですが、外側を「探る」というようなことをしなければならない、という気概も大切だろうと思います。もし田辺さんが大学じゃ真理を探れないと考えておられたのだとすれば、それは我々も薄々感じていることであり、田辺さんの今後に期待したいと思います。専門主義がはびこっている限り、そのような挑戦は今後も続くだろうと思いますし、私も違った形で、どうなるか分かりませんが、何か実践すべきだろうと思います。
(了)
著者紹介
春日直樹
人類学。大阪大学名誉教授・一橋大学名誉教授。主な著書に『太平洋のラスプーチン ヴィチ・カンバニの歴史人類学』(2000年、世界思想社)、『〈遅れ〉の思考 ポストモダンを生きる』(2007年、東京大学出版会)。主な編著に、『科学と文化をつなぐ アナロジーという思考様式』(2016年、東京大学出版会)、共編著に『文化人類学のエッセンス』(2021年、有斐閣)などがある。
奥野克巳
文化人類学。立教大学異文化コミュニケーション学部教授。以文社より共著、共編著者として『今日のアニミズム』(2021年)、『マンガ版マルチスピーシーズ人類学』(2021年)、 『モア・ザン・ヒューマン』(2021年)、 『Lexicon 現代人類学』(2018年)を刊行している。
清水高志
哲学、情報創造論。東洋大学教授。井上円了哲学センター理事。主な著書に『実在への殺到』(水声社 2017年)、『ミシェル・セール 普遍学からアクター・ネットワークまで』(白水社 2013年)、『セール、創造のモナド ライプニッツから西田まで』(冬弓舎 2004年)などがある。主な訳書にミシェル・セール『作家、学者、哲学者は世界を旅する』(水声社 2016年)、G.W.ライプニッツ『ライプニッツ著作集第Ⅱ期 哲学書簡 知の綺羅星たちとの交歓』(共訳:工作舎 2015年)などがある。
![Read more about the article 誰がパリ五輪に抵抗しているのか?[第3回]/佐々木夏子](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2022/05/JO-Paris-2024.jpg)

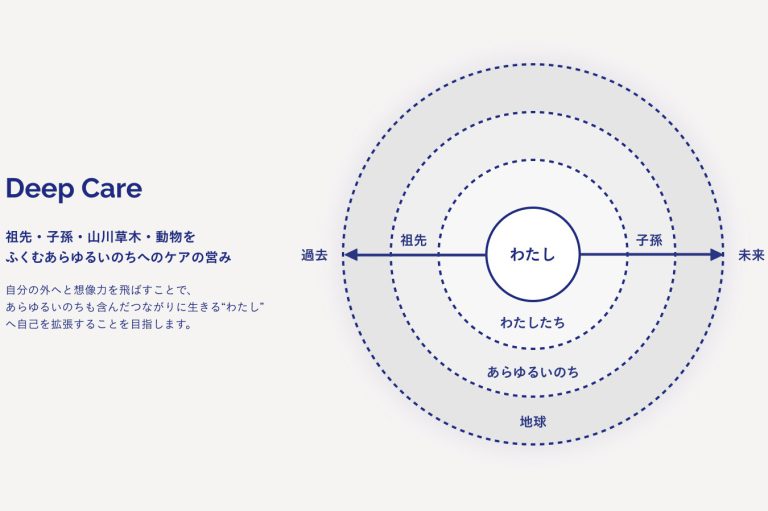
![Read more about the article 【連載】誰がパリ五輪に抵抗しているのか?[第4回]前編/佐々木夏子](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2022/12/図1.jpg)

