参与と融即のアニミズム
加藤学 × 奥野克巳 × 清水高志
小社では2021年末、文化人類学者の奥野克巳氏と哲学者の清水高志氏の共著『今日のアニミズム』を刊行した。本書は、岩田慶治が論じてきたアニミズムの再評価と同時に、人類学と哲学の領域を横断し、近年注目されるモノと人のネットワークを含む新たな存在論、そしてテトラレンマや浄土思想などの仏教の思想と論理からアニミズムの今日性の検討を試みた意欲作である。本記事は、共著者の奥野氏、清水氏に加えて、清水氏が有志と共に実施していたステム・メタフィジック研究会にも参加していた在野のディレッタント、加藤学氏をゲストに招き、同書の刊行を記念し鼎談を実施したものである(以文社編集部)。
二元論的世界を調停する「アニミズム」の原理
加藤:本書『今日のアニミズム』は、奥野先生と清水先生の独立した四つの論文と二つの対話から成り立っている書籍ですが、テーマはタイトルにもある通り、「アニミズム」です。
本書はアニミズムとはこういうものだというコンセンサスがあるような感じで始められているように思いますが、一般の読者からすると、「アニミズムっていわゆる原始的な精霊信仰のことですか」みたいなレベルの理解をしている方が多いだろうと思います。そういう人たちにとってはすぐに本書に入りづらいところがあるのかなと思いまして、まず今回の鼎談では、その部分をほぐしていきたいと思っています。
清水先生は「まえがき」で、「人類に普遍的に見られるアニミズムと呼ばれる思考と、そこで見出される自然を徹底的に考察し、思想としてそれがどれほどの深度を持ちうるものなのか、その限界まで探求しようとしたものである」と書いています。続いて「ブリュノ・ラトゥールやグレアム・ハーマンのような現代の哲学者の思索をも経由して、ナーガールジュナ、道元、原始仏教の英知に潜んでいた豊かな可能性が、さらにはその背後のアニミズムの活きた躍動する自然が、さまざまな二元性を超克して姿を現す」とも書いています。
この「アニミズムの生きた躍動する自然」というもののイメージが一筋縄では理解できないのではないか。例えばフィリップ・デスコラがナチュラリズムとして整理したような、「対象化された自然」であると一般的にはイメージしてしまうと思うのです。一方に人の主観があって、一方に客体としての自然がある、と反射的に考えてしまう。アニミズムの生きた躍動する自然とは、そういうものではない。それを内在的に記述しようとすると、主体による客体の確定記述という我々が普段慣れ親しんだ記法では記述できない。必然的に記述は非常にややこしくなりますね。
奥野先生と清水先生の対話の中でも言われていることですが、岩田慶治が書いていくときに、金太郎飴みたいに、「アニミズムはこうですよ」という公式を、さまざまな形で繰り返し反復して書いていくというところがある。それがアニミズムを記述するときの難しさであると感じます。「アニミズムの生きた躍動する自然」をどう記述すればいいか。例えば岩田慶治の「不思議の場所」という論考がありますが、そこには次のように書かれています。
伝統社会における空間の構造は二元的である。現世と他界があり、地上と天上の世界がある。娑婆と極楽といってもよい。二つの世界は表と裏のように背中合わせになっていて、たがいに顔をあわせることができない。二つの世界は断絶しているのである。二つの世界をつなぐ橋はない。しかし、だからといって二つの世界が永久に断絶したままであったら、そこに住む人間のこころに究極のやすらぎはないであろう。世界の分裂が人間の分裂をひきおこすからである。そこで人間は何とかして、おのれ自身のうちに、同時に、二つの世界を映そうとする。二つの世界のただなかで一元的に生きようとする。そういう一つのねがい、一つの祈りをもっている。その点ではキリスト教といい、原始宗教といっても少しも相違はない。人間のこころの出所は一つである。万法帰一である。万教帰一である。(岩田慶治、「カミの人類学――不思議の場所をめぐって」『岩田慶治著作集』3巻、106頁)
このように、「二つの世界を一元的に生きようとする」ということを、岩田慶治は繰り返しさまざまな観点で書き続けているということだと思うのです。
「二つの世界を一元的に生きようとする」ということについて、奥野先生が書いた「第一章 アニミズム、無限の往還、崩れる壁」では、メビウスの帯というモデルを立てています。
二つの世界を一元的に生きる。例えば西田幾多郎はこのことを「絶対矛盾的自己同一」という概念で表しました。矛盾しているものが矛盾しているままで同一性を実現していくということですね。奥野先生は、この点をメビウスの帯という形で表現されている。二面の一元的な生と言いますか、そのようなイメージがつかめていないと、やはりアニミズムの自然というのはいわゆるデスコラが定義するナチュラリズム的なものとしてしか、読者の中に入っていかないのではないかと思います。
ティム・インゴルドが言う「メッシュワーク」――この概念は、「生成」と「構造」を折り合わせようとするようなものですが――、これもまた「二つの世界を一元的に生きようとする」ものと言えるかもしれません。それが、岩田慶治的なアニミズムの一つの核になるのではないかと思います。
アニミズムについて何かを言うと、岩田慶治もインゴルドもそうなのですが、同じことの繰り返し、金太郎飴のように言えてしまうところがある。これをいかに、より根底的な形で公式化するかということが重要になってきます。岩田が言うような、二元を一元として生きるというようなある種、詩的というかメトリカルな表現ではなく、哲学的にもう一つ掘り下げた次元で公式化していくことはできないか。本書で清水先生が書かれているトライコトミー、三分法というのは、要するに、トライコトミーと言うのはアニミズムの一つの公式化である。そのように捉えられます。
その公式が世界の中でどのように作動していくべきか、あるいはどのようにし損ねているのかということが、言ってみれば本書の後半でナーガールジュナや道元を参照しつつ論じられる救いや救済の問題に繋がっていく。このくだりが本書でも最もエキサイティングな箇所ではないかと思います。
奥野先生の二つの論考は、恐らく奥野先生自身の実存的な問題みたいのもあるのかなとは思うのですが、「救済」というものは最初から全部一緒にして提示されているとも読めるところがあります。
今日、奥野先生、清水先生にお聞きしたい焦点は、二点です。一点目には、アニミズムというものの定義、公式について。そして、二点目、そのアニミズムの公式がどのように「救済」――それは世界の救済でも自己の救済でも構わないのですが――に繋がっていくのか。
まず、第一の論点として、アニミズムの公式というのは何か。清水先生の論考ではトライコトミーとして提示されています。改めて、簡単にこのトライコトミーとは何なのか、まず清水先生にご説明いただければと思うのですが、いかがでしょうか。
清水:例えば、僕たちが生きる世界があって、それに対して死の世界がある。あるいは人間と自然というように、一見分離している2つの世界をいかに分離のままに終わらせないで生きるかということが『今日のアニミズム』において、大きなテーマとなっています。それは、岩田慶治などもそうです。岩田の場合は人類学者ですから参与観察ということが大事で、自分がフィールドワークする対象の中にいるわけですが、もう一つ、その状況を俯瞰して眺めている眼を持っていることが重要なんですね。
これまでの哲学では、二元性の超克ということを考えるとき、一種の二重性の中だけで考える向きが強かったと思います。主体と対象にしても、精神と現象にしても、二重性の文脈に落とし込んで二元論を解いていこうというモデルがたくさんありました。例えば思考の主体がまた思考の対象にもなりうるという風に、順繰りに内部に繰りこんでいく。ドイツ観念論やドイツロマン派がそうなのですが、こうした二重の構図の中で内在と超越(「内/外」)という問題を解いていくという発想が伝統的にある。しかしこれでは解決になっていないのではないかと僕は思ってきました。どこまでも終わりのないプロセスでしかあり得ませんから。すでに述べた参与観察というものも、もっと違ったものであるべきだと思ったのです。
もう一つ、僕は「一/多」という問題を考えたかった。僕たちにはもちろん個別の実存や生があるわけですが、どうやったらそれが世界そのものの普遍的な形につながり得るかというのは、人類にとってきわめて重要な問題です。永遠のイデア的世界と日常の感性的な世界、「普遍/個別」の分離や二項対立といったものがある。「一/多」は、この原初の二項対立をもう少し通常のものの様態のほうに寄せた、より具体的な二項対立です。
近代西洋的な世界観は、主体が対象に対して優勢な二元論であるとよく言われます。じつはこうした場合には、おうおうにして主体と対象だけでなしに、別の二元性がすでに混ざってしまっているものなんです。例えば主体はもろもろの現象を整合・統合するものだと考えられているし、そこでは現象は雑駁で多なるものであるとされる。「主体/対象」と「一/多」が無自覚なまま混淆しているんですね。「一/多」は、多少なりとも具体的な二項対立でもあるから、こんな風に他の二項対立と混じりやすい。――こうした事情はじつはプラトンの時代から知られていて、例えば《一なるもの》と《多なるもの》のイデアについて考察しながら、「その《一なるもの》はまた《同なるもの》であり、《多なるもの》は《異なるもの》でもあるのではないか?」といった具合に、対話篇の中でソクラテスらは複数の二項対立の混淆を繊細な手つきで注意ぶかく分離しようとしている。哲学の歴史の中で繰り返し採り上げられ考察される諸概念は、そもそもそんな風にして生まれてきたものなんです。
ところが最近になって、面白い着眼点がでてきたように僕は思うんです。例えば哲学者で人類学者であるブリュノ・ラトゥールなどの議論を見ると、こうした複数の二項対立が混淆し、それらが組み合わさっていることを自覚しながら、しかもその組み合わさり方を敢えて変えてみたりしている。――これは新機軸だ。こうした操作をすることで、それらの項が別のものであることをはっきりさせることができるじゃないか! 僕はそう思ったんですね。
詳細は本をご覧になれば分かりますが(笑)ラトゥールの科学人類学では、「対象が一つあるのに対して、主体のアプローチが複数あって競合している」といった場面から状況を捉え、科学技術のイノベーション等が起こる現場を分析している。――このとき結果として主体よりもむしろ対象じたいが、もろもろの主体が予期せぬ状況をもたらすといった能動的な役割を果たすというのです。この場合、もろもろの主体と対象の間には循環的な相互作用が生まれますが、優位に立っているのはむしろ対象のほうです。二つの二項対立の組み合わせをツイストすることで、能動性の役割が入れ替わる、ある意味やっと対称性がそこで成立することになるわけです。
僕の考えでは、そこにさらにもう一つの二項対立をうまく組み合わせれば、何にも還元せず、どの項もばらばらに区別し、かつ起こっている循環も閉鎖的なフィードバックループではなく、多分岐的なものになるモデルが作られるはずなんです。
僕は以前、『実在への殺到』(水声社)という書物で、哲学の《幹-細胞》にあたるものを模索しようと試みました。上妻世海がメンバーを集め、加藤さんが参加されていたステム・メタフィジック研究会というのも、それを領域横断的に展開した研究会だったですね。そうした主題を宗教という意味で言うなら、アニミズムという形がまさに《幹-細胞》的なものだろうと思うんです。例えばそれが、岩田慶治が生き生きと描いているもののうちに読めるのではないか、道元も同じように読み直せるのではないか。『今日のアニミズム』で考えたことの大枠は、そういうことですね。
加藤:ありがとうございます。清水先生がトライコトミーによって議論している中で「こうすると二元性というのは調停できる」というように、「調停」という言葉がよく出てきますね。そもそも「調停」というのは一体、どういうことを指しているのでしょうか。「一即多」や「内即外」というように、二元性を「即」で繋いでいく、「即」の論理というのがあると思うのですが、この「即」の論理がどのように実現されるのか、言ってみれば、「調停」というのは、「即」ということなのでしょうか。
清水:まず二元論がなぜ二元論になってしまうのか、そこには原因があるわけです。それは排中律が成立する条件が成立しているということです。例えば、「このものは白いものである」と言えば、それは黒いものに属してない。これは二元的です。同時に違うものに分類的に属することはあり得ない。その場合は、かならず個別なものがより普遍的な述語に属するという形態になり、アリストテレスの論理学では種や類というものをそのように分類します。ただ、個別のものがより普遍的なあるイデアの性質を分有するということにしてしまえば、反対のイデアが同時に同じものにあるということが言えるのではないか? 例えばこのリンゴは砂粒よりも大きいし海よりも小さい、ということは言えるわけです。二項対立が第三項的なあるものの属性であるということになれば、そのときそれらの二項対立は「即」調停されるというのは、古代ギリシアの頃から知られており、プラトンの『パルメニデス』などでもすでに論じられているんですね。
ただ、分有(participatio)するのだというと、それはその分有されるイデアの部分に過ぎないのではないか? だからやっぱりすべてを含むイデアがあるのだ、という反論が可能で、対話篇でもパルメニデスは結局それがすべてを含む「一なるもの」であって、それだけが存在するのだという風に反駁してきます。こんな風にして「含む(外)/含まれる(内)」という二項対立が、調停不可能なものとして出てくるわけですね。
さらにプラトンの後期の『ソピステス』では、わざわざ「エレアからの客人」というパルメニデスの弟子を登場させて、この問題をなんとか解こうとしています。そこでは「~がある(有)」ということの反対にくるものが「無(非有)」ではなくて「~であらぬ(異)」なのだと主張される。そして「~であらぬ(異)」ものが「ある」、という風に述語づけることが可能だというんです。つまり、いったん述語であったものをまた主語の位置に置き直して、さらに述語に包摂する、というループを作って、「含む(外)/含まれる(内)」関係をなしくずしにし、「一なるもの」だけでなく「異なるもの」つまり「多なるもの」を増殖させてやるという戦略を採るのです。
これはギリシア風の弁証法ですが、このようなロジックはスコラ学に引き継がれ、山内志朗氏によるとドゥンス・スコトゥスを経てジル・ドゥルーズにまで非常に強い影響を与えているんだそうです(笑)。これもまた、印欧語におけるBeingの二重性(「~がある」と「~である」)の二重性を使った一つの解法ですね。しかしこれは同じところをぐるぐる回り続けるロジックでもあり、「異なるもの」であること、差異がどこまでもそこでは自己目的化されることになる。この循環はドゥルーズによってニーチェの永劫回帰の思想にも重ねられますが、差異の哲学と呼ばれたポスト構造主義までそれが尾を引いているわけですね。
ところで面白いことに、こうした「~がある」と「~である」の循環、そのショートサーキットを、ナーガールジュナは『中論』の第二章で延々と反駁しています。これは同じく以文社から刊行された『モア・ザン・ヒューマン』で師茂樹さんと話したことですね。古代ギリシアの哲学、ひいてはヨーロッパの哲学の中にある終わることのない循環のロジックのようなもののうちに危険を感じて、違う道を模索したのが一つにはインドの哲学だったのではないかと思います。――彼らが模索したのは、不生不滅とか、不同不異とかいう風に、「Aと非Aどちらでもない」という形で二項対立を調停しようとすることです。第三項をだして、「Aと非Aどちらでもある」とするだけではなく、第三項の位置を循環させて、ついには「どの二項対立の項にも還元されない」というあり方を見いだす。テトラレンマの第四レンマと呼ばれるものですね。
ちょっと説明しておくと、テトラレンマというのは、四句分別とも呼ばれますが、インド人が大昔から用いている論法です。①A、②非A、③Aかつ非A、④Aでもなく非Aでもない、という風に、Aという命題について四通りの命題を列挙するものです。西洋の論理だと非Aまでか、せいぜい第三レンマのAかつ非Aまでですが、インド人はこの第四レンマまで語って複雑な議論を展開しないと気がすまないんですね。
そうして生まれたインドや東洋のロジックはきわめて複雑で高度なものだが、その一方で残念なことに西洋風の《オッカムの剃刀》という発想、つまり重要な概念を必要最小限に絞って議論を展開するというところがない。それによって余計に勘所が分かりにくくなっているんですね。――例えば華厳の思想においては、世界の成り立ちや事物の関係を説明するにあたって十個ずつの異なるパターンを列挙するのを好むのですが、その数には特に必然性があるわけではない。ただ「十」が好きと言うほかない(笑)。インドの思想家で論理を削ぎ落としていき、数を絞ったのはナーガールジュナだけですね。彼は『中論』の冒頭においてテトラレンマで表現できる真理を、「八不」という四種類にまで絞った。ただその選択がベストだったかは考える余地がある。その後、法華一乗や華厳の思想が出てくると、「一/多」という二項対立がきわめて重要なものとして浮上しますが、「八不」の時点では組み込まれていないからです。
ナーガールジュナがキャッチしたアニミズムからの流れも含めて、哲学的にも宗教的にも《幹-細胞》的な基本構造を絞り込みたいと言うのが今回の僕のもくろみで、これをうまく絞れば違ったヴァリエーションにも柔軟に適用できると思うんです。そうであってこそ、西洋思想が壁にぶつかったところを突破したり、現代社会を再考したりするのにも応用できるようになるんじゃないかと思う。
一番抽象的な関係構造としての「含むもの(外)/含まれるもの(内)」の二項対立を調停するために、それが感性的な世界に現れたあり方としての「一/多」という二項対立をまず採り上げ、アニミズムの自然を扱う本書ではそれを「主体/対象」という二項対立と組み合わせている。その組み合わせ方の変奏も織り込んだうえで、これら三種類の二項対立をすべて合流させると、さらに第三項としての位置をすべての項が採りつつ、原因がどの項にも還元されないという第四レンマの状態が脱-時間的に成立する。これが「即」であり、また「調停」です。それによって、感性的な情念の世界と、抽象的で恒久不変な世界が融和する。――人類が古くから、なかば無意識的に考えてきた「救済」というのは、大方そんなものだったのではないかと僕は思っています。
加藤:そうしたロジックというのは、本書でもかなり精密に論じられていると思いますが、最終的なイメージとしては、すべての存在物が対称性において成り立っている、というように受け止められると思います。つまり、削ぎ落としていって、「内/外」と「主体/対象」と「一/多」の三つの二項対立が組み合わされると、すべての対称性が実現するというような考え方です。
奥野:シンメトリーということですね。
加藤:ええ。シンメトリーが最終的なビジョンとしてあるのかなと受け止めたのですが。
清水:そうですね。シンメトリーの三すくみのような構造を作りたいわけです。
加藤:三すくみにすることで、議論がこぼれず、シンメトリーが最終的にそこで実現する形が定義できるというイメージです。そのような状態をイメージしてみますと、先ほど挙げていただいたステム・メタフィジック研究会でも、関係と項を考えるとそのいずれもが相互に包摂している、というような言い方をしていたように思います。
清水:それが最も大事なところだと思います。二項だけの論理や二重性に立脚した論理からは、本当の複線性や多様性は生まれなくて、未解決の課題になるだけです。例えばインドでもヨーロッパでもそうなのですが、「~である」と「~がある」とが混じり合い、閉ざされた循環になるような説明に陥ることがよくある。ある様態aであるとき、その主体aを勝手に立てて、様態の原因をその主体aに帰して、「主体aがあるから様態aであるのだ」というように、原因と結果がループするロジックを立てて納得してしまうわけです。
言ってみれば、それは自己原因的な項を立てるということです。仏教的に言うと《自性がある》ものを想定するわけですが、これは一番シンプルな還元主義です。では他が原因ならば良いのかというと、その他が原因となる形でもろもろが還元されるというのでは同じことになる。非還元的でどこまでも多様、かつ複線的な世界のもろもろのパースペクティブを描こうと思ったら、いったんトライコトミーで語った内容を経由してテトラレンマにいくしかない。主語的な項に還元されないということは、項から関係がボトムアップで作られていくのではないということ、項と関係が二項対立的でなく、フラットなものになるということです。スケールフリーな相互包摂の世界、これは人間を含むさまざまな生き物が、お互いの異なるパースペクティブのうちにお互いを包摂し合っている、そんなアニミズムの懐しい深い森の世界のことでもある。
今回の鼎談に先立って奥野さんの論考も読み直してみたのですが、アイヌやクマにとっての神という存在、つまりクマがカムイであるような世界というのはこの地上の世界とは別に他にあるわけではないと書いてあったのがあらためて面白いなと思いました。クマ的パースペクティブと、われわれがみているパースペクティブがあり、この地上自体が多自然的にあるわけですね。
アニミズムは神道ではなく仏教である
加藤:このトライコトミーのロジックとは異なる文脈になりますが、インゴルドが「メッシュワーク」という概念を出していますね。ネットワークの場合、先に項が立つことになるわけです。項が立ったうえで、その項の間を能動的に繋いでいく。これがネットワークの構造です。しかし、じっさいは、その項自体が実は生成的なものなので、項というものが実体として存在するわけではない。だから、生成と生成がネットワーク上になっているという意味でメッシュワークという概念が出されている。項として存在するのは実体的な存在ではなく生成、つまりbeではなくてbecomeである。become同士の関わりがあるのであって、be同士のネットワークではない。それがメッシュワークだというわけです。
では、なぜインゴルドはメッシュワークということを言わなければならなかったのか。それは今、清水先生が言われたように最初に項を立ててしまうとすべて二項対立に落ち込んでいくからなんだと思うのです。メッシュワークということはつまり、項というものが生成としてしか存在しないわけで、結局のところはどこにも固定点がないということです。固定点がない状態で、すべてが関係し合って、すべてが変化し合っているっていう相依的な構造になっている。
いわゆる生成論では、どこにも主体や客体のようなものはなくて、すべてが生成の中に入ってしまっている。そうすると、一個の生成しかないというところにまた回収されていってしまう。しかし、メッシュワークとすることによって、生成自体が多数であるというところで、生成同士の多数の構造として捉えることで、一と多とが調停されているという状態が考えられていると思ったんですが。
清水:非常に難しいところですね。先ほど述べたプラトンの弁証法では、beingの二重性をめぐって循環し、「異」なるものを増殖させ、永久にそれを駆動し続けていないといけない。それがスコラ学になると個体化の原理となり、そうして個体化したもののいずれにもbeing、つまりあることが述語づけられることを、ドゥンス・スコトゥスは「存在の一義性」というふうに呼んでいる。時代は下ってニーチェは「神が死んだ」と言いましたが、個体化の原理がさく裂するさなかで、ニーチェ自体も人格としてのニーチェを超えたところで、世界の生成を見ているようなところがある。「異」なるものの循環的生成が、相変わらず念頭にあるわけですね。ただ、人類学者の語る生成や制作は、そこまで形而上学的に壮大なものではなくて、良い意味で局所的でもあって、そこにかえって可能性があると僕は思うんです。――どんどん巨大化しつづける循環の中での生成ではない。例えばラトゥールもやっていることは一種生成論的でイノベーション論なんですが、それはメッシュワークの一部なんだと思います。
加藤:ラトゥールの理論はある意味分かりやすいところがあります。すべてが依存し合っているという、一つの限定された状況をまず前提として想定していますね。ミシェル・セールが言っていたサッカーボールとサッカー選手という例をラトゥールも使って、アクターネットワーク論を展開しています。要するにサッカーという一つの状況を前提として、そこで相互のアクターが依存し合うというか、影響し合うわけです。限定した状況を見れば、すべてが絡まり合っている、影響し合っているという状況が浮かび上がってくるということだと思うのですが、本書でアニミズムとトライコトミーの議論が行き着きたいビジョンというものは、より包括的な視野を開いてくれます。つまり、状況に非依存的な状態というのはいったいどういう状態なのかということを最終的には描きたいことなのかなと思ったのです。
ラトゥールの議論というのはすべて状況論として回収されてしまうところがありますね。さまざまな状況をまず設定しないとラトゥールの議論というのはおそらく成り立たないだろうと思います。『今日のアニミズム』でも奥野先生も清水先生も言及しているユカギールの場合もそうですが、狩りということを前提にしないと、エルクと狩人の関係性というのは出てこないのだろうと思います。そうした状況を全部排していき、状況に対して非依存的であるということがどういうことなのか、ということです。
清水:エルクの狩猟の話というのは一種の、イマーゴとして現れた動物と人間の狩人の関係ですよね。そこから抜け出したものを狩人は持っているから狩りができるわけで、そういう感性が重要だと僕は思います。つまり、そこをどう抜けていくかということが生き方を問うことではないか、と。抜けるということはやはり哲学であり、知なのだと思うのです。それが仏教の場合だと、戒律を守るなどさまざまな形がありますが、結局、情念が自己増殖する狭いループのようなものからどう楽になっていくか、ということですよね。自分を投影した自然じゃないものもそこで現れてくるということが大事だし、狩人はそうやって自分がある意味、その状況から抜け出しているものでもある。
加藤:そこがとても面白いと思います。何が面白いのかというと、奥野先生の議論の中でもありましたが、アニミズムと言うときに、状況に依存していない、より根底的な哲学的問題を完全に解決していかないと、結局「人間が思っているだけだ」というところに再回収されてしまう。簡単に人間中心主義に再回収されてしまうのではないかということです。
ユカギールの話で言えば、エルクの側はそんなふうには見ていないという言い方もされ得るわけですよね。主体/対象というのが解決されていないわけで、最終的にアニミズムの話がすべて、人間の信仰に過ぎないというふうに回収されてしまう。これをどう解体するかというところを哲学的に掘り下げたのがトライコトミーではないか。
これは奥野先生が人類学的なフィールドの中で考えているところだと、亜紀書房から刊行された奥野先生の著書『絡まり合う生命』では、エドゥアルド・コーンの議論を出すことで、生命論的なところへと接続させて、主体に回収されるわけではないということで解かれているのではないかという気がしたのですが。
あるいは『モノも石も死者も生きている世界の民から人類学者が教わったこと』(亜紀書房)でもそうした問題を書かれていたのではないかと思います。同書では確か、こんまりさんの例を出されていましたね。彼女の考え方はアニミスティックとされているが、じつは主体優位の考え方じゃないか。その疑問が同書の最後まで問題意識として継続されている。いわゆる伝統社会で言われてきたアニミズムというのは、主体優位なのではないかということが葛藤的に論じられている構造だったように思います。それが『今日のアニミズム』、そして『絡まり合う生命』(亜紀書房)を通じて、より生命論的な方向へと抜けられているという印象を持ったのですが、その点はいかがでしょうか。
奥野:はい、それでは、最初加藤さんからご質問いただいた第一の点、アニミズムの定義、公式に関して、三点に絞ってお話したいと思います。
まず、加藤さんのおっしゃる通り、拙著『モノ石』では、こんまりこと近藤麻理恵さんの話から始めています。彼女はSpark Joyという言葉を使っています。部屋が衣服や雑誌やさまざまな小物や何やらでいっぱいになってしまって、捨てないといけないのだけれども捨てられずに困っているという状況で、残すモノと捨てるモノを選別する方法として、モノを手に取ったときにSpark Joyを感じたら残すほうに分類するというわけです。逆に、モノにSpark Joyを感じなければ捨ててしまう。つまり、モノに対する態度に一種の背反があるのです。Spark Joyを感じたモノは残すけれども、感じないものは捨てるという。これがこんまりさんの片づけのロジックです。
こんまりさん自身、アメリカでは日本から来たアニミストだとみなされている節があって、彼女の片づけの手法がアニミズムだとされることがあるのですが、しかし本当にそれをアニミズムと呼んでいいのだろうかという問題意識が、私にはありました。
そのような前提で、アニミズムを考え始めました。冒頭で加藤さんが述べられた「二つの世界を一元的に生きようとする」岩田的な図式のようなものを想定した上で、特に非西洋の人々はどう捉え、どう表現しているのかという点から見ていこうと。そこで最初に、一方的に人の主観があり、他方で客体としての自然があるという、デスコラ的な「対象化された自然観」としてのナチュラリズム的なものから入って行ったわけです。主観と客体、人と自然が、人類学においてアニミズムの典型例とされるアイヌのイヨマンテではどうなっているのかというと、主・客や人と自然が、表と裏の区別なく、シームレスに繋がっているという見立てです。そういう具合に、アニミズムは、人が主体として、客体としての自然に対峙する「対象化された自然観」によって成立しているのではなくて、人と自然に区別がない、つまり人間だけが地球上における主人ではないという思想なのだと考えました。
人間は、特に現代では、人間と人間だけが交わる世界の中で物事をあれこれ考え、行動することが多いのだと思います。植物や動物、モノなどのノンヒューマンは、ヒューマンから分断されて、そうした人間世界の外部に位置づけられています。現代世界では、ヒューマンとノンヒューマンの関係は、さきほど清水さんがおっしゃったシンメトリー(対称性)の逆、ヒューマンが優位でノンヒューマンが劣位に置かれるアシンメトリー(非対称性)になっているわけです。
アニミズムでは、ヒューマンとノンヒューマンのバランスがシンメトリカルだというのが決定的に重要なのではないかと考えました。ですから、こんまりさんが、片づけを指南するときにやるように、人間がSpark Joyを感じなかったら、モノを捨てよと言うのは、人間が一方的にその価値判断をしているという意味で、人間優位のアシンメトリーの土台の上で行われていることになります。ただし、こんまりさんは、モノを捨てるときには、「今まで私を支えてくれてありがとう」と言うようにも指南しているので、そこにはモノに対する情念の通路のようなものがある。その片づけ法は、必ずしもアニミズムでないのだとは言い切れないのかもしれないのですが。いずれにせよ私は、現代の片づけコンサルタントの振る舞いや言葉のなかに、アニミズムを考えていくための手がかりがあるように感じました。これが、私が描いたアニミズムの公式の1点目です。
次に、アニミズムの話からは少しズレてしまいますが、2021年11月末に九州大学行われた日本記号学会のシンポジウム「人間ならざるものの生命――哲学と人類学の交差から」で、増田展大さんの司会進行で、檜垣立哉さんと対談させていただいたのですが、その時、エドゥアルド・コーンやアナ・チンを取り上げながら、檜垣さんは「非人間主義」という言葉を使われていました。私は、これはいいなと思ったのです。非人間を主体と言っていいのかどうかは分かりませんが、非人間の力や、非人間を人間と同等ないし同等以上のものであると評価する際に「非人間主義」というのはなかなかいい言葉ではないかと。
私なりに解釈すると、ノンヒューマニズム、「非人間主義」というのは、人間が退いてしまっているんです。まずノンヒューマンがいる。そうやってみて初めて、ヒューマンが退いて、あらゆる種やモノであるノンヒューマンとヒューマンが一線で横並びになるように思えます。
またそのことに加えて「非人間主義」は、ノンヒューマンがヒューマンのほうに働きかけてきたり、自然が人間のなかに入ってきたり、あの世がこの世に入り込んできたり、死が生に組み入れられたりする・・・という意味合いまで包摂できそうな気がします。
人間主体で物事を進めていくのではなくて、むしろ人間が非人間に進めさせられるような契機をはらんだ実践とでも言いましょうか。それが、「他力論的アニミズム」という言葉を用いて本書の後半で表現していますが、私が提示したアニミズムの見取り図の2点目です。
三点目ですが、アニミズムは一般的には、神道以前の精霊信仰、古い日本人の信仰形態のように捉えられているということでしたが、今から150年ほど前のエドワード・タイラーの名づけと定義以来、精霊信仰というのがまかり通っていて、アニミズムはこれこれしかじかなものであると、正面切って論じられてこなかったのだと思います。20世紀の後半から今世紀にかけて、南米の先住民社会のフィールドワークをつうじて、フィリップ・デスコラやヴィヴェイロス・デ・カストロらは、それを、主体と対象の間の内面における連続性、あるいは精神的なつながりと唱えることで、この不動の事態に揺さぶりをかけたのです。
一般論としては、木や石、山に魂が宿るというような考え方や現象を捉えて、それを「アニミズム的だ」とよく言うのですが、実はアニミズムというのは一体何なのかはっきり示されないままである。そういう状況がずっと続いてきていて、清水さんとともに本書『今日のアニミズム』では、それぞれの学知を踏まえつつ、さまざまな他のものも混ぜ合わせながら踏み込んでいったことになります。ですから、高校の日本史の教科書に載っているような、アニミズムとは日本の古代信仰というアバウトな理解を超えて、これを機により広く、アニミズムについて議論がなさるようになればいいと思っています
その上で、やや振りかぶって言うと、本書で分かったことの大きなことの一つであり、私のアニミズムの公式の第三点目は、アニミズムとは「神道」ではなく、「仏教」だったということです。私は幼少の頃からわりと仏教的な風土で育ち、インド周辺で上座部仏教の仏僧もやったこともあったのですが、清水さんの仏教思想の探究に大いに刺激を受けて、ふたたび仏教に引きずり込まれていったことと相まって、仏教からアニミズムを眺める手がかりを得たような気がします。
これまで一般的に考えられたように、多神教的な神道の中にアニミズム的なものが潜んでいるというのではどうやらなくて、ロジックとして言えば、アニミズムは仏教だということが、本書の中では語られているのではないでしょうか。そもそも、岩田からして、仏教でアニミズムを語っている。アニミズムは禅で、シャーマニズムは浄土教だと。
それから、先ほどからお話しされていることをうかがっているなかで分かってきたのですが、清水さんは、西洋の形而上学の伝統を踏まえながら、現代哲学を隅々にまで把握し、それらに東洋思想あるいは仏教哲学を接続して、トライコトミーの論理を突き詰められたわけです。それに対して私は、人間のことを調査して語りますよとだれ憚ることなく公言してやってきた、人間をど真ん中に据える「人間主義」を肥大化させてきた人類学というものをどう考えていけばいいのかという問題意識を抱きながら、アニミズムという学問創設以来の主題に引きずり込まれ(笑)、清水さんの洞察にインスパイアーされながら、人間を含めたスピーシーズ(種)、人間を含めたライフ(生命)という主題のしっぽが見えてきたように思います。スピーシーズとアニミズムの同型性は、先ほど加藤さんが挙げてくださいましたが、ほぼ時を同じくして単著出版した『絡まり合う生命』で主に論じています。
メッシュワークとしてのアニミズム、汎生命論・汎記号過程としてのアニミズム
奥野:清水さんのトライコトミーの論理に関して、先ほど加藤さんは、そこには、項を先に立てて、項の間が能動的に繋がっていくようなネットワーク構造ではなくて、いわゆる無始無終の流れの中で生成どうしの多数の構造としてのメッシュワーク構造が想定されているのではないかと述べられました。最近私は、『週刊読書人』で、ティム・インゴルドの『生きていること』(左右社)の書評を書いたのですが(2022年1月21日号)、インゴルドは、アクターネットワーク理論とメッシュワークをとても対比的に語っていることを改めて確認しました。関係が複雑に織り成されるさまを、アンリ・ルフェーブルから借用して、メッシュワークと名づけている。それは、線描の縺れ合いであり、点と点を結ぶネットワークと比較されうる。
清水:アリ(ANT)とクモ(SPIDER)と言っていますよね。
奥野:そうです。アリ(Actor Network Theory)とクモ(Skilled Practice Involves Developmentally Embodied Responsiveness)です。クモは、線(ライン)的なのです。ラインを作り出していく。結び目が寄せ集められたネットワークではなく、糸と経路の絡まり合いであり、紡ぎ出していく生成の過程そのもの、プロセスそのものが重要だという点をインゴルドは強調します。それがメッシュワークだと論じているのですが、発達して身につけたクモの応答から構成されるようなものだというのです。そしてそれ自体は、私が出したような、表も裏もなく一繋がりになった「メビウスの帯」でもあるように思います。また清水さんが提起されている「内/外」「主体/対象」「一/多」というトライコトミー、あるいはテトラレンマ的なものとして理解することもできるということだと思います。
清水:そうですね。ラトゥール自身が初めて「非還元」ということを言ったわけですが、これは二項対立のどちらにも還元しないということで、まさにAでも非Aでもないという考え方です。こういう思考はヨーロッパではこれまで出てこなかったものだと思います。
ポストモダンでも、あるいはドゥルーズでもそうですが、「Aであらぬがある」とか「Aがあり、かつAであらぬがある」ということ自体、タイムラグを含んだものであり、循環的に発展しつつ「異」なるものを出していかなければならない理論だから、いずれにせよ、それは第三レンマです。
ラトゥールは、ヨーロッパの思考で初めて同時にどちらでもないということを言おうとしている。彼は人類学者でもあるわけだから、複数の二項対立を混ぜているということは自明だろうと思います。しかし、ドゥルーズのような「存在の一義性」や内在かつ超越の論脈に寄せてラトゥールを読もうとすると、「内/外」の二重性や主客の関係を内在化するという話が強調されてしまって、結局、「一/多」の問題が置き去りになってしまう。アニミズムをトライコトミー的に考えるように、あらかじめ「一/多」の問題をねじ込んでおけば、メッシュワーク的な断片と断片どうしの複数の関係も語れるし、おそらく間接的に全体についても展望できるんです。
世界の全体像としては、相互包摂で一即多のモナドロジー的体系を考え、さらに生滅を離れた第四レンマ的なあり方まで考える。それらすべての構造を同時に作ってしまおうというのが、僕の考えていることなんです。
加藤:先ほども述べたように、生成の内部にあるものとそこから疎外された個物が、さらにより根底的な視座においてはやはり相依的であるという、そのことを組み込んでいかなければ、「一/多」問題が解決されない。
清水:お互いに含みあっていて相互包摂的でありながら、生成としては別々である構造というのが考えられないと、巨大な一つの生成プロセスになってしまって事態が収束しない。「内/外」の二項対立と組み合わされてこそ「一/多」問題も解けるということですね。
現在の科学技術社会論(STS)でも人類学でも、断片的な状況の分析はしますが、そこから全体を展望する理論を作ろうとしたら、相依的というか、ばらばらに相互参照しあう総体としてのネットワークというものを考えざるをえないと思います。ラトゥールとともにミシェル・カロンがアクターネットワーク理論(ANT)を生み出すにあたって参考にしたミシェル・セールの「翻訳」という概念は、そもそもさまざまな領域をまたいで知のモデルがモナドロジー的にあちらからこちらへと相互参照される、という意味だった。サイエンスの全体的展望においても、まずそこに還らないといけない。
奥野:アクターネットワーク理論(ANT)を乗り越えていくというのが、清水さんがトライコトミーを出された出発点にある問題意識ですね。
清水:ええ、その通りです。アクターネットワーク理論(ANT)を扱う人は、一橋大学の久保明教さんなんかもそうなのですが、アクターネットワーク理論(ANT)は面白いのだけれどもそれを乗り越えたいということをよく言うわけですね。その乗り越える方向じたい、内在かつ超越という乗り越え方ではなくて、「一/多」の問題をしっかり組み込んだうえで乗り越えていく。これが僕の考え方です。
加藤:清水先生は、『今日のアニミズム』の78ページで、次のように書かれていますね。「主体は一なるものでありながら、世界そのものを《作るもの》としての主体、あるいは主体たちとそのままで別のものではない。――そうしたものとして働き、またみずからをも《作る》。これはいわば、汎生命的な世界の網の目である。アニミズムが直覚している世界とは、まさにこのような充満の世界ではないだろうか」。
この文章を読んで思ったのは、充満の世界のイメージとは、エドゥアルド・コーンが描き出しているような汎生命論的なイメージなのではないかということです。コーンの議論では、生命自体が記号過程であるというような前提があるわけですが、それは汎記号過程的な世界と言ってもいい。導き出されてくる理路は異なるのですが、最終的なビジョン、イメージというものは共通するのではないでしょうか。
清水:世界そのものが記号過程、推論の過程としてあるというのは、エドゥアルド・コーンを読んでいてもそういう解釈になると思います。記号学会で奥野さんは檜垣さんと対談したとのことでしたが、チャールズ・サンダース・パースの記号論への関心が檜垣さんにも早くからあるので、そうした本格的な対話ができるのだろうと思いますね。この《記号過程としての世界》という主題については、さまざまな学問領域をまたいでさらに対話していく必要がある。例えば仏教論理学(因明学)というものがありますが、五~六世紀頃にインドのディグナーガ(陳那)が語っている推論の方法を、現代の仏教学者は帰納法と呼んでいますが、僕が見るに明らかにアブダクションであり、記号過程なんですよ。その辺はもっとこちらからも対話に参加していく必要があるし、すでにそういう計画もあります。
複数の二項対立的問題をまたぐように解決する
加藤:清水先生が論じているトライコトミーや、奥野先生が『今日のアニミズム』に限らずこれまでのご自身の著書なども通じて論じてきたコーンの汎記号論的な世界を含めて、結局のところ、アニミズムというものが最終的にビジョンとして提示するのは、すべての二元性が対称的なところで超克されているというようなビジョンだと思います。
結局、アニミズムということをなぜ、今、言わなければいけないのかというと、自己と他者、男と女、生者と死者、動物と人間、意識と無意識といったようなさまざまな二項対立が、近代社会の中で非対称的に膠着してしまっているからだと言えるでしょう。普通に生活することの正体の分からない息苦しさや虚しさ、あるいは環境破壊なども、より大きな近代システムの限界が来ている。そのシステムの破綻が起きていることの根源には、結局、非対称で膠着した二元性というもののくびきがあるということだと思うのです。
これをどのように解体するのかというのは、思想的にはポスト構造主義以降の思想がずっと考えてきたことでしょう。あるいは、現代思想に限らず、そうした膠着状態から生まれてくる精神疾患をいかに癒すのかという問題や、男女間の非対称性を是正しようというフェミニズムの問題、最近は「利他」という問題も非常にフィーチャーされていると思いますが、そうした社会学的な問題意識というものも、近代特有の暴力性や非対称的で膠着した人間性をいかに解体して、対称性を回復していくかということを基本的には目指しているのだと思うのです。
そういう意味で言うと、アニミズムという考え方はそのすべてにわたってこれが対称性の原理だというふうに提示できる公式なのではないかとも思います。個別に諸問題を議論していても、結局は新しい二項対立を生んでいくことになるでしょう。二項対立を解消しよう、暴力性を解体しようという形で議論が始まっていたはずなのに、結果的には二項対立の暴力性を新しく再生産していく構図になっていく。
清水:暴力性の再生産とその反復というのは、「異」なるものを指向しつつも、同じ生成の循環の中でぐるぐる回っているだけだからですよ。
加藤:そうですね。例えば、本書の奥野先生と清水先生の対話の中では、アニマル・ライツの問題に少し触れていますね。動物の権利を認めましょうというときに、アニマル・ライツの議論はアニミズムという対称性の議論が解決されていない状態で始まってしまうため、どうしても新しい二項対立を生んでしまう。どこまで動物の権利を認めるのか、瑣末な議論に流されていってしまう。
それはフェミニズムの問題においても同様です。さまざまなタイプのフェミニズムが今日、展開されていますが、それぞれにアクチュアルな意味では有効性がありますし、政治的な意味では有効性がある議論もありますが、それがより原理的に非対称な二項対立を完全に対称性へと回復するということが考えられていない。そのため、どうしても新しい二項対立を生んでしまい、議論が錯綜していってしまう。しかし、本書『今日のアニミズム』で行われている議論というのは、アニミズムから対称性の原理を取り出していくことにとって、最終的に解決するという方向性を示唆するところがあるのではないかと読めるのではないでしょうか。
清水:トライコトミーというのは、言ってみればトランプのジョーカーみたいなものです。媒介としてさまざまなものに変わりうるものだと思います。
ある領域に問題を限定して、二項対立を第三レンマ的な二重性の論理によって解決しようとすると、結果として対立する二項の位置を逆転させるということだけに関心が絞られてしまって、そこでの闘争が激化してしまう。アニマル・ライツにしても、ジェンダー論にしても、二項対立を一種類の二項対立だけで、ワンオペで扱っているのが根本的に良くないと思いますね。その領域以外が視野に入らなくなると、そこで二者間の関係を対称的にしようとしても上手くいかない。それはある種のフェティッシュなんですね……。例えば等価交換が対称的な交換関係として理念化されるとして、一般的等価物としての貨幣というものが生まれると、貨幣経済という領域に関心が集約される。――それでWin-Winな関係が増大していくのかというと、むしろそれ以前よりも無残に格差が拡がってしまうというように、大概逆の結果がもたらされてしまう。垂直な上下関係のある一種類の二項対立を、ただひっくり返すという、単純なことだけが考えられている。垂直な上下関係にある二項対立、その逆転、さらにその反復……これだけです。そして「一/多」の問題が大概事後的に悪さをしてくるんですね。
実のところ、トライコトミーの中でも「内/外」、「一/多」については本質的で外せないのですが、三つ目の二項対立については社会的な水準のものを色々代入可能なのではないかと僕は思っているんです。複数の二項対立のコードをまたいで、それらを取り替えることで、二項対立の緊張を緩和するヒントが、トライコトミーにはあるのではないか。そういう、トリックスター的なロジック――ミシェル・セールならヘルメス的と呼ぶでしょうが――それがトライコトミーであり、またそもそもアニミズムの知でもあったと思うんです。
ようするに僕はフラットで、したたかに民衆的で、寓話的でもある知というものを取り戻したいんです。先ほど奥野さんが言及されたことで面白いと思ったのは、アニミズムが実は仏教なんだということです。日本の歴史を考えてみると、この国の成り立ち自体がそもそも仏教が入ってきて、宗教をめぐるロジックが抽象化されたことによって、一度、全体が結びついたというところがあったのだろうと思うんです。おそらく日本各地でシャーマニズムであったり、祖霊の祭祀と信仰が混じったようなものであったり、さまざまな形態があったろうと思いますが、別々な場所で独特に発展したそれらを統合しようと思ったら、一度、仏教という形で抽象化し、アニミズムという基本構造にもどってそれらが習合していくことが必要だった。その意味でも、日本に伝来した当初から、仏教はばらばらな領域をまたぐ、非常に強固でかつ柔軟な文化的なきずなだったんだと思います。
アニミズム的世界と「参与」ということ
奥野:おそらく清水さんが述べられたアニミズムとは仏教であることの意義が、冒頭で加藤さんからなされた問いかけの二点目である救済のテーマに繋がってくるのではないかと思います。
たしかに、清水さんが、メディウムを含んでいろんなものに変わりうるトライコトミーに踏み込んで、アニミズムをロジカルに追及されているのに対し、私は初めから、加藤さんがおっしゃっている「世界の救済」に向かっていたのかもしれません。というのは、既に述べたように、人間主義に潜むヒューマンとノンヒューマンの非対称性に目を向けているからです。本来的には、その二者が繋がっていたということであり、その繋がりを取り戻すことが世界を救済することになるのではないだろうかという見通しを示しているわけです。加えて、仏教に拠りながら、自己を退かせていって、アニミズムを他力論的な地平で説いている点で、「自己の救済」を語っていることになるのだと思います。
もう一点、加藤さんから提起いただいたアニマル・ライツやフェニミズムなどの現代的な課題が陥ってしまう二項対立について、述べてみたいと思います。その問題に関して、一つの取っかかりにしたいと思うのが、デザインという問題系です。最近、研究会で上平崇仁さんの『コ・デザイン』(NTT出版)という本を読んだのですが、非常に面白かったです。
同書によれば、これまでデザインというと、大量生産・大量消費の時代においては工業意匠だったり広告ポスターだったりを指していたわけですが、21世紀の今日においては、制度や行政、介護、医療、スポーツ、ありとあらゆる分野がデザインする領域になってきている。それとともに、デザインはデザイナーだけに任せるものではなくなってきている。タイトルにある「コ・デザイン」、つまりいっしょにデザインする時代に入ったというわけです。
その出発点は、1970年代の北欧だったそうです。スカンジナビア半島で、オートメーション化を目指す経営者とそれに不満を持ち、権利や働きがいを求めた労働者の間で労働争議があった。労働争議というのはまさに二項対立ですね。経営者と労働者が闘争するわけです。しかしなかなか解決を見ないわけで、それをどのように問題解決していったかというと、パーティシパトリーデザインつまり参加型デザインが導入される糸口をデザイナーたちが用意した。働きがいがありかつ生産性を上げるために、デザイナーが現場に介入した。そのことを経営者と労働者の双方が合意したらしい。経営者と労働者の争議にはもちろん政治性が絡みますが、パーティシパトリーデザインを導入するためにもまた政治性が必要だったのでしょうが、とにかくいっしょにやっていく方向で社会をデザインしていくことに決めたらしいのです。
二項対立で主張を競い合うのではなく、社会をデザインしていく際にいっしょに協力してやっていくほうが効率的だし、生産的・建設的だという風に考え方を変えたわけですね。不毛な二項対立や二元論をどのように乗り越えるのかという点は今に至るまでとても大きな問題なのですが、そういったパーティシパトリーデザインを「人類学の存在論的転回」の方向に拡張した「存在論的デザイン」では、人間を超えて、人間以外の存在や世界といっしょにデザインしていくことが視野に入っています。世界をデザインすると、世界からデザインし返されるというわけです。それは、往っていつの間にか還ってくるという、メビウスの帯的なアニミズムへの参入のようなものです。
デザインは現在の時点にとどまっているものではなく、未来に向けてのデザインを含んでいます。2030年〜2050年といった近未来に向けてどのように社会をデザインしていくのかということに関心を持つ若い世代の人たちが今、デザインを盛んに勉強しているようです。人新世の議論で、人間が地球をボロボロにしてもう長いことは持たないかもしれないという流れに対して、若者らが、いやそう言い切ってもらっては困る、なんとかできる道が残っているはずだと考えているんじゃないかと、私自身は思っていますが。
そうした近未来に向けてのデザインを考えている若い世代と比べて、アニミズムというとき、それは近未来に向けてというよりも、私たちが潜在的に持っている思想としてのアニミズム、私たちの心の奥底に眠っているものを取り出していく作業であり、それが『今日のアニミズム』の底の部分にあったのだとも思っています。
清水:やはり重要なのは、パーティシペーションparticipationなんですよね。それは人類学において言われてきた参与観察ということとも関わってくるだろうと思います。参与観察を通じて、世界そのものをデザイン的に可視化し、創造する。西田幾多郎的に言えば、「作られるものから作るものへ」ですね。しかし、デザイン的に可視化された社会というのも限定状況ですから、それよりさらに大きい構造をいかに考えるかというのも大事であって、どうやってさまざまな文化的コードに接続してあらたな局面を次々開いてみせるかということですよね。それがパーティシペーションそのものの問題であると。
例えば、プラトンが言うメテクシスμέθεξις、分有というものがあります。これはラテン語で言えばパルティシパティオparticipatioですね。これらの言葉にはいずれも参与するという意味もあって、そもそも両義的だからこそ『パルメニデス』で若いソクラテスが使ったことになっていたというわけです。
加藤:より実践的なレベルで言うと、パルメニデス的に抽象化されているわけではなく、例えば、折口信夫が「マナ」などの概念を使って、いわば魂が分有されていくようなことを言っていますね。つまり民俗学の現象とセットで論じられていく。それはパフォーマティブに論じられていくということでもあります。折口信夫の本を読んでいく限りでは、アニミズムとはこういうものかと何となく体感的に分かってくるところがある。それは『今日のアニミズム』で集中的に検討されている岩田慶治についてもそうです。しかし、それらを読むだけではロジックとして詰められていない、説明されていないところがあって、分かる人には分かるけれども、分からない人には本当に分からない状況を招いていたとも言えます。それが体感として分からないという人に対していかにロジックによって導いていくのかという点で、『今日のアニミズム』におけるトライコトミーという概念は非常に有効なのではないかとも思うのです。
逆に言えば、一度、分かってしまえば、救われてしまうところがある。その「救われてしまう」というところにいかに持っていくかということだと。清水先生の論考でいうと、「第五章 アニミズム原論」で展開された、俗諦から空によって真諦に行くという話があります。それが救いの構造であるということですね。俗諦から真諦へというのは、二項対立的世界からアニミズムの世界へ移行すると読み替えてもいいわけですよね。
清水:それこそ花が散るとか月が陰るとか、日本人が持っている無常感すら仏教が育んだ美意識なわけですよね。それらがただ習合したというだけではなく、ちゃんとロジックなんだということを明らかにしたかった。ただ、こういうことをキリスト教に近い人たちと議論すると、頭で分かっただけの人間が救われるなら宗教はいらないだろうという話になってしまうのですが、しかし、きちんと一番シンプルな形で論理構造を作っておき、ナーガールジュナよりも後世に登場してきた人たちの見解や議論をも折り込んで、そのうえで思うぞんぶん審美的な世界に浸り、納得したいというのが僕の立場なんです(笑)。
ところで奥野さん、ここにきてパーティシペーションparticipationという言葉が前景化してきましたが、これは人類学的にはそのまま「融即」という訳語でも知られた重要な概念ですよね。この訳語は仏教語からきているわけですか?
奥野:ええ。その融即という言葉自体は、華厳から来ているようですね。人類学では、フランスの哲学者ルシアン・レヴィ=ブリュルが、『未開の思惟』(岩波書店)の中で、パルティシパティオンを取り上げていますね。彼の定義で言えば、「一と多、同と異は、その一方を肯定する場合、他を否定する必然を含まない」ということです。レヴィ=ブリュルは、それを最初未開の「前論理」だと捉えたわけです。
日本ではパルティシパティオンに、華厳教学から「融即」という言葉を訳語として当てた。たしか訳者は、マルセル・モースに学んだ山田吉彦さんでしたか。きだみのるですね。ですから参加する、参与するというのはまさに融即してしまうということなんです。
清水:デザインの人類学が、「融即」というレヴィ=ブリュル以来の蒼古たる人類学のテーマと結びついてくるのは面白いですね。「融即」とはデザインの人類学における可視化なのかもしれない。仏教語にしろヨーロッパ言語にしろ漢語にするというのは色々解釈の幅も拡がってしまって、ぴったりはまるとすごく効果的なんですが、解釈の歴史的な積み重ねがあったり、それがまた案外まとはずれであったりして、難しいところもありますよね。
加藤:私も仏教の本というのは例えば、『中論』とかも一時期は読んでいたのですが、文献学的なところを通らないとなかなか読み通すことができない。ですから、一般の人にとってそれを読みこなすのは余程の忍耐が必要になる。ですから逆に『今日のアニミズム』のような形で、「内/外」「主体/客体」「一/多」というトライコトミーのような抽象度を持った形で論じてもらったり、アイヌのクマ送りなどのような具体的な事例で説明したりというのは、議論を掴みやすいのだろうと思います。基本的には二項対立の膠着をどのようにアプローチして対称性というものを回復することができるかということなわけですね。
仏教も基本的には宗教ですし、アニミズムもそうなわけですから、最終的には救いの論理へとなっていく。先ほども述べたように、それは今日的な諸問題に対して、いかに救いの論理というものを作動させ得るのかという議論にも繋がっていくのだろうと思います。
清水:繰り返しになりますが、二項対立を調停するときに、二ではなく一であるという形で解くというのは「一/多」という宿題がどうしても残ってしまうのであまり良くないわけです。「一/多」の問題も解きつつ、二項対立というものも解かねばならない。鈴木大拙や井筒俊彦も素晴らしい議論をしているわけですが、どうしても一のほうへと寄せて、論理ではないんだというところに落着させるきらいがあるのはちょっと残念なところです。
加藤:そうですね。だから、鈴木大拙も井筒俊彦も、そこで議論が進まなくなって、分かる人には分かるというような世界になってしまう。井筒俊彦の本を読んでいると、重要なところで「縹渺」などレトリカルな表現が出てきてはぐらかされてしまう。ある種、文学的なところで解消されてしまうところがある。
ですから、本書のように清水先生のトライコトミーの議論によってロジックで原理づけていくことで、奥野先生が書かれている章は応用編としても見ることができる。そのように読むことができるなとも思います。
清水:デザインの話が出ましたが、奥野さんはアート表現のあり方そのものについても考えておられるわけですよね。
加藤:以前、参与観察の最終的なアウトプットが民族誌だけというわけではないというような話をされていましたね。
奥野:参与観察の最終的なアウトプットは民族誌だけではないというのは、インゴルドを引いてどこかで書いたものだろうと思います。アート表現かどうか分かりませんが、私にはマンガは描けないので、マンガの原作を書いてみたいと思っています(笑)。
参与観察と民族誌に戻すと、フィールドワークに行くのは、データを集めて持ち帰ってくるためではないとインゴルドは言います。それだと、人類学という学問の制度や体系に従属しながら仕事をしているだけだと。人類学とはそういった民族誌ではなくて、民族誌に思弁と実験を加えたものなのだと言うのです。思弁とか実験からできているのがアートですから、人類学は今後アートに近づいていくだろうともインゴルドは述べています。
民族誌を書いてそれでおしまいというのではなくて、フィールドで見聞きしながら人間の生について学ぶ中で、スペキュレートしていくことが大事だということです。実は、インゴルドだけでなく、人類学者は誰しもそのようにやってきたはずです。フィールドでさまざまなデータを集めて、それをライトアップして、純度を高めて、民族誌ハイでき上がり、これでどうですか?ってのではない。
ある日本の人類学の大御所の方が言ってましたけど、国際狩猟採集社会会議で出会ったインゴルドは、「天才ぼくちゃん」的で嫌な奴だったけど(笑)、彼の人類学観は、人類学者にとってはすごくすっきり来るし、素晴らしいと。つまり本来、人類学者はフィールドで参与観察することによって、思弁的にかつ実験的にやってきたはずであり、インゴルドが、そのことを明確に言葉の形で定式化したのです。
加藤:参与観察する主体がスタティックなものであれば、当然ながら、そこでまた二項対立が生まれてくるということがあるわけですが、参与観察というのは観察に重点が置かれるのではなく、参与に重点が置かれるというように考えると、主体自体が制作的な主体でないと人類学としては整合性が取れないという話になってきますね。
奥野:そういうことですね。自己がフィールドの現実に参与し、自己変容していくプロセスのなかでどんどんと作品を創造して、制作していくのが人類学だということなのです。完了形の民族誌が人類学ではない。
加藤:岩田慶治が、それこそ参与観察とは何かというとその共同体に生まれ、生き、死ぬことだというような言い方をしている部分がありますが、言ってみれば、人生をそこで送る、人生っていう作品をそこで作るところが参与観察の本体ということですね。
奥野:かなりラディカルですよね。参与観察というのを、人類学のフィールドワークの次元を超えて捉えているという意味で。岩田の時代でそこまで言っていることを考えると、もうすでにインゴルドを超えていたのではないかという気がします。
加藤:アートの場合は、いわゆる作品としてオブジェクトが何かしら結実していくわけですが、岩田慶治は、伝承社会の人は全員悟りを開いているということも言っている。伝承社会の人々のアニミスティックな感性を持った人生や人生観というものは、一つの作品なんだというような考え方がそこにはあるのかなと思うのですが。
清水:参与とは実験であり思弁であり、それらのメッシュワークだということですね……。ところで、仏教でもとりわけ禅における中国の人のロジックの場合は逆説が多くなりますよね。まったく正反対な逆説を平気で並べていくんだけれど、それは逆説という形で、二種類の二項対立を交叉配置したような印象をも与えるんです。しかし三種類目がどうもうまく出ていないような印象があった。――ところが禅の要諦を偈によって表現したものの中に、「参同契」というものがあるんですが、大拙がこれをこんな風に解説しているのを先日見て、ううむと唸ったんです。「参とはまじわるで、諸法(あらゆる事物)が万別千差して、しかもその位を守って相犯さない様相である」「同は万別千差の世界をそのままにして、そこに一物があることである」そして「参にして同、同にして参という義」が、偈の中ではそれらがたがいに「回互(えご)する」という風に表現されている、というんですね。「参」の字にはもともと「まじわる」の意味も、「参照して引いてくる」の意味も、「三」という意味もある。これはまさに先ほど述べたパルティシパティオparticipatioだなと思いました。さらには「融即」でもありますね。二元論をひっくり返すということばかりやっている中で、文字通りの「参」が突如として出てきたという感じです。(笑)
奥野:なるほど。道元も「参学」という言葉をよく使っていますね。「つひに太白峯の浄禅師に参じて、一生参学の大事ここにをはりぬ」(弁道話)とか、「審細に参学すべきなり」(道得)など。
清水:学に参ずる、ですよね。参禅するということもそもそもメッシュワークなんでしょう。――パルティシパティオparticipatioは「含む(外)/含まれる(内)」ということだから、ここでは「内/外」が姿を現わしている。この「参」はまさに三分法、つまりトライコトミーとも重なってきます。
加藤:参与するということは単純に言ってしまえば、主体として対象を観るということではなく、そこに入っていくことですから、入っていってしまえば、それこそ、ハーマンの議論ではないのですが、あらゆるオブジェクト、人、動物、モノというのと対称的な関わりを持たざるを得ない。対称的な関わりを持つということはつまり、観察する視点というスタティックな視点を自分が持っていてはできないということですよね。
清水:役割を入れ替えて、二項対立の両極を兼ね備えるということですね。このことは、別の二項対立と交叉配置的に結びつくことによって、はっきりと明らかになってきます。ある二項対立Aと非Aは、それぞれ別の二項対立のBでもあり、非Bでもあるという第三レンマの状態にあります。こうした交叉配置的な変換については、レヴィ=ストロースも『神話論理』ですでに分析していますね。このような循環的な関係は、生成的なものでも、また滅びゆくものでもあるのですが、原因としてどこかの項に帰されるのかと言ったら、それはどちらでもないということになる。――どこから眺めても、原因が一方的にどこにおいてあるわけでもない、という第四レンマが、だから最後の答えとなってくる。
加藤:そうですね。テトラレンマの場所というのは、日常的なオブジェクトとそのまま繋がっていくということですね。
著者紹介
加藤学
経営コンサルタント会社経営。その傍ら趣味の文化活動の一環としてステム・メタフィジック研究会に参加。興味のおもむくままに、人文研究者へのインタビュー、映画プロデュース等するディレッタント。
奥野克巳
文化人類学。立教大学異文化コミュニケーション学部教授。以文社より共著、共編著者として『今日のアニミズム』(2021年)、『マンガ版マルチスピーシーズ人類学』(2021年)、 『モア・ザン・ヒューマン』(2021年)、 『Lexicon 現代人類学』(2018年)を刊行している。
清水高志
東洋大学教授。井上円了哲学センター理事。専門は哲学、情報創造論。主な著書に『実在への殺到』(水声社 2017年)、『ミシェル・セール 普遍学からアクター・ネットワークまで』(白水社 2013年)、『セール、創造のモナド ライプニッツから西田まで』(冬弓舎 2004年)などがある。主な訳書にミシェル・セール『作家、学者、哲学者は世界を旅する』(水声社 2016年)、G.W.ライプニッツ『ライプニッツ著作集第Ⅱ期 哲学書簡 知の綺羅星たちとの交歓』(共訳:工作舎 2015年)などがある。
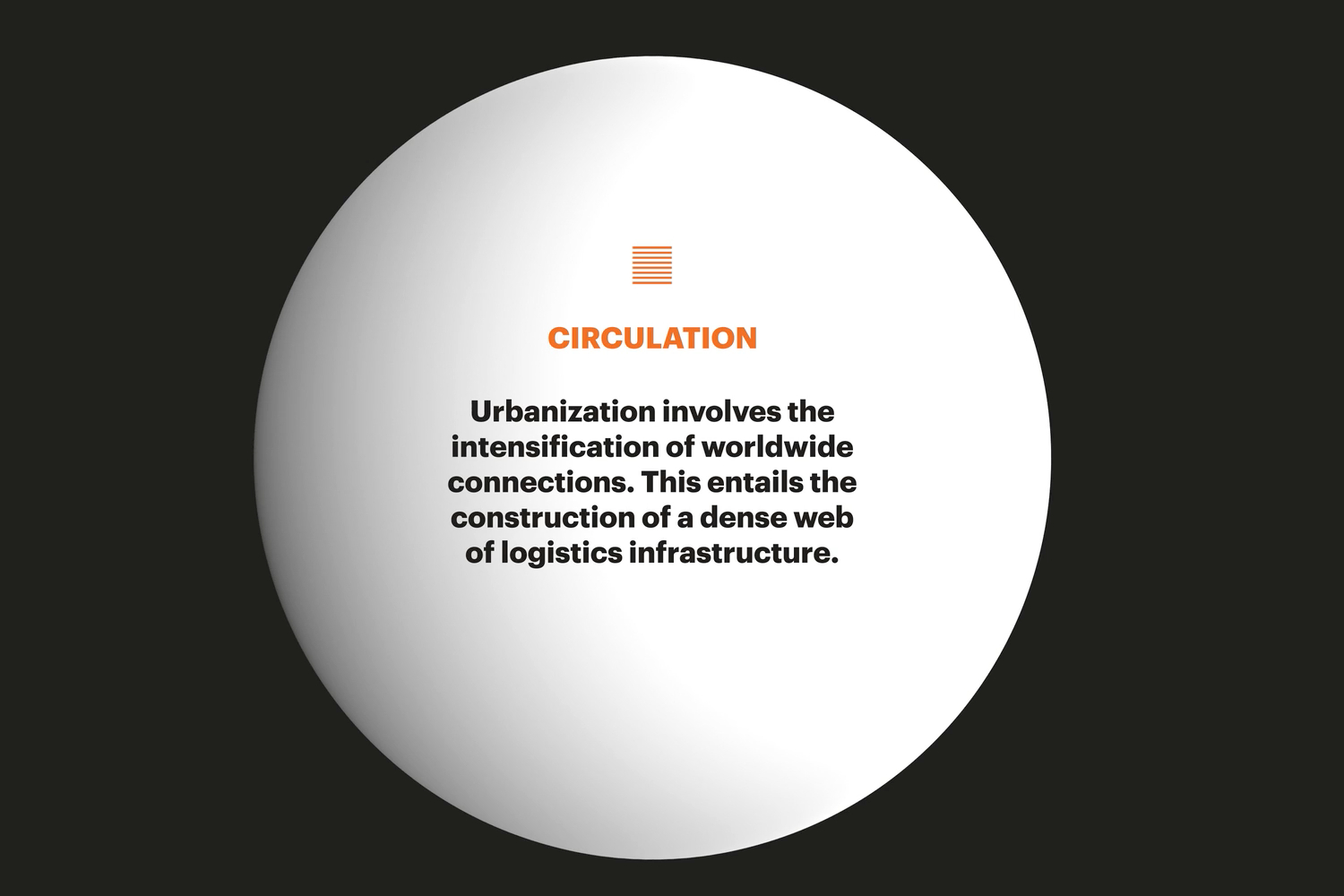
![Read more about the article 誰がパリ五輪に抵抗しているのか?[第1回]前編/佐々木夏子](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2021/12/PXL_20210530_093805138.jpg)

![Read more about the article 【連載】誰がパリ五輪に抵抗しているのか?[最終回]/佐々木夏子](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2023/07/佐々木_cartedesouvrages_画像.jpg)

