フェミニズム美術史への挑戦
━━カルラ・ロンツィの軌跡
ジョヴァンナ・ザッペリ
(松井裕美訳)
訳者解題
本論考は、Giovanna Zapperi, “Challenging Feminist Art History: Carla Lonzi’s Divergent Paths”, in Victoria Horne and Lara Perry (eds.), Feminism and Art History Now. Radical Critiques of Theory and Practice (London and New York, I.B. Tauris, 2017, p. 104-123) の日本語訳である。
論考の著者であり、現在トゥール大学美術史学教授であるジョヴァンナ・ザッペリは、現代アートの専門家である。マルセル・デュシャンが「ローズ・セラヴィ」(Rrose Sélavy)として繰り広げた活動におけるジェンダーの問題を取り上げた博士論文(パリ市ジェンダー研究賞受賞)を2005年に社会科学高等研究院に提出した後、L’artiste est une femme. La modernité de Marcel Duchamp (Paris, Presses Universitaires de France, 2012)として出版している。
また2005年から2009年にかけて、アントニオ・ネグリとマイケル・ハートの思想的系譜に連なる雑誌Multitudes(2000年創刊)の編集者としても活動した。アカデミックな美術史研究から逸脱する手法、とりわけフェミニズムやクイア、ポストコロニアルといった観点から現代アートに切り込む彼女の研究は、こうしたキャリアとも結びついていると言えるだろう。
近年ではマドリードのソフィア王妃芸術センターにおいて、展覧会Defiant Muses: Delphine Seyrig and feminist video collectives in France in the 1970s and 1980s(2019年9月24日〜2020年3月23日)のチーフ・キュレーターを務めている。
本稿は、美術史の教育を受けつつも、美術批評家の道を放棄してフェミニズム運動に取り組むようになったカルラ・ロンツィ(Carla Lonzi, 1931〜1982年)についての論考である。
本稿が描き出すのは、一人の美術批評家がフェミニズム運動家に転身する際の葛藤に満ちたプロセスであるのだが、ザッペリの叙述を支えているのは、過去の英雄的な人物の称賛でも、また過去を回顧するノスタルジックな眼差しでもない。
それは、リンダ・ノックリンやグリゼルダ・ポロック、そしてロジカ・パーカーらが先駆的に提起してから繰り返し主張されてきた次のような事実、すなわち芸術家、美術史家や美術批評家、学芸員の活動の基盤となっている諸制度が、家父長制的な背景のもと成立し、構造化されてきたという事実なのであり、ザッペリの叙述はあらためてそのことを私たちに突きつけているのだ。
またここで重要になるのは、美術史的な語りを放棄するというロンツィのとった選択が正しいのかそうでないのかということでもない。むしろ本稿で描き出された一人の女性の葛藤のプロセスそのものが重要なのである。彼女は美術史や美術批評の世界の根底にあった家父長制的な構造を解体するために、歴史的な叙述を放棄し、録音した声をモンタージュすることで、著書『自画像』を構成し出版した。だがそれは、美術史家としてのアイデンティティを放棄すること、つまり芸術を語る主体としての彼女自身の「声」を犠牲にするものでもあった。彼女にとって、そうでもしなければ、フェミニズム活動に参与するための新たな主体性を真に獲得することができなかったのである。
ザッペリは本稿において、ロンツィのラディカルな選択に至るまでのプロセスを私たちに紹介しながらも、そこから現在の美術史や美術批評の批判を展開するような記述を直接は行っていない。ロンツィの姿勢を現在の私たちがどのように捉えるのかは、完全に読者に委ねられている。
個人的な体験を述べさせていただくならば、美術史に直接関わる私個人としては、二つの主体のあり方のあいだで葛藤したロンツィの思考のプロセスに思いをめぐらせることによって、みずからの政治的な主体性というものについてあらためて考えざるを得なかった。それは意識した選択の結果ではなくても、あらゆる行動や発言におのずと現れているはずであり、またそこから立ち上がってくるものであるはずだ。
本稿はむろん、ロンツィが葛藤した二つの主体のオルタナティヴのうちのどちらか一方を選択するよう読者に迫っているわけではない。むしろそのあいだを行き来しながら家父長制から解放された美術批評ないしは美術史の言説の可能性について考えてみるよう、私たちを誘っているのである。
だからこそ美術史からロンツィが離別したことを語るザッペリ自身は、アーカイヴを開拓し歴史を紡ぎ出すという美術史的なメチエを放棄しはしない。ザッペリや、この論考が掲載された著書の著者たちが過去を振り返るのは、まさにそうした現在における主体性の問い直しと過去の出来事とをあらためて接続させるためにほかならないのである。
訳者はこの論考が出版される直前に、ザッペリを日本に招聘する機会に恵まれた。その際、早稲田大学総合人文科学研究センター研究部門「イメージ文化史」主催で、ザッペリの講演会「フェミニズムの時代:カルラ・ロンツィを読む」(2017年9月27日)を企画した。司会をお引き受けくださり、講演会の実現にご協力くださった橋本一径先生、コメンテーターとしてご参加くださり、議論を掘り下げてくださった西谷修先生に、あらためて心より御礼を申し上げたい。
ザッペリを最初にご紹介くださり、こうして彼女との知的な会話と友情とを育むきっかけを与えてくださったのも、実のところ西谷修先生であった。また、ここで翻訳した論考は、この講演会でご発表いただいた内容であり、以文社の前瀬宗祐さんにも、このようなかたちでふたたびザッペリの講演内容を紹介する機会をいただけたことに深く感謝を申し上げる。さらに翻訳にあたり、一部のイタリア語表現の邦訳を、池野絢子氏にご教示いただいた。記して深謝申し上げる。また原文におけるやや不明瞭な点については、著者に問い合わせた上で言葉を補った。
2020年11月20日 松井裕美
※ 凡例
本文の引用における作者の補足は[ ]で、本文中における訳者の補足は〔 〕で示した。
20年前、
私は大学の学生だった
15年前、
私は文学士〔日本の学士号にあたる〕だった
10年前、
私はアート・ライターで芸術家たちの友人だった
2年前、
私はフェミニストだった…
そして今
私はなんでもない、まったく、何者でもない
――カルラ・ロンツィ、1978年
美術批評からフェミニズムへ

本稿著者による著書『カルラ・ロンツィ』(2017年)書影より
カルラ・ロンツィ(1931〜82年)はイタリア人美術批評家であり、フェミニストであり、ライターであり、そして詩人であった。だが彼女は、なんらかの役割やアイデンティティを寄せ集めて人生を要約する力を持つこうしたカテゴリーから、逃れようとあらがうような人だ。だからどんなに彼女を定義しようとしても、どうしても条件つきで不完全なものになってしまう。
ロンツィは1960年代から70年代のイタリア文化を背景としながら、さまざまな実験的方法で執筆した。当時イタリアでは、国内の社会構造に対する抗議の声が高まり、巨大なフェミニズム運動が生まれつつあった。ロンツィは創造的な執筆プロセスを通して、自身の抑圧に結びつくような役割を拭い去ろうと奮闘する一方で、集団的試みのなかで得られる主体としての経験を表明しようとしていた。
「政治的な主体としての私の自意識は、グループから生まれたもの、非イデオロギー的な集団の経験としてかたちづくられていた実現〔イタリア語で現実を意味するrealitàが、ここでは「実現」という意味で用いられている〕から生まれたものである」と、彼女は1978年に書いている(1) 。ここで女性たちは、集うことによって、集団の中で主体を成り立たせているのだ。そしてこの場そのものもまた、集団によりつくられていく。
私が強調したいのは、主体になるという創造的なプロセスと、共有された解放の経験との絡み合いこそが、まさに、ロンツィのフェミニズムと彼女のアート・ライティングとを結びつける接点になるということである。
1969年、カルラ・ロンツィは『自画像』(Autoritratto)を出版した(2)。テープ・レコードに記録した14人の芸術家たち――カルラ・アッカルディをのぞけばすべて男性芸術家――との一連の会話を、モンタージュで構成した著書である。この著書はまた、彼女が10年にわたり従事した活動であるアートワールドと美術批評に、別れを告げるものでもあった。
1970年、ロンツィはアッカルディとともに、イタリアで最初のフェミニズム団体であるリヴォルタ・フェッミニッレを設立した。この団体の活動は、女性の集い〔ここで著者が用いるseparatismは、差異派フェミニズムというよりもよりニュートラルなものを示し、女性のみで結束することを示す〕と自己意識(Autocoscienza、イタリア語で意識高揚[コンシャスネス・レイジング]を意味する)に根差したものであった(3)。ロンツィにとって、かつて自身が従事していた美術批評とフェミニズムへの参与とのあいだには、どんな一致もあり得なかった。このため彼女の人生とキャリアは劇的に二分されたものとして示されてきた。
1982年に51歳で亡くなったロンツィは、イタリアにおけるフェミニズム第二波を創始した人物の一人であり、『ヘーゲルに唾を吐こう』(Sputiamo su Hegel)(1970年)や、『陰核女と膣女』(La donna clitoridea e la donna vaginale)と『女性の性と中絶』(Sessualità femminile e aborto)(どちらも1971年)など、多くの挑発的な文章やマニフェストを執筆した。
1978年には、『黙れ、いやむしろ語れ――あるフェミニストの日記』(Taci, anzi parla. Diario di una femminista)というタイトルで自身の日記を出版した。また1980年には『もう行っていいよ――ピエトロ・コンサグラとの対話』(Vai pure. Dialogo con Pietro Consagra)を上梓した。この著書は彼女の長年のパートナーだった芸術家ピエトロ・コンサグラとの4日間にわたる対話を収めたものであり、二人の関係の終焉を記録したものである。
これらの著述は、イタリアのフェミニズムについてのもっとも重要な資料の一部であるというだけでなく、実験的な執筆や創作、知識生産のフェミニズム的な取り組みを代表するものでもある。これらの文章においてロンツィは、日記や会話、あるいはマニフェストといった、伝統的には「マイナー」な表現形式を新たに取り入れている。さらにロンツィによる文化解体〔deculturationの訳語。ここでは既存の文化や慣習的な知識習得のプロセスを解体することを意味する用語として用いられている〕へ向けた計画は、既存の歴史の一部たらんとするどんな包括的な野心にも異議を唱える女性の自律性の追求を、記録にとどめるものであった。
歴史の時間を反弁証法的に理解する彼女の思想において、歴史そのものは、構造的に女性を排除する男性的構築物として理解されている。『ヘーゲルに唾を吐こう』にも記されているように、フェミニズムはクロノロジカルな連続性と(家父長制的な)歴史のモノローグの双方を拒絶するものだ。彼女が歩んだ道そのものが、フェミニズムを非連続的なものとして理論化したロンツィの思想を反映しているのであり、彼女の知的遍歴を線的で均質な歴史の枠組みを用いて読むことは不可能なのである。むしろ彼女が既存の認識論的パラダイムとの関係を断ち切ったことは、これらの伝記的なパースペクティヴよりも広い観点から考えられるべきなのであり、議論の余地はあるが現在においても多くの考察を与えてくれる場として考察されるべきである。
ロンツィはその生涯において、決して公人になることはなかったし、70年代に抗議デモを行ったフェミニズム集団とは直接のつながりもなかったが、彼女の著述はのちにフェミニストの意識の芽生えと結びつけられるようになった。
ロンツィは一般に、イタリアのフェミニズムの「生みの母」として考えられており、また矛盾したことに、おそらくこのことが理由で、彼女の全著作は最近まで看過されてきた。
フェミニズムの歴史家たちが主張しているように、ロンツィはすぐに伝説の人物として偶像化され、著作を綿密に吟味すべきフェミニズム思想家の同胞としてよりもむしろ、神話的な創始者としての役割が与えられたのである(4)。結果として、イタリアのフェミニズム第二派の歴史において彼女が担った重要な役割は広く認められているにもかかわらず、それとは驚くほど対照的に、批評家や学者は彼女の著述に関心を向けてこなかった(5)。80年代以降、イタリアのフェミニズムにおいて彼女の著述はつねに参照されてきたのに、大部分が検討されないまま今日に至っている。解放論者やマルクス主義、精神分析学など、すでに確立されている批評の伝統(それらは70年代イタリアの対抗運動における言説を支配していた)とは対照的に、独自の言葉を作り出すロンツィの能力は、こうしたプロセスにおいてきわめて重要なものであった(6)。
彼女が書いたものは本質的に実験的で、その断片的な構造は、主体への生成が未完であり進行中であることを示している。加えて、ロンツィの作品は自律した表現形式を根気強く追求するものであり、そのことによって否応なしに、彼女が生み出したものを体系的に分類しようとするいかなる試みにも抵抗するものとなっていた。
カルラ・ロンツィの名前をイタリアのフェミニズムの歴史に結びつけることは、美術批評家としての彼女のかつての活動との関連性を曖昧にすることにもなった。とりわけ『自画像』は、60年代のイタリア美術を研究するにあたり素晴らしい材料になるのに、この著書が規範的な文章とみなされたことはこれまで一度もなかった。反対に同書は、公式の美術史の語りと相入れないものであるばかりか、70・80年代にイタリア美術を意図的に売り込んだ文化的な商品包装のたぐいであるように思われたに違いない。
アート・ライティングの伝統的形式を無効にするロンツィのラディカルな試みは、美術史の教科書ではほとんど言及されることがなく、顧みられないまま放っておかれるか、さもなければ単に、それに続く彼女のフェミニズムへの参与の、ある種の延長線上にあるものとして考えられた。現在はロンツィの著作にも新たに関心が向けられるようになっており、彼女のフェミニズム運動参与の「前」と「後」との違いについても、いくらかは再確認されるようになってきているが、美術史のパースペクティヴとの決裂がいかに重要なものであったのかについては、触れられないままである。
伝統的な観点から考えてみると、彼女の美術批評家としての活動は、今でも多くの場合には彼女のフェミニズムとは区別されるものとして考えられているし、美術史の学問的な枠組みの中で触れられるべきものであるか、あるいはせいぜいのところ、単にフェミニズム思想を予告するものとしてしか考慮されてこなかったのである。
本稿で私がロンツィの著述について考察するのは、彼女の美術批評との決裂をフェミニズムの美術批評と美術史の枠組みのなかで扱うことでこそ、見えてくるものがあると思うからである。フェミニズムはこの40年のあいだ美術史に介入してきたのであり、それを経た今、私たちは彼女の思想を、現在の私たちに影響し変化させるような一連のはたらきとして再考する必要がある。つまりフランチェスコ・ヴェントレッラが述べるように、「現在における芸術とフェミニズムとの出会いを求める行為として」(7)、彼女の思想についてあらためて考えてみる必要があるのだ。
実際、ロンツィがフェミニズムをとおして美術批評と決裂した道のりを検討することで、これまで主に――完全にとは言わないまでも――英語圏のコンテクストで繰り広げられてきたフェミニズム美術史の著作についての現在の議論のうちに、根本的に異なるパースペクティヴを導き入れることができるだろう(8)。ロンツィによる芸術についての著述は、彼女がフェミニズム思想を抱くようになった動機を分析する際にも分けて考えることはできない。それどころか彼女のフェミニズム的な文章は60年代に取り上げられた多くの問題と関連づけなから考察される必要がある。
したがって私は、ロンツィの妹マルタ――彼女自身リヴォルタ・フェッミニッレのメンバーだった――による次のような提案を広げて論じてみたいと思っている(9)。美術業界の見解では、ロンツィは美術批評に従事したことを私的な後悔すべき選択として拒否したということになっている。だがマルタ・ロンツィが指摘しているのは、分離した領野としてのフェミニズム概念を超えて、カルラが歩んだ様々な道を扱わなければならないということ、むしろ美術と文化に直接関係する問題としてそれを扱わなければならないということだ。
こうした洞察にしたがいつつ、ここでは、美術批評家らフェミニズムへの転換を、芸術と美術史についての国際的なフェミニズム論争のなかでかたちづくられてきた一連の問題との関わりから解釈されるべきものとして考えてみたい。そのためにここでは互いに関連する三つのトピックを概観したい。
まず1969年の著書『自画像』――彼女がフェミニズムに参与する数ヶ月前に出版された――について考察する。この著書は、ロンツィが美術史の知識生産への批判を実行に移す際の、変化のプロセスを示すものとして理解されるのである。美術史の知識生産への批判は、ロンツィにとって、文化を抑圧的な性質のものとして理解するうえで欠くことのできない役割を果たしていた。
次に、創造的プロセスにおける女性の役割の問題にロンツィがどのように取り組んでいたのかを検討する。とりわけカルラ・アッカルディとの友情(のちに決別する)と、フェミニズム内部における創造性の本質についての彼女の考えをとおして、このことを考察する。こうしたことは彼女の著述をとおして、とりわけピエトロ・コンサグラとの1980年の対話のうちに現れてくる。
そこで第三に注目するのは、そうした際にロンツィが試みた、芸術からの撤退と文化的な統合への抵抗が、どのような意味を持っていたのかという点である。
知識批判
ロンツィは60年代のあいだ、美術史家としての独自の実践を展開しようとしていた。その試みが頂点に達したのが『自画像』である。それは主体としての自己の位置づけと、批評活動を限定している社会および知の諸構造への鋭い批判に根差した、アート・ライティングにおける実験的試みだった。
この本は1965年から68年のあいだにロンツィが録音し、書き起こして集めた会話に基づいている(10)。それぞれの対話は断片化されていて、発話言語の口語調を残すよう編集されている。ロンツィは質問をやめたり芸術家の作品について語るのを中断したりすることがあるのだが、その部分を、あたかも途切れない対話であるかのように構成して、おのれのために、みずからの声で語る。
録音するということの何がこんなにも私自身を惹きつけるのだろう。私を魅了しているのは、次のようなとても基本的なことだ。音から句読法への、書体への移行が可能になること。まだ書かれていない頁を探すこと。ただこの頁とは、そう、まるで化学的なプロセスにおける凝縮のようなもので、音から記号を凝縮する。ガスが液体へと変化するときのように。なぜかはわからないけれど私はそれが大好きだ。あなたがいつも読んでいるものとは違うものを読んでいるのだと考えるのが好きだ。それは脳のはたらきによって生み出されるもので、そのことについて考えるだけでひどく疲れてしまう(11)。

ロンツィは美術批評という「オーセンティックではない専門職」から逃れ、彼女自身を変化させるような参加プロセスを探していた。この追求の中で対談は、それぞれの芸術家の作品とキャリアに非体系的なやり方で触れるようになるのだが、同時に彼らの生活や関係性、彼らがイタリアの美術制度に対して共有している不満、そして当時の政治情勢についての多くの考察にも触れることになる。こうした議論は、68年の抗議運動やアメリカの公民権運動、ベトナム戦争やフェミニストの意識の高まりといった幅広い問題に関わるものだった。とりわけ最後はカルラ・アッカルディとの対話でこうしたことが話された。
ロンツィはまた、芸術家たちに写真を提供するようあらかじめ依頼した。そのことで進行中の会話に多くの図版を挿し込み、美術史の著書の伝統となっているテキストとイメージから成る構成を想起させようとしたのだ。ただしこうしたイメージの大部分は私的なものか旅行中のスナップショットだった。この本のいたるところにそうした写真が挿入されていたために、文章を構成する会話のなかに伝記的な要素が入り込むことになった。
ロンツィは、アート・ライティングの支配的な諸形式が持つ実践も詩学も、文字通り無効にしているのである。創造のプロセスに参与するために解釈の権限を放棄しながら、彼女は芸術家の主体性と非歴史的なやりとりに焦点を当て、形式主義者の知の基盤の一つとなっていた芸術作品――とりわけ視覚的性質――の卓越性を骨抜きにしようとしているのである。
ロンツィは慣習的なアート・ライティングに不満を抱えており、早くも1963年にはそのことを示すような論文を発表している。それは「批評家の孤独」と題された、論争を巻き起こすような論文で、孤立や家父長制、権威に根差した美術批評の支配的形式として彼女が捉えていたものに対する反応として書かれたものだった(12)。彼女は60年代には、芸術作品よりもその作家たちに徐々に傾倒するようになり、それにつれて批評家としての自身の役割に疎外を感じるようになっていった。
彼女は1966年には、イタリアの雑誌『マルカトーレ』にテープレコーダーで記録した会話を出版し始め、それとともに、頁に掲載される文章から自分自身の記述を次第に消し去っていった。聞き取り、沈黙し、参与することが、批評家の解釈にとってかわり、そのことで彼女は観察者としての役割を超える手段を手に入れた。
ロンツィにとって、批評家の慣習的な立場とは、芸術家と批評家とのあいだの階級的な関係を表すもの、基本的に超然としていて、創造的プロセスとは無関係なものであった。『自画像』の序文で書いているように、カセットテープによる録音は彼女に、自身の活動を変える手段を与えたのである。
近年私は、ますます批評家の役割に戸惑うようになってきた。それが芸術的な行為とは無関係なものを文章にすることのように感じてしまうのだ。私はそれを、芸術家に対する差別の力の行使として理解するようになってきた。テープレコーダーを使うからといって自動的に批評が変わるわけではないが――批評家にとってしばしば、インタビューとは対話の形式をとった評価判断でしかない――、私が思うにこれらの会話から少なくとも一つの見解を引き出すことができる。すなわち、完璧で確かな批評の行為とは、芸術的な創作の一部を成しているものなのだ(13)。
生活の諸現実にみずからの活動を結びつけることに関心を抱いていたロンツィにとって、美術制度を考え直さなければならないという思いは、彼女自身の役割の再考察と密接に関連していた。同書の序文で書いているように、書物を組み立てていくこと[アッセンブリング]で彼女が意図していたのは、情報を集めるということではなく、むしろ「広く伝達可能で人間的に満足できるようなやり方で誰かと触れ合う」ことだったのであり、そのことによって「私が持っていなかったような、魅力的に感じた活動や人間性[……]」にみずから触れることであった(14)。
最終的に、この書物のアッサンブラージュ〔産業的素材や商業製品や自然物など、異質な素材を組み立てて制作する立体作品〕のような構成は、男性が支配する60年代のアートワールドにおいて、主体生成の複雑なプロセスを生み出すことになった。このプロセスの中では、男性中心的なアートワールドを支えていた役割とアイデンティティは、ともに瓦解する。あとに残るのは、私たちが芸術と呼ぶものを構成する諸々の神話からの解放を可能にする前提条件となるような、ある種の関係性の空間である。
「美術批評家としての役割を失った今、私には何が残されているだろう。ひょっとすると芸術家になったのだろうか。私の答えはこうだ。すなわち私はもう部外者ではないのだ(15)」。ロンツィのアッサンブラージュ本は、ある「はけ口」(sbocco)の追求を体現している。この「はけ口」とは、単線的でない、対話的で集団的な語りのうちで彼女自身の声を分散させることにより、批評家の一貫した統一的性格を拒むものである。同書はこうした点において、主体性や参与、自己表象の問題がきわめて重要であるような彼女のフェミニズム的著述に、共鳴しているのだ。

左:幼年時代のピーノ・パスカーリ/右:ベネズエラのパーティーに出席するヤニス&エフィ・クネリス夫妻(1958年)
『自画像』は、テキストに表れる批評家・芸術家のアイデンティティに結びついた諸慣習に異議を唱えることだけでなく、公式の美術史の語りもまた問いに付している。公式の美術史の語りの多くは、モノグラフ形式〔一人の芸術家のみを扱う形式〕であるか、あるいは(男性)芸術家たちや諸運動、カテゴリーのクロノロジックな系列を示す形式に根差したものだ。同書はまた、視覚的な分析を気まぐれな会話に置き換えることで、当時支配的だった美術史の形式主義モデルも問いに付している。
一世代前の傑出した美術史家であるロベルト・ロンギのもとで研鑽を積んだロンツィは、その教えを活かして彼女独自の形式主義を発展させていた。ロンギの方法は鑑定眼を基礎とするものであり、中立的で身体性を欠いた観察主体を前提とするものだった。そのことによって観察主体は観察対象と分離されたのである。ロンギにとって、直接観察するということは、議論が信頼できるものであることを保証するものだった。したがって注意深く見て証拠を得ることは、眼の特別な鍛錬と、イメージを文字によって言語化する能力とを基礎とするロンギの教えにおける、きわめて重要な要素であった。実際視覚と知識は、彼の語彙においてほとんど同義語であったのだが、ロンツィにとってはこの等式が徐々に問題含みのものとなっていった。
ロンツィは1970年の論文「美術批評とは権力である」の中で、支配と知識生産とのつながりについて明確に述べている。制度的な権力の一形態である美術批評は、このつながりを得ることができたと公言しているのだ、と(16)。
美術史の知の構造を解体しようとするロンツィの試みは、『自画像』全体で扱われた次のような諸問題、すなわち、作者という確立された概念に異議を唱えるような、分散していて不均一な集団的主体性、編集とモンタージュによって生まれた単線的でない時間性の導入、そして参与や対話、横のつながりに対し視覚を優位に置く形式主義の拒否から出てきたものだ。おそらくより驚くべきなのは、これらの対抗的な言説が、この本の実際の構造から生まれている点である。『自画像』の構造は、規範的な物語を脱構築し、そのことによって知識生産のオルタナティヴな諸形式を取り入れるようはたらきかけるのである。
『自画像』における知識批判と、その後ロンツィが展開した女性の自律についての思想とのあいだには、直接のつながりがある。彼女の見解によれば、解放のプロセスは、彼女が文化解体の実践と呼んだものからつくられる何もない空間の中で、そのほかの女たちと関係することにより始まる。女性のアイデンティティを成す役割と立場を解体しようとする彼女のフェミニズム的な野心は、批評家という役割のアイデンティティから脱しようとする先立つ彼女の試みに、呼応するものなのである。
ロンツィにとって、美術制度は彼女が「文化」と呼ぶものの一部を成していた。この言葉が示唆しているのは、彼女が家父長制を、教育も含む社会生活のすべての側面を内包する包括的なイデオロギーとして理解していたということである。ロンツィにとって、女性の自律性とその行為主体性は、抑圧的な力として考えられる社会的・文化的認識の諸構造につきしたがうことへの拒否から出発するような、終わりなきプロセスであった。ロンツィはすでに『自画像』において、彼女自身が受けた美術史家としてのトレーニングが「官僚主義的」で「抑圧的」な性質のものだったと記している(17)。また数ヶ月後に彼女は、高等教育が女性の抑圧に加担しているのだと示唆している。
カレッジと大学は、若い女性たちが文化をとおして解放される場などではなく、彼女たちの抑圧が完成される場なのである。この抑圧は家庭の中でかくも盛んに培われているのと同じものだ。一人の若い女性を教育するということは、彼女がもっとも潜在的に責任ある行為、彼女の自信を深めるような経験をしようとせんばかりの間際に、彼女を麻痺させる毒をゆっくりと注入することにある(18)。
ここでロンツィが、若い女性の動きを封じる毒について触れているのは、彼女が逃れようとしてきた制度的な知識生産の諸形態が、肉体に影響を与えることを示唆するためである。文化が持つ麻痺させるような効果は、女性の主体性を抑圧する役割とステレオタイプとに縛られて動くことができなくなった、化石化した主体のイメージに喩えられるものだ。
ここでロンツィがほのめかしているのは、肉体という強力な機械によって抑え込まれる客体[オブジェクト]としての女性という、伝統的な役割である。女性たちをおのれの身体とセクシュアリティから疎外するようなこれらのメカニズムは、自律性と自由への道を拓く予想もつかぬ振る舞いの追求の中では、解体される必要がある。したがって女性たちは、麻痺してしまうことを避けるために、彼女たちがとらわれていた繰り返しの環を打ち破らなければならない。この反復に含まれているのは、女性性を抑圧し定義するような役割やステレオタイプ、カテゴリー、身元証明といった前提である。この点では文化解体の試みは、自身について知っていると思っていたことをあえて放棄するような、女性たちの主体生成のプロセスと一致するものであった。
男性の創造性と女性の表現
ロンツィにとって、観察者の立場を放棄する必要性は、多くの点できわめて重要であった。彼女は一方では、権威を振りかざして観察者の立場にあるのだと断言することを拒み、他方では活発に芸術と関わった。たとえそれが芸術家になるということを意味していなくても、である。
『自画像』の序文で彼女が書いているように、部外者ではなくなることで、自己表現と自律性の可能性がひらけたのだ。ロンツィは、自身が美術批評を放棄したことについて説明しようとする際に、芸術家にとっての観客としての役割を演じることを拒み、そのことによって芸術家の眼差しの問題を導入することが必要であったのだと主張している。
当時の、(ほぼ)同時代の英語圏の人々が、客体としての女性を問題として理論的に取り上げていたとすれば、それとは反対にロンツィにとって問題であったのは、女性が客体というよりもむしろ芸術作品の観客であるということだった。女性を排除した男性の創造性を受け身のまま観察し、そのことによってそれを正当化しているのは、ほかならぬ女性である、というのである。
こうした考察から伺えるのは、美術批評家としてのみずからの仕事が、ジェンダーのヒエラルキーを壊すような批評用語の追求と矛盾するようになったことに、彼女がフラストレーションを抱えていたということだ。ロンツィは、美術批評の権威的な力を拒否した後でさえ自身が受け身の姿勢にとらわれてしまっていると感じており、『自画像』においても、また彼女の日記においても、そのことを深く悔いている。
参与型の批評形式を生み出そうとする試みの中で、ロンツィは、同輩の芸術家たちによって自分が受動的な聞き手の役割に押し戻されてしまうのをつねに感じていた。それはいつも彼女を落胆させる種となっていた。
ロンツィによれば、女性が不在であることによって、創造性が持つ家父長制的な性格が正当化されていたのだが、だからといってただちに女性芸術家たちを熱心に擁護することにつながったわけではない。リヴォルタ・フェッミニッレの誕生はむしろ、逆説的にもフェミニズムと芸術との分岐を告げるものであった。
1971年3月に書かれ、リヴォルタ・フェッミニッレが著名した文章『男の創造性の発揮が賞賛されるとき、女はいない』(Assenza della donna dai momenti celebrativi della manifestazione creativa maschile)は、こうした思想を展開している。この短い宣言は、リヴォルタ・フェッミニッレのグループが、アートワールドから身を引きつつも、男性性や家父長制的な関係の外で、異なるタイプの創造性を集団で求めているということを、高らかに告げるものであった。
リヴォルタ・フェッミニッレによれば、女性の抑圧に対して芸術が共犯関係にあるとするならば、女性たちは二つの選択肢に直面していることになる。すなわち、「創造的であると男たちが歴史的に定義してきたものの水準で対等になること[……]、あるいは[……]男性的なモデルが押し付けてくる抑圧の中で培われた女性独自の創造性を取り戻し、女性の自律的な自由[を求めること]」である(19)。
このオルタナティヴな創造性がどのような性質のものなのかについては、はっきりと説明されていないのだが、この声明が示しているのは、女性の抑圧を維持する権力構造の内部ではそれが存在し得ないということであった。
これとは逆に、『自画像』の短い文章は、女性芸術家の問題を取り上げている。それは、女性芸術家たちをそれ自体として支持することのあからさまな拒否に先立つものだった(このロンツィの立場は、結果的にカルラ・アッカルディとの友情に終わりをもたらすことになった)。ロンツィの女性芸術家たちに対する態度は、とりわけフェミニズム美術史の観点から見れば、おそらく彼女の思想の中でももっとも物議を醸す一面であろう。カルラ・アッカルディは、『自画像』に参加した芸術家の中では唯一の女性であり、重要なことに彼女の発言は、すぐ後にロンツィがフェミニズムへ転向することを告げる記述で締め括られている。
ただ今となってはそうではありません……こうした男女の問題が、まさにあって、そういうことが〔考察対象として〕必要なのです。ある日誰かが私に「そんな問題なんてない」と言うのです。いや、いや、いや……次の日起きると、問題はまだそこにあるのです。[……]女性というものは[……]少しの幸せでも享受していられるよう自分がもがいているのだという事実を、いつでも念頭に置いておかねばならないのだから(20)。
ロンツィはアッカルディとの対話を二件、テープレコーダーで記録している。一つは1966年のもので、もう一つは1969年のものだ。興味深いことに、二人の女性はすでに女性の創造性と女性芸術家の役割について1966年に議論しており、同時に、この年のアッカルディの作品《カーテン》のフェミニズム的解釈を共有する提案を行なっている。ロンツィがのちにみずからの日記の中で強調しているように、二人の関係は、ロンツィがフェミニストになる過程において欠かすことのできない役割を果たした。彼女は次のように書いている。
「リヴォルタ・フェッミニッレは二人の人物から生まれた。[カルラ]と私だ。私たちが男性の主体性を問うたのは、まさに私たちが自分たちを主体の位置においていたからだ。[カルラ]は芸術家として、私は別のアイデンティティを意識する者として(21)」。
彼女たちの友情は非常に強く、打ち込んでいるものも共有していたにもかかわらず、二人の女性たちは1973年頃にその友情の幕を閉じた。というのもロンツィは、アカルディが芸術家としてのアイデンティティを持っていることが、文化解体の試みとは両立しないと考えていたからである。
彼女たちの衝突が関わっている問題とは、どのようにフェミニズムの創造性を考えることができるのか、それがどのようにアートワールドと関係しているのかということであった。リヴォルタ・フェッミニッレの初期段階においては、芸術とフェミニズムのあいだの結びつきがどのように可能になるのかという問題については議論されていたものの、芸術はもっとも差し迫った問題ではなかった。もちろんアッカルディだけが会合に参加した芸術家だったわけではない。スザンヌ・サントーロ、シモーナ・ヴェッレ、アンナ・マリーア・コルッチ、そしてシルヴィア・トルッピらもまた、ローマとミラノの両都市で、このグループに参加した。しかしながら、彼女たちの多くは、みずからの芸術家としてのアイデンティティが自己意識(autocoscienza)の目覚めにより引き起こされる文化解体の試みとは両立できないと感じていた。
一人の男性彫刻家〔ピエトロ・コンサグラ〕と生活を共にし、イタリアの前衛の第一線でほとんどの時間を過ごしてきたロンツィにとっては、私生活とフェミニズムの実践双方において、芸術とは必然的に出発点であり、同時に比較のための参照点でもあった。『自画像』は、創造性の神話に異議を唱えるような関係性の空間の可能性を拓いたのだが、当然のことながら、男性芸術家たちはみずからの特権を手放そうとはしなかった。ロンツィはのちに日記の中で、繰り返し創造性を、男性の神話として、また自由への虚偽の約束として、幻想として、そして文化の役割をとりわけ力強く表明し女性たち自身による創造性の真の表現を妨げる行為として、退けている。
ロンツィにとって、芸術が男性文化により達成された「もっとも高次の意識」を象徴している限り、芸術家としてのアイデンティティを得るということは、家父長制への許し難き妥協に等しいものであった。
わたしはフェミニストの女性芸術家たち(feministe-artiste)に尻込みした。女性的な表現を強化するのだと言い訳しながら、彼女たちは利益を得ることができるようなフィールドの中だけで――つまり男性文化の内部で――、女という存在が示唆しているものを利用しているのだ。そうすることで彼女たちは、社会的なアイデンティティと引き換えにみずからを売ったりなどしない女性の同志たちを、裏切っているのである(22)。
ロンツィは芸術家たちに――とりわけ女性芸術家たちに――敵意を向けていたにもかかわらず、女たちによる表現についての彼女の考えは、批評家としての自身の経験と無関係のものではなかった。
最初ロンツィは、芸術家たちと女たちとの同盟を提案し、「非−家父長制的」で分散した創造性の諸形態について考えをめぐらせていた。この創造性とは、芸術家と観客とのあいだの上下の分離に根差しておらず、むしろ自己意識(autocoscienza)の横のつながりに根差すものであった。
ロンツィとアッカルディは、早くも1966年にはこうした問題について議論している。それは女性芸術家の場合に生じる差異について彼女たちが話し合っていた時だった。アッカルディは次のように述べている。「芸術はいつも、男性の縄張りであり続けてきた。創造性という、男性特有の領野に入ってすぐに(加えて)私たちがしなければならないのは、それを取り巻き近づき難くしている威光のオーラを、まるごと剥ぎ取ることなのだ(23)」。
リヴォルタ・フェミニッレ誕生に先立つ数年前からの(そしてそれに並行する数年間の)アッカルディの制作は、彼女がロンツィと絶え間なく対話しながら、女性的表現を伝える作品を構想する濃密な熟成期間を過ごしていたことの証左となっている(24)。
ロンツィにとって美術史とは、芸術家の男性的アイデンティティとその受動的な他者〔としての女性〕とのあいだの非対称性にもとづき、ジェンダーを排除した創造性の概念を展開した学問であった。ロンツィの著述をとおして、「創造性」という言葉は、複雑でしばしば矛盾するやり方で登場する。というのも彼女はその意味を再定義しようとしていたからだ。
私は『自画像』において、[芸術家たちに]喋らせることで、私自身の存在を異なる方法で作用させ、彼らを自分自身へと立ち戻らせたかった。[……]意識がたった一つの役割に閉じ込められている時にはいつでも、芸術家がより適切な観客を期待しているという事実から、袋小路へと入り込んでしまう。それゆえ、家父長的なタイプの創造性ではないと了解している場合を除き、フェミニズムの内部で創造性について話すのは間違っている。ある女性の自己意識(autocoscienza)が、別の女性の自己意識の前で立ちすくみ、承認されることがないとすれば、その自己意識は不完全なのだ(25)。
この一節が明らかにしているのは、いかにロンツィが、非対称性と権力にもとづく制度化された表現形式として芸術を捉えていたのかということだ。彼女にとっての芸術とはすなわち、観客が「ものごとの中に入り込」み参加することを、妨げるものだったのだ。したがって、女性の受動性にもとづくこうした主体-客体の関係性は、対話や共鳴、参与のために放棄されねばならない。このことにより、自己意識(autocoscienza)が互いに関係する空間の中で、オルタナティヴな表現方法が探求されるのである。
ロンツィにとって、フェミニズムの表現性は芸術と同一視され得るものではない。というのもそれは、文化というよりも生活に関係するものであるからだ。「あらゆる表現が存在のレベルにとどまることができるような世界があったらいいのにと思う(26)」と、彼女は自身の日記に記している。
ロンツィの撤退
1981年に、キュレーターでありアルテ・ポーヴェラの一団を率いていたジェルマーノ・チェラントが、パリのポンピドゥー・センターで展覧会「イタリアのアイデンティティ――1959年以降のイタリアにおける美術」を開催した。それはイタリアのネオ・アヴァンギャルドとポスト・アヴァンギャルドの意義を評価することを目的とした企画であった(27)。『自画像』は出版されてからもずっと注目されることなく見過ごされていたのだが、ロンツィともともと知り合いだったチェラントは、展覧会カタログに文章を執筆するよう彼女に依頼した。何を寄稿しようかと思いをめぐらせるメモの中で、ロンツィは自身が美術批評家をやめた瞬間を思いかえし、当時自分の関心ごととなっていたところに立ち戻ることができるのだろうかと自問している。
当時私が感じていたのは、私自身のこととして、一人称でこの問題を考える必要があるということだった。そしてそれは、制度の外であるほかないのだということがわかった。というのも制度は、物事が遠くに行き過ぎてしまうことを許さないからだ。[……]この撤退のおかげで私は、分離した立場を見出すことができた。それは私を立ち戻らせてくれるだろう。制度ではなく、動機となる地点へと(28)。
この引用が明らかにしているのは、美術批評の制度的な枠組みには回収され得ない観点から芸術や創造性について考察する可能性が、ロンツィにとって重要であったということだ。このことから私たちは、なぜロンツィが「今日におけるルーシー・リパード〔アメリカ人美術批評家で、フェミニズム・アートの支持者〕」(29)として振る舞うことを拒んでいたのか理解することができる。この事実は、次のことを強調しているのだ。
すなわち、芸術とフェミニズムとの出会いを展覧会企画の指針に統合するという当時の試みに加わることは、彼女には難しかったのである。しかも彼女の著述には、芸術が家父長制と性差を含意しているのだとする考察が散りばめられることになる。こうした考察は、断片化されていて体系化されていないかもしれないが、それらをとおしてロンツィは、女たちで結束する立場から芸術における家父長的な構造への批判を展開したのであり、この立場が彼女をアートワールドの外に否応なく位置づけることになったのだ
興味深いことにロンツィは、みずからの撤退を、1968年にアンディ・ウォーホールに向け銃で発砲したヴァレリー・ソラナスに喩えている。この事件を彼女は、ソラナスが「アートワールドに所属すること」(30)から解放された出来事として解釈したのである。
ロンツィは、ソラナスとは反対に、アートワールドというコンテクストの中でかつて生み出したものを否定する必要はないと感じていたことを強調する一方で、ソラナスの行為の切迫感や挑戦のうちに、みずからの撤退を間接的に承認する要素を見出している(31)。ロンツィにとって、アートワールドを離れることは自律性へと向かうために必要な一歩だったのだが、ソラナスの単独の振る舞いとは違って、彼女の撤退は彼女の生活のあらゆる側面の変容に関わるような集合的経験を引き起こすものだった。
この試みは、これまで見てきたように、人々と共存するためのオルタナティヴで反階級的な方法を築く可能性のうちに予言されていたものである。したがって彼女が自分を美術批評家とみなすのを拒んだことも、女性のアイデンティティとそのほかの社会的な相互関係の双方を規定してしまうような、あらかじめ定められた振る舞いや社会的相互作用と芸術とが結ぶ共犯関係の拒否として解釈することができる。
ロンツィがアートワールドから撤退し小さなグループに所属することを選択したのが事実である一方で、彼女は隠れた存在でありたいと望んでいたわけではなかった。実際にこの点において、彼女の撤退は両義的なものだった。女性たちで団結する場の構築が、自律性を得るためになくてはならない一歩だった一方で、自律性は、自由な振る舞いがほかの女たちの中で「共鳴」する、ないしは「呼応し合う」(rispondenza)ような集団的な企てのうちでしかあり得ないものだった。
このことは、なぜ個人同士の関係性がロンツィにおける女性同士の結束の思想にとってかくも重要だったのかを説明している。それは孤独とは異なるものである。反対に彼女のフェミニズムは、グループの外へと潜在的に広がっていくことができる集団的な実践とみなすことができる。それは、彼女とピエトロ・コンザグラとの関係においても同様であった。この点について、一つの応答(rispondenza)が失敗すると、「一問一答のように、個人が存在しておらず、その人が生ける過ちであるという印象」が生み出されるという(32)。「自己意識」(autocoscienza)とはその反対に、自己表現の場を拓くもの、あるいはむしろ「数えきれぬ応答(rispondenza)を対話に呼び込むような、意識の数えきれぬ表現(33)」の場を拓く。
しかしながら、自律性の空間を拓くためには代償も払わなければならなかった。芸術を離れる――それにともなってほかの活動や役割(「作家」・「詩人」・「フェミニスト」と言った彼女以外の何者か)に自己同一化することをいっさい拒む――というロンツィの決意が意味していたのは、彼女がやろうとしていたことがせいぜい理解し難いものにとどまるか、最悪の場合それがまるで存在しなかったかのように無視されてしまう宿命にあるということだった。
これは、ピエトロ・コンサグラとロンツィの対話をもとにした著書『もう行っていいよ』のなかで主に扱われている問題の一つである。コンサグラと愛を交わし生活をともにした二〇年を経て、この時彼らの関係は破局を迎えている。対話は、ロンツィのローマのアパートで四日間にわたって記録され、それから数ヶ月後に文字起こしされ編集された。それは何年も前の彼女の行いを想起させるようなものとして編集された。ロンツィは、愛と創造性の問題とが絡まり合う、音声で記録されたこのアーカイヴを組み立てていくなかで、生きたやりとりの真正性を捉えて新たな表現形式の追求のための足がかりにしたいという気持ちに、忠実であり続けている。
ロンツィはこの対話のなかで、彼女の撤退が持つ意味に立ち戻り、みずからの不安定な状況を、成功をなした芸術家としての立場を享受しているコンサグラとは対照的なものとして浮かび上がらせた。ロンツィの活動はその生活に一致するもの、すなわち人に気づかれないものであった。これに対しコンサグラの環境は完全に、社会的・文化的承認のメカニズムにより示されるものだった。ロンツィにとって、これらのメカニズムは、女性が排除されている家父長的な構造に一致するものであった。『もう行っていいよ』の次の一節において彼女は、女の生活は重要ではないという認識とともに生きていくことから何が生じるのかについて述べている。
女は失敗を経験する。多くの女たち、その大半にとって、この条件は耐えがたいものである。なぜなら、私個人としてあなたたちに言えることなのだが、この失敗を意識しながら一生を送ること、またそうした意識があなたに課す責務とともに生きていくこと――つまり自律した存在であること、伝統的な文化の濫用に対して闘いを挑むこと、生活のあらゆる微細な局面に存在している、自分を麻痺させるものすべてを、いつでも発見しなければならないこと――、そんな人生はとても生きられたものではないからだ(34)。
ロンツィが女の失敗と言うときに指し示しているのは、女たちが社会的・文化的な承認からこれまで排除されてきたという事実、今でも排除されているという事実である。だが彼女はまた、主体生成のプロセスを目に見えるようにしようと努めているにもかかわらず、彼女自身の主体への生成がいかに未承認のままであり続けるのかについて考察している。ここで、これらの言葉が80年代初頭に書かれているということに注意を向けることは重要である。
フェミニズムの制度化と復活の両義的なプロセスを経験した10年を経て、このときすでにメディアは、バックラッシュ(riflusso)について話題にし始めていた(35)。この状況の変化のなかで、ロンツィの撤退は、フェミニズム運動内における数々の立場から距離を置く手段にもなった。彼女はこの運動を、メインストリームの文化に妥協しそれに囲い込まれたものとして考えていた。このことはすでに、「私は私と言う」(io dico io)と題されたリヴォルタ・フェミニッレ第二宣言に記されていた(36)。
同様にして、コンサグラが彼女に、ある程度妥協を受けいれさえすればものごとはもっとずっと簡単になるのだと納得させようとしていた(例えばコンサグラは、みずからの展覧会のオープニングに参加することを勧めているのだが、彼女はそれを拒んでいた)にもかかわらず、ロンツィは自分にとって大事であったこと、つまり彼女自身の生活と、あらゆる社会的慣習や社会的身分への同一化を超えて自分自身になろうとする努力こそ必要なのだと主張している。
実のところ、『もう行っていいよ』のなかで、「カップルはある種のメタファーとなっている。それは社会の諸権力が演じられる劇場なのだ。労働と好きでする仕事という二本の柱のまわりで、議論は繰り広げられる(37)」。
ロンツィはまた、1970年に書かれた最初の「リヴォルタ・フェミニッレ宣言」ですでに問題とされていたことのいくつかを、ここで発展させている。効率性と労働を含む競争的な資本主義構造を拒絶し、かわりに性の解放と非生産性を求めるこの宣言の主張は、今や、資本主義構造がみずからの生活のもっとも私的な領域にまで浸透している状況から逃れようと模索する女性たちの日々の闘いの中に、織り込まれている。
『もう行っていいよ』は、私的なことがいかに政治的なのかということを示す、驚くべき資料なのである。仕事と個人的・私的人間関係とのあいだの分離についてのロンツィの自覚は、社会的な生活が組織される基盤を成すものであり、認識と変容に向けた彼女の闘いにおいて、きわめて重要な土台となっている。このことは、「とても生きられたものではない」女の生活がどれほど強くロンツィを美術批評の放棄へと駆り立てたのかということを説明している。彼女とコンサグラとの対話にも見られるように、「芸術」は諸々の制度や権力関係、戦略、さらには女性たちを構造的に抑圧してきた社会的な付き合い、生活、労働の諸形態として現れてくる。
こうしたことを背景として、女性たちで団結する空間のおかげで、ロンツィは、自分自身の失敗を出発点とし、生活の様々な諸形式で実験的取り組みを行うことができるようになった。この実験のためには、既存の社会構造に敵対し、主体生成の集団的なプロセスを経ることが、前提として必要とされたのである。
(1)C. Lonzi, ‘Mito della proposta culturale’, in M. Lonzi, A. Jaquinta, C. Lonzi, La presenza dell’uomo nel femminismo (Milano, 1978), p. 151. これ以降、特記されたものをのぞき、すべてのイタリア語は筆者による翻訳である。
(2)C. Lonzi, Autoritratto (Bari, 1969; Milano, 2010). いかに続く引用は2010年度版を参照している。
(3)「自己意識」(autocoscienza)については、次を参照のこと。Milan Woman’s Bookstore Collective, Sexual Difference: A Theory of Social-Symbolic Practice, trans. P. Cicogna and T. De Lauretis (Bloomington, IN, 1990); L. Passerini, Storie di donne e femmisiste (Torino, 1991).
(4)次を参照のこと。P. Di Cori, ‘Cultura del femminismo. Il caso della storia delle donne’, in Storia dell’Italia Repubblicana, vol. III, Istituzioni, politiche, culture (Torino, 1997), pp. 809–11. 権威あるフェミニストの象徴へとロンツィが変化したため、学術的研究においては、そのような立場に彼女を置くことで彼女を「裏切る」ことになるのではないかという不安を表明し、彼女への敬愛の気持ちを示すような傾向が広く認められるようになった。カルラ・ロンツィ研究の第一人者と言って良いルイーザ・ボッチャも、こうした態度に共感を示している。M.L. Boccia, Con Carla Lonzi. La mia opera è la mia vita (Roma, 2014).
(5)2000年代の半ばまでは、カルラ・ロンツィについての伝記といえばほとんどマリア・ルイーザ・ボッチャの1990年代に出版された著書に限られていたことを考えれば、このことはとりわけ著しい傾向だった。M.L. Boccia, L’io in Rivolta. Vissuto e pensiero di Carla Lonzi (Milano, 1990)
(6)L. Ellena, ‘Carla Lonzi e il neo-femminismo degli anni ‘70: disfare la cultura, disfare la politica’, in V. Fiorino, L. Conte and V. Martini (eds), Carla Lonzi, la duplice radicalità (Pisa, 2011), pp. 117–22.
(7)F. Ventrella, ‘Carla Lonzi’s Artwriting and the Resonance of Separatism’, European Journal for Women’s Studies, 21/3 (August 2014), p. 283.
(8)カルラ・ロンツィとイタリアのフェミニズム美術批評・美術史との関係については、次を参照のこと。J. Russi Kirshner, ‘Voices and Images of Italian Feminism’, in C. Butler (ed.), Wack! Art and the Feminist Revolution, exh. cat. (Los Angeles, Museum of Contemporary Art, 2007), pp. 384–99.
(9)M. Lonzi, ‘Un rifiuto comprensibile’, in C. Lonzi, Rapporti tra la scena e le arti figurative dalla fine dell’800 (Firenze, 1995), pp. xv–xix.
(10)『自画像』に含まれる芸術家は次の通りである。カルラ・アッカルディ、ジェットゥリオ・アルヴィアーニ、エンリコ・カステラーニ、ピエトロ・コンサグラ、ルチアーノ・ファブロ、ルーチョ・フォンタナ、ヤニス・クネリス、マリオ・ニグロ、ジュリオ・パオリーニ、ピーノ・パスカーリ、ミンモ・ロテッラ、サルヴァトーレ・スカルピッタ、ジュリオ・トゥルカート、サイ・トゥオンブリー。彼らの名前は本のタイトルの一部になっている。彼らのなかには、のちにアルテ・ポーヴェラのグループに参加する者たちもいれば、当時すでにイタリアのネオ・アヴァンギャルドの鍵となる人物となっており、1950年代から活動をしていた者たちもいた(アッカルディ、コンサグラ、フォンタナなどである)。この時すでにローマにいたサイ・トゥオンブリーは、話をしていない唯一の人物なのだが、ロンツィは彼の沈黙を、1962年に自身が彼に送った質問への答えとして本の内容に含めることに決めた。『自画像』については次を参照のこと。L. Iamurri, ‘Intorno ad Autoritratto. Fonti, ipotesi, riflessioni’, in V. Fiorino, L. Conte, V. Martini (eds), Carla Lonzi: la duplice radicalità, cit., pp. 67–86; and G. Zapperi, ‘L’autoportrait d’une femme. Préface’, in C. Lonzi, Autoportait, translated from the Italian by M.-A. Maire Vigueur (Paris, 2012), pp. 7–35.
(11)C. Lonzi, Autoritratto, cit., p. 29.
(12)C. Lonzi, ‘La solitudine del critico’, L’Avanti, 13 December 1963(次の著書に再録。C. Lonzi, Scritti sull’arte, ed. L. Iamurri, L. Conte, V. Martini (Milan, 2012), pp. 353–6.
(13)Carla Lonzi, Preface to Autoritratto, translated into English in R. Flood (ed.), Zero to Infinity: Arte povera 1962–1972, exh. cat. (Minneapolis, MN, Walker Art Center, 2001), p. 10.
(14)注13を参照のこと。
(15) Idem.
(16)C. Lonzi, ‘La critica è potere’, NAC. Notiziario d’arte contemporanea, n. 3, dicembre 1970, pp. 5–6 (次の著書に再録。C. Lonzi, Scritti sull’arte, cit., pp. 647–50).
(17)C. Lonzi, Autoritratto, cit., p. 32.
(18)C. Lonzi, ‘Let’s spit on Hegel’ (1971), in: P. Jagentowicz Mills (ed.), Feminist interpretations of G. F. W. Hegel, trans. G. Bellesia and E. Maclachnan (University Park, PA, 1996), p. 292.
(19)Rivolta femminile, ‘Assenza della donna dai momenti celebrativi della manifestazione creativa femminile’ (1971), in C. Lonzi, Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale e altri scritti (Milan, 1974), p. 64.
(20) C. Lonzi, Autoritratto, cit., p. 300.
(21)C. Lonzi, Taci, anzi parla. Diario di una femminista (Milano, 1978); now: et al./edizioni 2010, p. 28. 以降本文におけるすべての引用は2010年版からのものである。
(22) C. Lonzi, Taci, anzi parla, cit., p. 949.
(23)C. Lonzi, ‘Discorsi: Carla Lonzi e Carla Accardi’, Marcatré, nn. 23–5 (June 1966), pp. 193–7 (C. Lonzi, Scritti sull’arte, cit., p. 477).
(24)L. Cozzi, ‘Spaces of Self-consciousness: Carla Accardi’s Environments and the Rise of Italian Feminism’, Women & Performance: A Journal of Feminist Theory, 21:1 (2012), pp. 67–88.
(25) C. Lonzi, Taci, anzi parla, cit., p. 35.
(26)C. Lonzi, Taci, anzi parla, cit., p. 949.
(27)G. Celant, Identité italienne. L’art en Italie depuis 1959, exhib. cat. (Paris, Centre Georges Pompidou, 1981).
(28)未刊行の手記だが、部分的に次の文献に掲載されている。M. Lonzi and A. Jaquinta, ‘Vita di Carla Lonzi’, in C. Lonzi, Scacco ragionato. Poesie dal ‘58 al ‘63 (Milano, 1985), p. 68.
(29)マニュエッラ・デ・レオナルディスとのインタビューの中で、スザンヌ・サントーロが報告している。S. Santoro and M. De Leonardis, ‘Intervista’, in: Art Apart of Culture(www.artapartofculture.net/2011/01/30/suzanne-santoro- intervista-di-manuela-de-leonardis)【2014年9月閲覧】.
(30)C. Lonzi ‘Itinerario di riflessioni’, in M.G. Chinese, C. Lonzi, M. Lonzi and A. Jaquinta, È già politica (Milano, 1977), pp. 35.
(31)C. Lonzi, ‘Mito della proposta culturale’, cit., p. 141.
(32)Ibid., p. 148.
(33)Ibid., pp. 148–9. 次のように記されている。「アイデンティティとは、〈質問〉を根本的に拒絶することから生まれるのであり、したがって〈答え〉を拒絶することから生まれる。つまりアイデンティティは、〈質問〉を粉砕して、対話における無数の応答に訴える「意識の無数の表現」へと変えるのである。ここで(〈答え〉ではなくむしろ)応答と言っているのは、私がそれ〔別の女性の意識〕に触れているときにいつも、応答という作用が他者の意識の表現によって生み出されるからだ。」
(34)C. Lonzi, Vai pure. Dialogo con Pietro Consagra (Milano, 1980; Milano, 2011), p. 30.
(35)イタリアのフェミニズム運動の時代区分については、次を参照のこと。P. Di Cori, ‘Il movimento cresce e sceglie l’autonomia. 1974–1979’, in A.M. Crispino (ed.), Esperienza storica femminile nell’età moderna e contemporanea, Parte seconda, Unione Donne Italiane, Circolo ‘La Goccia’ (Roma, 1989), pp. 107–17.
(36)Rivolta femminile, ‘Secondo manifesto di Rivolta Femminile: io dico io’, in M. Lonzi, A. Jaquinta and C. Lonzi, La presenza dell’uomo nel femminismo, cit., pp. 7–9.
(37) Claire Fontaine, ‘We are all Clitoridan Women. Notes on Carla Lonzi’s Legacy’, e-flux journal, 47 (September 2013), http://www.e-flux.com/journal/we-are- all-clitoridian-women-notes-on-carla-lonzi’s-legacy/.
著者紹介
ジョヴァンナ・ザッペリ(Giovanna Zapperi)
2005年にパリ社会学高等研究院(EHESS)にて博士号を取得後、フンボルト大学客員教授、ナント高等研究院研究員、ブールジュ高等美術学院(ENSA)講師を経て、2017年9月よりトゥール大学教授。2007年から2009年まで雑誌 Multitudes の編集委員をつとめる。近年はイタリアのフェミニストであるカルラ・ロンツィの美術批評および美術史研究について研究している。単著に L‘artiste est une femme. La modernité de Marcel Duchamp (Presses Universitaires de France, 2012) , Carla Lonzi. Un’arte della vita (DeriveApprodi, 2017).
訳者
松井裕美(まつい ひろみ)
1985年生まれ。パリ西大学ナンテール・ラ・デファンス校(パリ第10大学)博士課程修了。博士(美術史)。現在、神戸大学国際文化学部准教授。専門は近現代美術史。
単著に『キュビスム芸術史』(名古屋大学出版会、2019年)、共編著に『古典主義再考』(中央公論美術出版社、2020年)、編著に『Images de guerres au XXe siècle, du cubisme au surréalisme』(Les Editions du Net, 2017)、 翻訳に『現代アート入門』(名古屋大学出版会、2020年)など。


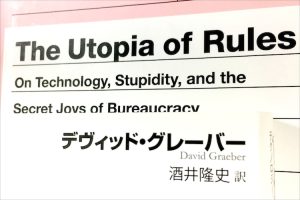
![Read more about the article 【連載】誰がパリ五輪に抵抗しているのか?[第4回]後編/佐々木夏子](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2022/12/スクリーンショット-2022-12-15-18.00.00.png)

