マルクスの反植民地主義のルーツについて(大畑 凜、森田 和樹 訳)
ティエリー・ドラポー
本稿は、Jacobin誌のWeb版で2019年1月に掲載されたティエリー・ドラポー(Thierry Drapeau)による記事 “The Roots of Karl Marx’s Anti-Colonialism” の日本語訳である。この記事はその後、“Marx and the Chartist” と改題されて、Tribuneにも転載されている。
マルクスのヨーロッパ中心主義が批判されて久しいが、しかし他方で、マルクスが当時の左派としては異例の植民地主義批判の視点をもちえた点も評価されている。
ここにわたしたちが訳出した短いエッセイは、そのマルクスの異例性が、決して「偉大なる」マルクスの頭脳から飛び出してきたわけではないことを教えてくれる。すなわち、マルクスの後年のプロジェクトを長期にわたって規定する──そして、わたしたちの時代にもアクチュアリティを保持しうる要因である──その洞察は、当時の労働者たちからえられたこと、そしてその洞察には、社会運動とのつながりを失わず、つねにそこからなにごとかを学ぼうとするひとりの知識人の姿勢が認められるのである。デヴィッド・グレーバーの「啓蒙の脱植民地化」プロジェクトの一翼ともみなしうる試みの一端を、ここで紹介するにいたったゆえんである(『民主主義の非西洋起源について』の「訳者あとがき」を参照)。
著者のドラポーは大西洋を跨いだ労働者階級によるインターナショナリズムの歴史を専門としており、ヨーク大学でPh.Dを取得後、現在はケベック大学ウタウエ校で労使関係を専門とする講師を務めている。また、みずからの単著として The Long First International: Workers of the Atlantic World Unite for Emancipation, 1714-1864 を執筆中であるという。
訳者
映画『若きカール・マルクス』(日本語タイトル『マルクス・エンゲルス』)で監督のラウロ・ペックは、パリ屋外でのピエール=ジョゼフ・プルードンのスピーチの最中に、名もないアフリカ系のフランス人が真摯にもそこに割り込んでいく場面を冒頭で演出している。
周囲を取り巻く労働者たちとは対照的に、優雅なドレスとトップハットに身を包んだその黒人紳士が演説に一瞬の間割り込んだのは、その著名な雄弁家〔プルードン〕に、産業化によってますます技能を脅かされる職人たちの自由のみならず、プロレタリアートからなるアンダークラスの自由をも語るように促すためだった。かれは声をあげた、「工夫、機械工、製鉄工たちよ!」。
この有色市民(citoyen de couleur)の隣に座っていたマルクスとかれの生涯のパートナーで共同思索者でもあったジェニーは、フランス・アナーキズムの父に対するこの批判的な発言を、ともに歓迎しているようにみえる。
このシーンが記憶に残るのは、工場労働者を含めた労働者階級の概念をプルードンに勧めるのがマルクスではなくてひとりの黒人──おそらくは植民地主義と奴隷制に直接に、あるいは係累を遡ればむすびついている──ゆえであるのは確実である。
そこでの議論が、植民地世界の人種化され奴隷化されたプロレタリアートの問題にはっきりとふれてはいるわけではない。だが、潜在的にはふれている。というのも、その黒人の登場人物を通じてペックがわたしたちに、以下の点を想起させるからである。
すなわち、マルクスがこのときいまだ人種的奴隷制に支配された植民地をもつ帝国の中枢で生活し思索していたこと、そして、こうした植民地支配の文脈が帝国のメトロポリタン中核における労働者階級の内部構成をかたどっていたこと、である。
歴史がそうであったように、映画においてもいまだ、パリ時代のマルクスは知的にも政治的にも植民地主義と奴隷制に興味を示していない。それゆえ、ペックの映画のなかでは、マルクスは自身と同じ見識を共有しているのはあきらかであるその黒人の発言者へ話しかけることはせず、むしろかれがひどく批判的であったプルードンに話しかけている。
ハイチ人監督が浮き彫りにしてみせた若きマルクスの思考のなかのこの植民地主義的な落とし穴は、マルクス個人の特質というだけではなかった。それは、1843年から1845年にかけ光[啓蒙]の都(Ville Lumière)パリのカフェやサロン、集会などで、マルクスがみいだし、交流をおこなった、労働者階級の政治の反映なのである。
かれらは必ずしも奴隷制支持ではなかったが、プルードンからルイ・ブランキ、ピエール・ルルーにいたるまで、程度の違いこそあれ、すべての主要なフランスの社会主義たちは、1840年代初頭の段階で、国内での「社会問題」を解決する方法として、そして社会主義を海外へと輸出するための方法として、植民地支配の意義を認めていた。
アルジェリア *1 やグアドループ *2 での抑圧からの解放の呼びかけと戦いは、それゆえフランス社会主義者たちの政治に対して差し迫った関心とはならなかったのである。したがって、植民地主義は「抽象的な」プロレタリアートに対してもまた、差し迫った関心となることはなかったのだ。
マルクスが『パリ手稿』およびその後の『コミュニスト宣言』で、資本主義の転覆という課題を委ねようとしたのは、まさにこの「抽象的な」プロレアートの双肩であった。
事態が変化したのはマルクスがロンドンに移住してからである。その独特な労働者階級文化に深いかかわりをもったこと、とりわけラディカルなチャーティストで労働者詩人でもあったアーネスト・ジョーンズと密接な関係をもったことが、かれの視野の拡大にとって鍵となった。
急進的(ラディカル)ロンドン
新たに成立した保守体制によってフランスから追放されたのちの1849年8月後半にマルクスがロンドンにたどり着いたとき、諸革命の砂煙はまだ大陸ヨーロッパに漂っていた。
その一年前、チャーティズム──労働者階級によって導かれたイングランド史上最初の大衆運動──の革命派は、イギリス海峡を北に越えた地〔イギリス〕にもその春〔1848年の革命は「諸国民の春」と呼ばれていた〕を呼び寄せようと努力していた。
1848年6月の初旬、イースト・ロンドンで情熱的な演説を行ったアーネスト・ジョーンズは、群衆へ向かって、まずもってアイルランドで自由を実現すべしと宣言し、ブリテンによるくびきからのアイルランドの解放を呼びかけた。
かれはただちに逮捕され、二年間の独房監禁を命じられる。まもなくチャーティストの急進派のあいだで首都での武装蜂起の計画がたてられる。計画ではジョーンズを留置所から解放し、政府を転覆して、共和国を創設する予定だった。

(1819-1869)
この計画の共謀者のなかにはウィリアム・ダウリングとトーマス・フェイという二人のアイルランドの自由を求める闘士と、洋服屋で奴隷制廃止論者の黒人チャーティスト、ウィリアム・カッフェイ──西インド諸島の奴隷の息子であった *3 ──がいた。
したがってその共謀は深く大西洋横断的な様相を呈しており、これがもし成功していたとしたら、歴史家のピーター・ラインボーとマーカス・レディカーが『多頭のヒドラ』で描きだしたような、海盆を通じた「雑多なプロレタリアート」による長期に渡る都市蜂起の伝統を復活させただろう。
この計画は露見し、マルクスがテムズ川の埠頭についた時にはすでに挫折していた。ジョーンズは一年ちかくにわたり幽閉され、カッフェイ、ダウリング、フェイと他三人の共謀者たちはオーストラリアで無期懲役の刑に服していた。チャーティズムは深刻に弱体化したものの、そのラディカルな政治的伝統は生き続けた。
独立の新聞編集者で、それ以前は船乗りであった、友愛民主主義者協会の指導者ジョージ・ジュリアン・ハーニーに率いられたチャーティスト運動は、その運動の左派部分を中心として復活の途上にあった。イングランドの革命の失敗から教訓を得たハーニーは、新たに社会主義を基盤にして独立した労働者階級の運動としてチャーティズムを再編成しようとしていた──そして、それは「憲章とそれ以上のなにものかを」という標語に結実する。
ロンドンを基盤にしたドイツ人の共産主義者同盟との関係が破綻していたマルクスは、ハーニーの赤色共和主義(Red Republicanism)に惹きつけられ、熱狂とともに1850年、その組織に加わった。その年の11月、ハーニーの新聞『レッド・リパブリカン』は『コミュニスト宣言』の初めての英訳を発表した。その間にジョーンズは刑務所から解放されると、ハーニーの「赤派(レッズ)」に加わってチャーティスト運動を再開するが、そこでジョーンズはマルクスの友人となるのである。
マルクスとジョーンズ
ジョーンズとマルクスは1850年の時点でともに32歳であり、二人とも生まれはドイツだった。
ベルリン在住のイギリス人貴族のもとで生まれ、成人するまでかの地で教育を受けたジョーンズはマルクスの母語で流暢にコミュニケーションをとることができただけでなく、マルクスと共通の文化をある程度共有しており、そのおかげもあってかれらの友情は強固なものとなった。かれらはまもなく政治を越えて意気投合したのである。
マルクスはジョーンズの雄弁にすぐさま感銘を受けるようになった。かれは1850年から51年にかけてジョーンズの講演や演説に幾度も参加したが、それらの演説はチャーティストの運動を基盤から再結集させるべくイングランドを飛び回るものだった。
マルクスがみるに、ジョーンズはそのとき「最も才能に溢れ、信念に満ちた、チャーティズムの力強い象徴」であった。それゆえ、ジョーンズはチャーティストの運動体内部において事実上の指導者の役割を担っていたのである。ジョーンズが週刊の新聞『ノーツ・トゥー・ザ・ピープル』の発刊を決意したのは1851年5月のことであるが、マルクスは協力者として名乗り出ることを躊躇わなかった。
このときのマルクスは、『ニューヨーク・デイリー・トリビューン』紙のヨーロッパ特派員の仕事を主な収入源としていたが、チャーティストの報道機関にマルクスがジャーナリストとして関与したのは、イギリスの労働運動へ直に接触するためであった。
かれは『ノーツ・トゥー・ザ・ピープル』に二つの記事を執筆したが、これらはどちらもフランスでの1848年革命についてのものである。また、少なくとも六本の記事をジョーンズと共同執筆した。さらに、のちにエンゲルスにあかしたところでは、マルクスは1851年から52年の間にジョーンズの名で書かれたすべての経済記事の執筆にアドバイスを与えていた。伝えられるところでは、ジョーンズの執筆を直接的に補助することもあったという。その記事の合計は『ノーツ』で発表された全記事の三分の二を越えるものだった。
こうした関わりがマルクスを新たな知的環境へ没頭させ、そこでかれは反帝国主義を含むチャーティズムの思想と政治的視座に触れ、そこから学んでいったのだ。
帝国に抗するチャーティズム
ジョーンズとのジャーナリスティックな共同制作と政治的協力関係を通じて、マルクスは、そのパリ時代とは違い、植民地侵略に対する長い抵抗の歴史をもつ労働運動とむすびつくことになった。
その労働運動は、17世紀のディガーズとレヴェラーズ *4 や18世紀のペイン主義ジャコバン派(Painite Jacobins)*5 にまでさかのぼるものであった。1850年代、チャーティズム内部において、ジョーンズは紛うことなく一貫してその伝統の信念に満ちた提唱者であった。その反植民地主義のために1848年かれは監獄に送られることになったのだが、出所後もその考えはただ深まるばかりだった。
監獄のなかからジョーンズは「新たな世界、民主主義の詩」の幾つかの節を書き始めた。その叙事詩は『ノーツ・トゥー・ザ・ピープル』の創刊号に公開され、ジョーンズの作品のなかでも最も有名なものとなった。その詩では、英国占領下のインドで革命が勃発する世界が描かれる。
人民の権利の急激なうねりは激しく打ち寄せ、
そして、セポイ兵たちは、目覚め、手に手を取り合い、
そしてついに、みずからに祖国のあることを思い出すだろう!
脱植民地革命の嵐はアフリカへと拡大し、目覚めた奴隷たちは侮蔑への報復として復讐をおこない、ハイチ革命の精神を呼び起こしていく。
燃え上がる南部の奥深くで、煙が立ちこむ。
まる4000年間くすぶり続けた激しい怒り。
歴史の気まぐれがいかなる名をあたえようとも、
ムーア人、イフリート、エチオピア、ニグロはいまだ奴隷のままだ!
…
そして、同志たちよ!かれらの復讐を確固とせよ。
かれらの背後にはオジェとルヴェルチュールがそびえたっている。
とうとうアフリカの革命は中央アメリカと南アメリカに行き渡り、反乱者たちは征服された原住民にかわって数世紀にわたるスペイン帝国の支配を転覆する。
笑えメキシコ! そして手を叩けペルー!
老モクテスマよ! 墓から抜け出せ。
再びお前たちの灯りを灯すのだ、今はなきウェスタの処女の太陽よ!
お前は見るだろう、ピサロの所業が打ち破られるのを!
ジョーンズは、急進的(ラディカル)ロンドンでの戦闘的な闘争経験から、人民憲章を求める闘いが奴隷制廃止論や反植民地主義とからみ合っており、労働者階級はグローバルで多人種的(multiracial)であることを学んだ。
しかし、1848-49年の壊滅的な敗北と、イギリスをはじめヨーロッパ各地でそれがもたらした政治的無力感によって闘争の次元は再編された。そのなかでかれは、1850年代の反動的情勢において、グローバルな革命的攻勢はヨーロッパの労働者たちによってではなく、植民地の抑圧された大衆のなかからはじまると考えたのである。
マルクスは、それまで一度もそのように反植民地主義的な観点を持った人間と密接な共同作業をおこなったことがなかった。『ノーツ』の寄稿者であり読者であったかれは、ジョーンズが書いた「新世界(New World)」や「われわれの植民地(Our Colonies)」と題されたコラムを必ず読んでいた。これらの文章で、ジョーンズはイギリス帝国主義を批判し、海外でのイギリスの支配に抗する抵抗運動を支持するよう労働者階級の読者に呼びかけていた。
こうした編集方針は、『ピープルズ・ペーパー』にも引き継がれる。
1852年5月に創刊されたこの雑誌は、『ノーツ・トゥー・ザ・ピープル』に代わってチャーティズムの主要な機関誌となった。マルクスは継続してこの新しい週刊紙の編集に関わり、ジャーナリスティックな共同制作を行った。かれは計二十五本の記事を書いたが、そのうちのいくつかは『トリビューン』記事の転載である。
『ピープルズ・ペーパー』創刊号は反植民地主義的立場を打ち出し、労働者へ訴えかけた。「われわれは、しっかりとヨーロッパの民主主義の利害を見据えてきた。それはすなわち、われわれは植民地の闘争に目を向けるということである」。植民地におけるイギリスによる支配からの解放は、いいかえれば、資本主義の中核におけるプロレタリア解放のための梃子だったのだ。
マルクスはジョーンズに何を学び、何を教えられたのだろうか。四年前の『コミュニスト宣言』でマルクスとエンゲルスは、西洋の帝国主義を、未発達の社会をブルジョア文明へと引き上げる、進歩的で有用な勢力とみなしていた。
いまやかれはそれとは正反対の意見をもつ人間と共同作業をしており、そのような状況が、かれのヘーゲル哲学の素養からすれば、いわば内在的批判とでもいえよう立場へと移行させた。すなわち相反する視点の前提そのものは受け入れ、取り込みながら、弁証法的に乗り越えるという批判である。
ジョーンズの反植民地主義がマルクスの思想に与えた弁証法的な影響の最初の徴候を、マルクスが1852年に書いた『トリビューン』の記事「チャーティスト」*6 に見いだすことができる。そのなかでかれは、スリランカにおけるイギリス統治の圧政と弾圧を非難するジョーンズのスピーチを引用している。この重要なテクストの一年後には、インドがかれらのジャーナリスト的アンテナを惹きつける。マルクスが、チャーティストの知識人コミュニティの一部となり、吸収されたことがあきらかになった。
反植民地主義という試み
1852年から1853年にかけての東インド会社の特許状の更新をめぐる議会での論戦は、〔大英帝国による〕インド支配や統治の現状をまざまざとさらけ出した。ジョーンズとマルクスは、それに促されて東方の植民地へと焦点をシフトさせた。そしてここまでの政治活動と同じように、ジャーナリズムにおいてもこの二人を切り離すことはできない。
ジョーンズはまず、先住民に対する合法化された直接的な略奪としてイギリスのインド支配を非難する一連の記事を『ピープルズ・ペーパー』に書いた。
1853年5月に発表された一連の記事でジョーンズは、インドを「東方のアイルランド」と呼んでいる。「イギリスの野蛮」たるイギリスの支配は、進歩ではなく悲惨な窮乏をもたらしたというのである。これは、帝国主義のオリエンタリズム的言説を反転させ、被植民者ではなくイギリスの支配者たちを野蛮人とみなす、チャーティスト的帝国批判の典型だった。
しかし、ジョーンズは他のチャーティストたちと違い、「新世界」で展開をみせていた視点に同調しながらさらに一歩踏み込んで、インドの独立を提唱している。
そこには、インド人兵士──セポイ(sepoys)として知られる──がイギリスの支配者たちに立ち向かい民族解放運動を主導するといった期待があった。それにつづくある記事でジョーンズは、イギリスの労働者の搾取とインド住民への植民地的な抑圧をむすびつけ、英国内での階級闘争にとってのインド独立の意義を力説している。
マルクスも同様の立場にすすんでいった。
かれによる『トリビューン』紙の記事では『コミュニスト宣言』での論調とは打って変わって、イギリス帝国主義はインドに進歩や文明化ではなく死と破壊をもたらしたと認識されている。マルクスもまたインドを「東方のアイルランド」とするアナロジーを援用しているが、このことはマルクスの思考の多重線的な発展とジョーンズとのむすびつきを示唆している。
さらに1853年8月8日付の「イギリスのインド支配の将来の結果」 *7 という有名な記事のなかで、マルクスはチャーティストによる帝国批判の修辞法(トロープ)を彷彿させる言葉遣いをもって、「ブルジョア文明のもつ深い偽善と固有の野蛮性」*8 の一例としてイギリスのインド支配を非難した。
同記事において、この新たな反植民地主義的な修辞法(レトリック)を用いながら、マルクスは、インドの解放はイギリスにおける労働者階級の反乱からも、あるいは植民地住民自身による自己解放運動からも起こりうることを認めている。
これはマルクスの思考における大きな転換であった。というのも、マルクスはここではじめて、植民地の人びと自身が革命的社会変革を主導することを想定したシナリオを示しているからである。かれはジョーンズと同一の立場にたったのだ。
1854年、マルクスはジョーンズによる草の根の組織活動を支援し、この活動によってマンチェスターで国内の労働者評議会──いわゆる労働議会(Labour Parliament)である──が開催される。
1856年4月、マルクスは『ピープルズ・ペーパー』の四周年を記念するために開かれた集会に参加し、オープニングスピーチをおこなった *9 。マルクスがエンゲルスにあかしているように、そのスピーチの目的は、チャーティスト運動のメンバーであり支援者としての自身の立場を強化することにあった。それと同じ活動家精神でもって、マルクスは同年、路上に繰り出して、懲役から戻ってきたチャーティスト、ジョン・フロストを支援するデモに参加している。
このように、反植民地的反乱がインドでもはじまろうとしていたとき、チャーティストの活動は、依然としてマルクスの生涯でも重要な位置を占めていたのである。
インドの亡霊
1857年の春、決起したセポイ兵によって主導されたインドの植民地軍の反乱の消息が次第にイギリスにも伝わりはじめた。マルクスとジョーンズは、すぐにこの出来事に関心をもった。四年前には理論上の推測にすぎなかったものがいまや実体をもった可能性として眼前に現れたのである。かれらは躊躇することなくそれを受け入れた。
イギリスの報道が反乱を中傷し嘲笑するなか、マルクスとジョーンズの報告は分岐をみせつつも同一の結論にいたっている。
当初より、かれらはインド住民の苦しみに共感しイギリスの植民地支配を非難すると同時に、この暴動は必然的に広範にわたる民族解放運動に展開すると指摘した。かれらはまた、被植民者であるインド人の自律的な活動と政治的合理性が一連の出来事の方向性を形作る上で決定的な要因であると主張した。
そしてマルクスはジョーンズと同様にこの蜂起をヨーロッパに取り憑いた新たな亡霊であるとし、これを労働者の新たな攻勢のきっかけを切り拓きうる危機と捉えた。マルクスは、エンゲルス宛の手紙で、「インドはいまやわれわれの最良の同盟者である」と熱を込めて書いている *10 。

1857年の夏から秋にかけてジョーンズは、チャーティスト的な応報主義(retributivism)の比喩を用いてこの蜂起を把握し、文章を書いた。
応報主義とは、すなわち、歴史を動かすのは内在的な正義の過程であって、歴史的な誤謬は応報によって修正されるという宗教的メシアニズムから持ち込まれた考えである。ジョーンズは、1857年8月4日付の記事で「各国家の不正は必ずや応報に見舞われる」とし、インドの蜂起を「歴史の均衡を補正する顕著な例である」としている。そして〔歴史の均衡を補正する〕「この応報の担い手(エージェンシー)」を、ポーランドやハンガリー、イタリアの解放運動と並べてみせるのである。
その一週間後マルクスは『トリビューン』紙に「インドの反乱」を書くのだが、そのなかでかれは、インドの蜂起を、弁証法的で変革的な社会的動力を有しており西ヨーロッパの経験に並行していると認めている──それは東方諸国に関するかれの従来の立場を完全に逆転させたものだった。
マルクスは、つぎのように述べている。
人間の歴史には、応報ともいうべきものがある。この応報の武器が被害者によってではなく、加害者によって鍛えあげられるのが、歴史的応報の法則である。
フランスの君主制にくわえられた最初の打撃は、小農からではなくて、貴族からやってきた。インドの反乱を始めたものは、イギリス人から苦しめられ、辱められ、身の皮まで剥ぎとられたインドのライヤトではなくて、イギリス人から衣食を受け、かわいがられ、肥えふとらされ、甘やかされたセポイであった。*11
このマルクスの散文のなかには、ジョーンズの表現が驚くほど染み渡っているが、これはインドの蜂起の展開をみつめるマルクスの思考にチャーティズムが影響を与えつづけていたことを示唆するものである。
あきらかにイギリス帝国の周辺での反植民地主義的な反乱は、マルクスをして自身の立場を改めさせ、かれの唯物論的な歴史概念のなかに植民地主義を統合するよう駆り立てたのである。
だが、マルクスは、この一歩をさらに推し進めていくために、ジョーンズに手がかりを求めたというのが実態に近いだろう。マルクスがこの長年の同志のテキストにみいだしたのは、帝国の支配を混乱に陥れつつある現在進行中の反植民地運動を射程に入れることで、資本主義の中核国におけるブルジョア対プロレタリアートの対立という通常の二項対立を乗り越えようとする議論であった。
すでにジョーンズは、労働者の選挙権を勝ち取るため、ブルジョアのうちの急進的陣営との選挙同盟を模索しはじめていた。たしかにマルクスはその動きに失望し、一時的にではあるが、1858年にジョーンズと決裂した。しかし、この幻滅は政治的なものであり、インドの反乱についてのジャーナリズム活動の相同性が示唆するように、ジョーンズの著作や社会批評に対するマルクスの評価が損なわれることはなかった。
ロンドンのマルクスにとって、1850年代は、チャーティストの十年であった。それはマルクスがジョーンズとの共同関係から、そしてより一般的にいえばチャーティズム運動のなかの経験から学びを得た十年であった。
この十年が終わったとき、マルクスはジョーンズの政治的立場に幻滅していたかもしれないが、知的には変貌を遂げていた。最も重要なのは、ジョーンズのおかげでマルクスが、以後長きにわたってかれの政治的プロジェクトの中核を構成しつづけることになる反植民地の道を確固として歩みはじめたことである。
注
- フランスはシャルル10世治世下の1830年にアルジェリア侵略を開始し、植民地支配に乗り出すが、アラブ人首長アブド・アルカーディルらによる武力抵抗が全国各地で起こり、47年まで戦闘がつづいた。 ↩︎
- カリブ海に位置するグアドループは、1493年のコロンブスによる発見以降、スペインの領地となった。しかし、1635年にフランス人が同地を占領して以降、入植が進み、奴隷貿易や奴隷制による支配がおこなわれた。その後フランスとイギリスとの間で領有をめぐる争いが幾度も繰り広げられるなか、1794年にフランス革命によって奴隷制が一度は廃止されるが、1802年ナポレオンのもとで復活すると、激しい反乱が勃発した。最終的にグアドループは1815年のパリ条約でフランスの植民地となり、奴隷制は1848年に廃止された。 ↩︎
- ウィリアム・カッフェイ(1788-1870)は、ロンドンで活動した黒人チャーティスト。1834年洋服屋組合のストライキにかかわることから活動家人生を始めると、39年チャーティズムの運動に加わる。1842年に全国憲章協会の幹部に選出されるなど、ロンドンのチャーティストの中心人物となっていったカッフェイについて、当時の新聞は運動を揶揄して「黒人とかれの党」と書きつけもした。48年に武装蜂起の計画が露見しオーストラリアはタスマニアに追放される。かれも含めて政治犯は56年に恩赦を受けるも、カッフェイはタスマニアに残り、それ以降も植民地での主従法の改正に取り組むなど、活動をつづけた。 ↩︎
- レヴェラーズはピューリタン革命時の左翼党派を指し、しばしば「平等派」あるいは「水平派」と訳される。当時、独裁を敷いていたクロムウェルに対し、普通選挙による議会の実現などを通して人民の政治的平等を主張した1647年の「人民協約」をまとめ、共和政の樹立を訴えた。一方でディガーズは、レヴェラーズのなかの最左翼に位置する党派を指す。私有財産の否定や土地の平等な配分を訴えるなど、レヴェラーズの主張を推し進めたことから「真正水平派True Levellers」とも呼ばれた。 ↩︎
- 『コモン・センス』や『人間の権利』の著者であるトマス・ペインを信奉するジャコバン派のことを指すものと思われる。アメリカの独立革命やフランス革命の理論的な支柱となったペインは、革命政府に招かれてフランス議会の議員となり、ジロンド派に属する立場ではあったものの、のちにジロンド派と対立するジャコバン派の面々とも交流をもっており、ここでの「ペイン主義ジャコバン派」もその意味で理解可能である。しかしその後は、死刑全般にたいする批判ゆえにルイ16世の処刑に反対したことなどでジャコバン派からの迫害を受けた。死後ペインの思想はとりわけ「諸国民の春」と呼ばれた1848年革命に大きな影響を与えたとされる。ペインについては、同じくウェブ版『ジャコバン』誌に掲載されたショーン・モナハンの記事を参照。 ↩︎
- 『マルクス・エンゲルス全集』(大内兵衛・細川嘉六監訳、大月書店)第8巻、334ー343頁。 ↩︎
- 『マルクス・エンゲルス全集』第9巻、212-218頁。 ↩︎
- 同上、217頁。 ↩︎
- 『マルクス・エンゲルス全集』第12巻、3-4頁。 ↩︎
- 『マルクス・エンゲルス全集』第29巻、206頁。 ↩︎
- 『マルクス・エンゲルス全集』第12巻、271頁。 ↩︎
著者
ティエリー・ドラポー(Thierry Drapeau)
ニューヨーク大学でPh.Dを取得後、現在、ケベック大学ウタウエ校の講師(専門は労使関係)。初の単著として、The Long First International: Workers of the Atlantic World Unite for Emancipation, 1714-1864 を準備中。
訳者
大畑凜(おおはた りん)大阪府立大学大学院博士課程、社会思想・戦後日本思想
森田和樹(もりた かずき)同志社大学大学院社会学研究科博士課程、歴史社会学[朝鮮現代史]

![Read more about the article 【連載】誰がパリ五輪に抵抗しているのか?[第4回]後編/佐々木夏子](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2022/12/スクリーンショット-2022-12-15-18.00.00.png)
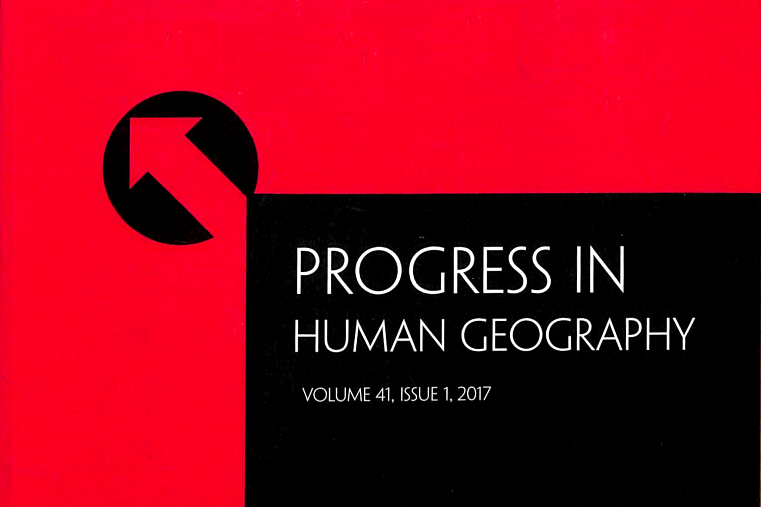


![Read more about the article 人間狩り・奴隷制・国家なき社会[第2回]/酒井隆史×中村隆之×平田周](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2022/06/img_9784750352305_1-768x514.jpg)