【連載/第2回】
誰がパリ五輪に抵抗しているのか ?
Qui luttent contre les Jeux Olympiques 2024 de Paris ?
佐々木夏子
「メディア」
1.
2021年12月26日に放送されたNHK BS 1スペシャル「河瀬直美が見つめた東京五輪」の捏造事件について、本記事にアクセスされた読者であればご存知ない方はおられないだろう。本連載の「序」で述べたとおり、東京五輪反対デモには最盛期でも(パンデミック禍という状況もあって)1000人ほどしか集まっていない。日本国内の認知度も決して高くはなかったはずである。皮肉にもこの捏造事件が、東京五輪開催への反対を表明するため街頭に繰り出した人々の存在を広く知らしめることになった。この時期になってこんな形で自分たちの認知度が高まろうとは、当事者は遺憾という言葉では足りないほど頭に来ていることだろう。彼ら彼女らは札幌への2030年冬季五輪招致に反対する活動1注1:「2030札幌冬季五輪を止めよう! 招致に反対する全国・全世界共同アピール」:http://www.2020okotowa.link/2021/12/17/2030sapporo_nolympics_statement/も行なっているので、次につながることを願うばかりだ。
この事件への反響は大きく、東京五輪と反対デモへの温度を問わず、さまざまな識者がコメントを出している。以下に引用するのは、1月12日に東京新聞に掲載された斎藤美奈子のものである。
お粗末な話である。不確かな内容に基づいてデモが反社会的行動のような誤解を与えるなど言語道断。捏造に近い。問題はNHKがなぜこんな失態をやらかしたかだ。
今度の五輪は最初から捏造ではじまっている。安倍元首相の「アンダーコントロール」発言である。(…)もはや負の記憶しかない東京五輪。そのイメージを払拭したいという願望が番組を暴走させたのであろう。反対デモは負の五輪をまさに象徴するできごとだからだ。
同じ番組で「五輪を招致したのは私たち」「だからあなたも私も問われる」と河瀬監督は発言した。まるで一億総懺悔。最後まで捏造だったといわれぬよう、NHKの轍を映画が踏まないことを祈る2注2:東京新聞2022年1月25日、第25面。「捏造を呼ぶ五輪」斎藤美奈子。
このコラムは早いタイミングに限られた紙数で、NHKの捏造事件がいかに「言語道断」であるかを強調するものなので、あまり厳しいことを言っても仕方ないかもしれない。しかしこの文中には少なくとも二つの看過できない問題がある。
最後の一文で斎藤が言及しているのは、河瀬直美が監督を務める東京五輪の公式記録映画のことである。この期に及んで公式記録映画が「NHKの轍を」「踏まないことを祈る」のは、この件における河瀬の責任を問わない身振りだと言っても過言ではないだろう。
第二に斎藤は、「問題はNHKがなぜこんな失態をやらかしたかだ」と適切な問いを立てながら「(「負の」)イメージを払拭したいという願望が番組を暴走させたのであろう」としか述べていない。これでは答えになっていない。問題は、日本国居住者から半ば強制的に受信料を徴収する「みなさまのNHK」が、なぜ五輪の「イメージを払拭したいという願望」を抱くのかだ。一国の公共放送局が、国際オリンピック委員会(IOC)というスイスの一非営利団体主催のイベントについた悪い「イメージを払拭」したいと願うのは、なぜなのか。
まず指摘できるのは、籾井勝人がNHK会長に就任して以降、NHKという組織が抱えている問題である。「国境なき記者団」が発表する「世界報道自由度ランキング」において、日本は2012年まで報道の自由度が(そこそこ)高い国、と評価されていた。しかし籾井がNHK会長に就任する前年の2013年に一気に順位を下げ、2016年と2017年には72位にまで落ちている。記者クラブや天皇制など、昨日今日生まれたわけではない日本独自の制度が報道の自由に貢献していないことは間違いない。けれども2010年代後半の急落の大きな要因には安倍晋三と籾井勝人の存在を挙げないわけにはいかない。「河瀬直美事件」が論じられる中、籾井がNHKに残した負の遺産を指摘する声は多い。
けれどもより構造的かつ本質的なのは、NHKをはじめとするテレビ局がIOCに放映権料を支払う利害関係者である、ということである。NHKと一般社団法人日本民間放送連盟は、世界的なスポーツイベントの際にジャパンコンソーシアムを構成し、すべての主要テレビ局が大会を放送する仕組みになっている。これは日本の主要テレビ局が一つ残らず、いわゆる「横並び」で巨大スポーツ大会の利害関係者となることを意味する。自国開催のオリンピックともなれば、その利権構造はますます強固なものとなる(ジャパンコンソーシアムが払った2018-2020年のオリンピック放映権料は、前後の大会よりも2-300億円高い660億円となっている)。オリンピックに批判的な報道を行い視聴者のオリンピック離れを加速させることが、IOCから放映権を購入しているテレビ局各社の利益に反することは言うまでもない。開会式など重要な放送を担うNHKの利権は、ジャパンコンソーシアム加盟各社の中でも突出して巨大なものとなっている。
そもそも近代スポーツは、近代メディアなくして現在の形とはなっていない。1956年メルボルンオリンピックに参加後、研究者となったフランスのスポーツ社会学者、レイモン・トマはこう述べている。
ある人たちにとって、スポーツとは本質的にスペクタクルである。より正確を期すると、マススペクタクルである。中世の馬上槍試合はすでにスペクタクルであった。けれども近代の技術によって初めて、観客の輪の際限ない拡張が可能となったのである。新聞とラジオはスポーツの発展において確かに重要な役割をになった。けれどもスポーツが世界的に広がったのは、テレビのおかげである3注3:Raymond Thomas, Le sport et les médias, 1993, Édititions Vigot, p.19.。
東京五輪の無観客開催は、スタジアムに集う観客ではなく「近代の技術によって」際限なく拡張された「観客の輪」によってオリンピック経済が回っており、その経済規模が巨大であるため中止が不可能であることを見せつけた。そして過去に「スポーツの発展において確かに重要な役割をになった」メディアである「新聞とラジオ」も、この経済のおこぼれに与る構造となっている。
日本のように大手五大新聞社(朝日・読売・毎日・日経・産経)すべてが大会のスポンサーとなった事態は過去大会に先例がなく(さらに北海道新聞もここに加わる)、「世界ではありえない」と言われることが多い。確かにその通りだ。けれども新聞社が正々堂々と、自分達はオリンピックの利害関係者であると公に認めた、と(あえて)評価することもできる。メディアはオリンピック経済の担い手であり、大量のスポーツ記者の雇用主である。そうである以上、批判的な報道をするモチベーションなど元々限りなく低い。これはオリンピック開催国に普遍的に観察される現象である。イギリスのスポーツ社会学者、ジョン・ホーンは「(イギリスの)地方紙ならびに全国紙、そして放送局が2012年ロンドン大会にまつわる否定的な報道を行うことはほとんどなかった」と述べている4注4:John Horne, ‘Sports mega-events: mass media and symbolic contestation’ in Sport, Media and Mega-Events, ed. by Lawrence A. Wenner and Andrew C. Billings, 2017, Routledge, p.28.。それならいっそ公平な報道機関の体裁を取り繕われるよりも、大会スポンサーとなって立場を鮮明にしてくれた方がすっきりする、と言えなくはないか。
ちなみに2030年冬季五輪の招致を目指して札幌商工会議所が設立した「冬季オリンピック・パラリンピック札幌招致期成会」の顧問には新聞社や放送局などメディア11社の社長・支社長が名を連ねており5注5:http://sapporo2030.jp/about/officer.html、この癒着公認路線は日本において現在も継続中である。
メディアとオリンピックの癒着公認に一定の評価を与えることは、悪しき“加速主義”のそしりを免れないかもしれない。しかしたとえスポンサーとならなくても、招致期成会の役員に就任しなくとも、マスメディアがオリンピック経済の担い手であり、スポーツ担当記者を雇用している事実は変わらない。本稿執筆時点で、2024年パリ五輪のスポンサーとなっているフランスのメディア企業はない。恐らく今後も出て来ないだろう。しかしその一点をもってして、日本と異なりフランスのメディアは自由に自国開催のオリンピックを批判できているはず、などと想定しては早計である。
日本のメディアによる東京大会の扱いと、フランスのメディアによるパリ大会の扱いには、明らかに違いがある。そこに日本とフランスの違い、という側面がないわけではない。しかしそれ以上に大きいのは、以下に述べるような、2020年大会までとそれ以後の大会を画することになるような違いではないだろうか。
2028年ロサンゼルス五輪への反対活動を展開しているNOlympics LA6注6:https://nolympicsla.com/のメンバーと私は定期的にZoom会議をしているのだが、大西洋とアメリカ大陸を跨いで私たちは次の見解を共有している。
東京五輪はマスメディアが総力を上げて一大キャンペーンをはる最後の大会となるだろう、と。ロサンゼルスやブリスベン(32年大会)の場合、開催の11年前に決定してしまったので、鬼も何度笑わなければならないものか途方に暮れてしまうほど先の話で盛り上げようもない、という新事情もある(いったいどれほどのアメリカ人がLA 2028について知っているだろう?)。けれども従来通り7年前の開催地決定となった24年パリ、26年ミラノ・コルティナと欧州で続く大会を観察するだけでも、以下の事実に気づかずにいることは難しい。オリンピックはロープロファイルを志向し始めている、と。
東京五輪では電通が大活躍してスポンサー企業が68社も集まり、オリンピック関連広告が公共の電波や空間を埋め尽くした。その後COVID-19のゴタゴタで、開催を強行するのか否かが国民的関心事となった。以降の大会が開催国でこれほどまでの関心を集めることはもはやないだろう。最大の要因は、メディア環境の変化である。
インターネットが日常生活を支えるインフラとなって20年以上経ち、マスメディアの黄金期は終わっている。そしてオリンピックはマスメディアの落とし子である。アメリカでは東京五輪の視聴率は大きく下がり、リオ大会から42%減となっただけでなく、NBCが独占放送を開始した1988年以降で最低の数字となっている。その根本的な原因を、オリンピックの取り分となるアテンションのパイの減少に求めることは至って自然であろう。NetflixやAmazonプライムがカタログを充実させ、YouTubeが収益モデルを確立させている時代に、連日1500万人のアメリカ人がNBCにチャンネルを合わせたというのは凄いことなのではないか、とその底力を評価する声もある7注7:「米NBCの五輪中継視聴率は「惨敗」だったのか?」https://www.yomiuri.co.jp/world/nieman/20210908-OYT8T50004/
。けれども大きな流れとして、コンテンツの供給が豊富となり、アテンションが希少となる傾向に歯止めがかかる気配はない。
こうした中、自国開催を控えている各国のマスメディアは躍起になって盛り上げようとする戦略をとっていない。フランス・テレビジョン(フランスの公共放送局)が1924年パリ五輪についての大河ドラマを制作する、という話は全く出ていない8注8:日本では2019年にNHKが『いだてん』という大河ドラマを放送している。1992年アルベールビル冬季五輪を舞台に『トリコロールソウル』などといった映画が作られることも、まず考えられない9注9:日本では、長野冬季五輪のテストジャンパーを主役にした『ヒノマルソウル』という映画が2021年に公開されている。。広告やメディア業界だけでなくパリ五輪組織委員会内部でも、オリンピックは準備段階では必ず批判されるが、開催されて自国の選手がメダルを獲得すれば盛り上がる、という知見は共有されている10注10:2021年10月12日、パリ政治学院でのカンファレンス後に組織委の広報担当、ミカエル・アロイソが筆者たちとの懇談中に披露した見解。カンファレンスの模様は以下で視聴可能。https://www.sciencespo.fr/evenements/?event=les-jeux-de-2024-enjeux-perspectives-controverses。批判ムードが上回っている、と主催者が判断しているタイミングで、わざわざ派手なキャンペーンが打たれることはないだろう。
一方には「ネット社会」における(特に若年層の)オリンピックへの関心低下、他方には批判の蓄積による開催候補都市の減少、という性質の異なる困難がある。端的に「オリンピックはオワコン」という評価がある中、どうキャンペーンを打ったらいいか、IOCや組織委も試行錯誤しているのが現状ではなかろうか。2022年初頭現在、2年後にパリで五輪が開催されること自体フランス国外ではほとんど知られていないようだが11注11:NOlympics LAのメンバーが筆者にそう語った他に、根拠となるデータなどは存在していない。、このまま露出を抑え続け注目度が低いままならチケットが売れず、視聴率も振るわず、興行として失敗する可能性は十分ありうる。スポンサー探しの難航や、18万ユーロという経費を理由に聖火リレーの受け入れを拒否する県(ヴォージュ県、ムルト=エ=モゼル県、ローヌ県など)が続出している事態に、その兆しはすでに現れているかもしれない12注12:https://www.bfmtv.com/lyon/jo-2024-trop-chere-la-flamme-olympique-ne-passera-pas-par-le-rhone_AN-202202250556.html。
問題は、パリ五輪はメディア展開こそ地味になっているものの、大会規模は東京までとそれほど変わっていない、ということだ。種目数も、参加選手数も東京大会と比べて増えてこそいないが、目立って減ってもいない。ロープロファイル路線に合わせて大会規模を縮小し、競技会場を減らし、経費を抑える、ということにはなっていないのである。そして「興行として失敗」した場合、運営費の穴を埋めるのにはフランス人の税金が使われる。
2.
ここまで日本のメディアによる東京五輪の扱いと、フランスのメディアによるパリ五輪の扱いには量的な差がある、と述べてきた。しかし質的な違いはあまり見られない。メディアがオリンピック経済の担い手である構造はどの開催国でも同じであり、差があるとしたら程度のそれにとどまる。
フランスにはジャパン・コンソーシアムのようなものはない。オリンピックやサッカーW杯といったメガイベントの放映権を購入できるテレビ局は限られているので、民放最大手のTF1、有料放送局最大手のカナル・プリュス、公営放送局のフランス・テレビジョンのいずれかあるいは複数が放送するパターンが多い。
パリ五輪の開催が決定した2017年以降はオリンピックが国策となったので、2022年北京大会、2024年パリ大会については公共放送のフランス・テレビジョンとラジオ・フランスが独占放送権を獲得している(放映権料は非公開)。このことは、フランス最大13注13:フランステレビジョンの収益は約30億ユーロで、TF1グループの収益は約20億ユーロ。にしてもっとも公共性の高い放送局が、オリンピックに批判的な放送をほとんど行わなくなることを意味する。ちなみにフランス・テレビジョンもラジオ・フランスも個性の異なる複数のチャンネルを有しており、総合すると日本におけるNHKよりもはるかに大きなプレゼンスを誇っている。
一例を挙げよう。COVID-19発生後、東京五輪の延期や中止についてIOC会長、トーマス・バッハから重要な発言を引き出してきたのは、イギリスにおけるフランス・テレビジョン的立場にある英国放送協会(BBC)である。フランス・テレビジョンが東京五輪について、バッハ会長やIOCの副会長たちに突っこんだ質問をしたことは一度もないのである。
BBCとフランス・テレビジョンの国際的なプレゼンスが比較にならないのは確かである。そのため国際イベントであるオリンピックの最高責任者へのインタビューをBBCが行い、全世界に発信するのは理に適っているだろう。しかしフランスは何と言っても次大会開催国である上、バッハ会長の任期はパリ大会まで続くのである。バッハ会長がどういう発想の持ち主で、どういう発言を行い、どういう行動に出る人物なのか、報道する義務がフランスのメディアにはあるのではないか。
本連載の「序」で、私は何の裏付けもなく「トーマス・バッハの顔と名前が一致するフランス人なんて1%もいないはず」と記している。データの裏付けがないから控え目に書かざるをえなかったが、1%は相当多めの見積りで0.1%と書こうか迷ったほどだった。この「ぼったくり男爵」の人となりがフランス人に全く知られていないというのは、フランスの報道の自由における決して小さくない問題なはずである。
フランスのメディアにおけるIOC批判の不在は、北京五輪開催中にも際立っていた。アメリカのCNNでは、ゴールデンタイムのオリンピック中継を1992年から2016年まで担当してきた元NBCのスポーツ記者、ボブ・コスタスが「IOCが中国に戻ったことは、あらゆる軽蔑、嫌悪に値します(…)IOCはこのことについて全く恥じていないのです」と発言している14注14:https://twitter.com/JulesBoykoff/status/1491854275374460934。またヨハン・ハリというイギリスのジャーナリストが「(IOCは)世界でもっとも醜悪かつ腐敗した組織の一つだ(…)いったん解体してゼロからやり直すべき、胸糞悪い組織だ」とテレビ番組で発言したのち会場から大きな拍手が沸き起こった様子を、アメリカの政治学者、ジュールズ・ボイコフがツイートしている15注15:https://twitter.com/JulesBoykoff/status/1491987527334445061。フランス・テレビジョンではまず考えられない光景だ。雪のない北京五輪や中国当局を批判する報道は、確かにフランスにもいくらでもある。しかしIOCの責任まで問われることはまずない。フランス語メディアによるIOC批判を探すと、カナダ発のもの16注16:たとえば以下など。https://www.lapresse.ca/sports/chroniques/2022-02-04/jeux-olympiques/le-cio-n-est-pas-neutre-il-est-complice.phpにたどり着いてしまうのである。
答えの出ない問いを立ててみよう。「トーマス・バッハの顔と名前が一致するフランス人なんて1%もいない」のだとしたら、それは次の大会がパリだからこそ、なのではないか? もしフランスが次期夏季五輪の開催国でなければ、フランス・テレビジョンを含むフランスのメディアは、東京五輪や北京五輪にまつわるIOC会長の問題発言をもっと報道したのではないか? バッハ会長やIOCについてフランス人が知識を得ることは、自国開催オリンピックという一大ビジネスチャンスを控えているフランスのメディア産業の利益を損ねる、という判断があるのではないか?
本稿の力量では陰謀論に陥ることなくこうした疑問を追求することはできない。そのため甚だ不十分ではあるが、以下の傍証を確認することで代わりとしたい。
2021年末に出版された吉見俊哉他による『検証 コロナと五輪 変われぬ日本の失敗連鎖』(河出書房新社)は、マスメディア分析にかなりの紙数を割いており、第5章はまるまる海外メディア分析に充てられている。同章「海外はどう見たか パンデミックのなかの東京五輪」は欧米・韓国・中国の3部構成で、クレジットは安ウンビョル/藩夢斐/サム・ホールデンとなっている。欧米メディアの分析はおそらく米国出身のサム・ホールデンによるものだ、と仮定して以下の論を進めていく。
ホールデンは『ニューヨークタイムズ』や『ガーディアン』など進歩派やリベラルに分類される英語メディアから、『ウォール・ストリートジャーナル』や『エコノミスト』まで、私もリアルタイムで読んでいた東京五輪ないしはオリンピックそのものに対する批判記事を手際よく整理している。そうした中で目を引くのが、ドイツの『デア・シュピーゲル』による批判記事の引用である。この章において言及される非英語圏のメディアは、実はこれだけなのだ。これがあるからこの節のタイトルをかろうじて(「英語圏」ではなく)「欧米から見た東京五輪」とできている、と言える。
本書は吉見俊哉が自分の研究室の院生と共同で執筆しており、分析対象の選択はおそらく「院生がカバーできる言語」というプラクティカルな要因に帰することができるものだと思う。次大会開催国であるフランスのメディアは「あえて」分析から外されたのではなく、「たまたまフランス語ができる院生がいなかった」といったところだろう。しかしそれでもこう思わずにはいられない。東京大学大学院情報学環ともあれば、本気で次大会開催国のメディアの分析を加えたければ、フランス語のできる院生を探し出すことなどわけなかったのではなかろうか、と。
実は、ホールデンが担当している「欧米から見た東京五輪」の節は、フランスのメディアの分析を加えると大きく書き換える必要が出てくるのである。同章の末尾近くに章全体をまとめる形でこう書かれている。
欧米の主要メディアでは、パンデミックという前例のない危機に遭遇し揺らぐようになった東京での二度目の五輪が、差別や格差など、日本社会の構造的問題や近代オリンピックそのものに対する根本的な批判を深めるきっかけとなっていった。韓国の主要紙では、コロナ禍以前から取り上げられてきた「まだ収束していない原発事故」という安全問題が重視される一方、「我々が過去に追いつこうとした先進国の日本はもう存在しない」という競争的な言説が繰り返された。一方、中国の報道ではあまり批判的な言説は目立たず、むしろ好意的な評価が主流をなしている。そのポジティブな報道は、二〇二二年に開催される北京冬季五輪の予定通りの開催を意識したもので、五輪という「夢」そのものを損なうまいという中国当局の意思が示されている17注17:吉見俊哉編著『検証 コロナと五輪 変われぬ日本の失敗連鎖』2021年、河出書房新社、pp.230-231。。
もしこの章にフランスのメディアの分析が加えられていたならば、このようなストーリーテリングは不可能となる。紛れもなく「欧米の主要メディア」の一翼を担っている『ル・モンド』他フランスのメディアが、「近代オリンピックそのものに対する根本的な批判を深める」ようなことはついぞなかった、と加えることが絶対に必要となる。
それどころか『ル・モンド』は東京五輪が延期になってしまった2020年の夏に、「オリンピック架空ガゼット(La gazette virtuelle des JO)」というタイトルで全15回におよぶ、つまり本来の大会期間中に連日「もし東京五輪が開催されていたなら」という主旨の連載さえしていたのである。同連載の最初の数回は以下の同じリード文で始まっていた。
Covid-19によって中止となったオリンピック。けれども『ル・モンド』はそんなことは気にせず、まるで大会が開催されているかのような経験を読者のみなさまにお届けします。プログラムの内容は、架空試合、アスリートとの深い話、そしてオリンピックこぼれ話など18注18:https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/07/25/la-gazette-virtuelle-des-jo-alaphilippe-victime-d-une-conspiration-tir-a-l-arc-et-erreur-d-adresse-fatale_6047254_3242.html。
ここまでくれば『ル・モンド』がパリ五輪のスポンサーとなってないことなど大した問題ではない。私も世界中のメディアをチェックできているわけではないが、いわゆる「欧米の主要メディア」でここまでやった新聞社が他にあるとは思えない。こうした「ポジティブな報道」は、2024「年に開催される」パリ「五輪の予定通りの開催を意識したもので、五輪という『夢』そのものを損なうまいという」、フランス当局というよりは新聞社の意思を示すものである。4年後にパリ大会を控えていなくても『ル・モンド』はここまでやっただろうか? 安ウンビョル/藩夢斐/サム・ホールデンが分析にフランスを加えていれば、「欧米」と「中国」の間の差よりも、次大会開催国が有する共通点の方が際立つことを炙り出せたはずなのだ。
東京五輪に先立つリオ大会にまつわる問題については、『ル・モンド』は丁寧な報道をしていたのである。オリンピックパーク建設のために破壊されたファベーラ、ヴィラ・アウトドロモ19注19:https://www.lemonde.fr/jeux-olympiques-rio-2016/article/2016/08/16/jo-2016-vila-autodromo-et-ses-rebelles-des-jeux_4983536_4910444.html。グアナバラ湾の汚染20注20:https://www.lemonde.fr/jeux-olympiques-rio-2016/article/2016/07/29/a-rio-les-jeux-sont-mal-faits_4976068_4910444.html。そしてもちろん、蜂起寸前となったデモ21注21:https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/07/07/bresil-manifestation-a-rio-contre-les-jeux-olympiques_4965168_3222.html。もちろん同紙が東京五輪についてネガティブな報道をまったくしなかったわけではなく、週末別冊版(M Le mag)では東京の反五輪グループ「反五輪の会」や、「オリンピック災害おことわり連絡会」こと「おことわリンク」のメンバーである哲学者の鵜飼哲が取材されたこともある22注22:https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/05/31/sauvez-des-vies-plutot-que-les-jeux-pour-les-japonais-les-jo-n-en-valent-pas-la-chandelle_6082129_4500055.html。しかしそうした記事は『検証 コロナと五輪 変われぬ日本の失敗連鎖』でサム・ホールデンが紹介した英語圏のメディアのものに比べて質量ともに大きく劣り、「近代オリンピックそのものに対する根本的な批判」には程遠いものとなっている。
フランスには他にも『リベラシオン』という、ジャン=ポール・サルトルが創刊に関わったことで有名な新聞がある。「《私たちの声明は、IOCの暴走を止めることを目的としている》と、痛烈な批判を展開している」記事を『リベラシオン』が掲載した、と『文春オンライン』が報じたことを覚えておられる読者もいるかもしれない23注23:https://bunshun.jp/articles/-/46579。
しかし『リベラシオン』の東京特派員、西村カリンがツイートした通り、これは「リベラシオンの記者が書いた記事ではなく、社説でもない、リベラシオン紙が掲載した数人の政治家とアクティビストが書いたオピニオン記事」24注24:https://twitter.com/karyn_nishi/status/1411656027326480389で、英語圏で言われる「オプエド記事」あるいは「ゲスト・エッセイ」に相当するものだ。文春による「誤報」のおかげで、この記事は日本で多少話題になったようだが、フランスでは全く話題にならなかった。署名者の一人である私が言うのだから間違いない。
この記事が出た6月23日、オリンピックプール建設で破壊されることになるオーベルヴィリエの「守るべき菜園(Jardins à défendre)」の占拠闘争現場で、私は一日中反オリンピック関連イベント25注25:https://paris-luttes.info/le-23-juin-journee-noympique-aux-15139をしていたのだが、「『リベ』の記事、読んだよ」と言ってくれる人はその日にも、その後にもついぞ現れることはなかった。そして『リベラシオン』がこの記事を超える「近代オリンピックそのものに対する根本的な批判」を出すこともついになかったのである。
3.
ここまで読んで、フランスのメディアがそこまで公平性を欠いているとは思えない、と眉に唾をつけておられる読者もいらっしゃるかもしれない。しかしNHKの「河瀬直美事件」が構造的な問題(メディアがオリンピックの利害関係者であること)と、個別の問題(籾井勝人)の複合を背景に生まれているように、フランスのマスメディアが置かれている固有の事情も存在する。
「国境なき記者団」が発表する「世界報道自由度ランキング」において、この組織の本拠地であるフランスは30〜40位台をウロウロするあまりパッとしない順位となっている。最新の2021年のランキングでは34位となっており、このような説明がされている。
編集の独立性は引き続き微妙な問題である。なぜならメディアの所有権が集中し、経済の他の領域に利害関係を持つビジネス集団に報道機関が統合される傾向にあるからだ。こうした状況は利害の対立を助長し、メディア不信を生んでいる26注26:https://rsf.org/en/france。
メディア研究者でも何でもない私に可能な比較対象範囲は限定的なものとなるが、アメリカ・イギリス・日本と比べると、この「メディア所有権が集中し、報道機関が経済の他の領域に利害関係を持つビジネス集団に統合される傾向」は明白にフランス固有のものとなっている。
インターネットの普及によってマスメディアはどの国でも苦境に立たされることになったが、対応には日米英仏の四カ国でかなり大きな違いが見られる。たとえば「不動産屋が新聞を発行している」と揶揄される朝日新聞は、不動産事業の安定利益がメディア・コンテンツ事業を下支えする構造となっている。こんな会社を新聞社と呼べるのか、という厳しい批判もあるが、ともあれ「経済の他の領域に利害関係を持つ」外部資本に頼らずにいられる、というのは大きな利点である。
英語圏の有力メディアにいたっては、事実上の国際共通語の使用を武器にペイウォールのビジネスモデルを確立することに成功した。この過程で米『ニューヨークタイムズ』の劇的なV字回復が果たした貢献が大きいことはよく知られている。また読者からの信頼性の高い英『ガーディアン』のように、寄付モデルによって収益を上げる例もある。
フランスの新聞社の場合、日本の新聞社のように事業成長期に不動産投資をしてきたわけでもなければ、英米の新聞社のように世界中の読者をあてにした収益モデルを確立することもできなかった。そういうわけでフランスの名高い新聞や雑誌は、「経済の他の領域に利害関係を持つビジネス集団」に次々と買収されていったのである。
現在、フランスの代表的なメディア所有者には以下の人物が挙げられる。

壮観である。フランスの主だったメディアは、いくつかの貴重な例外をのぞき、通信成金か、武器商人か、旧植民地で現地人を搾取する一族か、コンプレックスを刺激するマーケティングによって高級ブランド品を売りつける高齢男性によって牛耳られているのである。
もちろんこの状況に危機感を抱いているジャーナリストは少なくない。たとえば『ル・モンド・ディプロマティーク』はGitHubで公開されているデータ27注27:https://github.com/mdiplo/Medias_francaisを元に「フランスのメディア:誰が何を所有しているか」28注28:https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPAというページを作成し、随時更新している。しかしこうした努力があっても、ここまでの惨状になっているとは、日常的にマスメディアに接しているフランス人の間で必ずしも広く知られていないのが現状である。
けれどもブルターニュ出身の熱烈なカトリック29注29:現代フランス社会で「熱烈なカトリック」という形容詞は、「どうしようもなく反動的」のほぼ同義語である。の富豪、ヴァンサン・ボロレが所有メディアの編集方針に積極的に介入し、極右主義者のエリック・ゼムールをフランス大統領候補へと押し上げたことで、民主主義が危機的な状況に陥っていることに気づいた人も多い。
元『フィガロ』の政治記者であるゼムールは、フランス国外では手っ取り早く「フランスのトランプ」と称されることも多いが、演説や討論スタイルなどは似ても似つかない。プロレスラーにマイクパフォーマンスを教わったドナルド・トランプと対照的に、ゼムールは現在のフランス政界に並ぶものの見当たらない雄弁家であり、抜群の反射神経の持ち主である。彼の過激な思想については日本でもかなり紹介されるようになっているので、他に譲ろう。本稿の関心は、このようなモンスターを産み落としたフランスのメディア環境に絞られる。
ゼムールが「フランスの寡占メディアの落とし子」であることを、外国人に向けてわかりやすく紹介したものに、イタリアの『コリエーレ・デラ・セラ』によるフランソワ・オランド前大統領のインタビュー30注30:https://www.corriere.it/esteri/21_ottobre_30/francois-hollande-politica-uomo-libero-l-ideologia-ci-salvera-zemmour-come-grillo-79b2e9a6-38e5-11ec-8ce2-c94918111ac8.shtmlが挙げられる。このインタビューは2週間後に『ル・モンド』によって「逆輸入」の形で紹介された。以下、オランドの発言を含む抜粋となる。
こんなに迅速にメディアグループが誕生するなんて、滅多にあることではない。メディアグループがこんなにすぐに政治的意図に奉仕するのも、これが初めてに近い。(『チャレンジ』誌によると)フランスの長者番付14位に位置付ける実業家〔ヴァンサン・ボロレ〕が、出版分野にまで広がる反動的な一極をわずか数ヶ月で築き上げたのである。(…)政治闘争におけるヴァンサン・ボロレの虎の子の武器もジャーナリストだった。「人種差別の扇動」や、イスラム教徒への「憎悪の扇動」などで有罪となり、死刑制度およびペタン元帥のナチス協力の擁護者にして、対抗勢力、欧州連合、第五共和政憲法の敵、エリック・ゼムール。この人物こそが来るべき大統領選挙の台風の目となる。
立候補を正式表明する前から、ゼムールはリズム、言葉、論争を吹き込んできた。「ゼムールは、メディアグループによって支えられている一つの企業であり、それには財務結果が伴っている」と分析したのは、前大統領のフランソワ・オランドである。10月31日付のイタリアの日刊紙『コリエーレ・デラ・セラ』でオランドはこう言っている。「トランプはリアリティ番組からホワイトハウスに移ったが、彼は共和党の候補者だった。けれどもゼムールは一テレビ局グループの候補者なのである31注31:https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/11/16/l-opa-de-vincent-bollore-sur-la-presidentielle_6102316_4500055.html」。
フランスのメディア環境は、現在ここまで急速に劣化しているのである。
フランスの元老院(Sénat)もさすがに危機感を持ち始めたようで、今年の1月から主な寡占メディア所有者の公聴会を開いている。トップバッターとなったのはヴァンサン・ボロレで、フランス元老院の公式YouTubeチャンネルでその模様が公開されている32注32:https://www.youtube.com/watch?v=UtPwGBtjKuI。誰もが懸念している「このようなメディア帝国を作る意図は?」との質問への答えは「あくまで経済的利益の追求です」。編集方針への介入については、自身の権限は大したものではない、と矮小化し、質問がエリック・ゼムールとの関係に及ぶと「私が初めて会った時、彼はすでに有名人でした」とくる。こうしたやりとりが何の役に立つか私にはわからないが、やらないよりはマシなのだろう。
ちなみにボロレは近い内に、フランス最大の出版社であるアシェットや『ELLE』、『パリ・マッチ』などを所有するラガルデール・グループを買収すると言われており、フランスの出版関係者は警戒を強めているところである。
オリンピックからだいぶ離れてしまったが、マスメディアの凋落という同時代の世界的な流れがフランスでどのような展開を見せているのか、確認しないことには論を進められないことはお分かりいただけたと思う。
一方にはこのような比較的新しい大きな流れがあり、他方でテレビ登場前に遡るIOCをはじめとするスポーツ界とマスメディアの癒着は残り続けている。こうした状況で、自国開催のオリンピックについて質の高い批判的ジャーナリズムをマスメディアに期待することは、おそらく無駄なのだ。産業構造的に無理なのである。「河瀬直美事件」が私たちに見せつけたのは、そのことなのではないだろうか。
とはいえ元老院が公聴会を開くほどには、メディア環境劣化への危惧がフランスで高まっているのも事実である。そしてメディアが外部資本に頼り、編集の自治を失うことへの危機感はボロレとゼムールの接近よりもはるか前から存在している。
優秀なジャーナリストを多数抱えていた『ル・モンド』は、2010年末に通信大手Freeの経営者であるグザビエ・ニールに買収されているが、それ以前から経営が安定しない状況が長く続いていた。こうした中で元主筆のエドウィ・プレネルは『メディアパルト』、環境問題のスター記者だったエルヴェ・ケンプは『ルポルテール』といった独立メディアを設立し、その後それぞれ軌道に乗せ、後続のための道を開いている。
現在フランスでは、既存メディアの寡占状態を背景として新しい独立メディアが次々と生まれており、「活況を呈している」と言ってもいい状況にある。しかし報道の質と経営を安定させるのは簡単ではない。昨年10月には「窓を開き、独立報道機関を読もう」33注33:https://basta.media/concentration-liberte-presse-soutien-medias-independantsというタイトルの「支援依頼」とでも言うべきテクストが、署名団体となっている各独立メディアに一斉に掲載された。そこには「情報は一般的な商品とは異なることを積極的に認め、代替メディアを支援しなくてはならない。これは民主主義の根幹に関わる問題である」といったことが書かれている。
こうした独立メディアに、英語圏の有力メディアで見られたような「近代オリンピックそのものに対する根本的な批判」を期待できるだろうか?。
一つ確実に言えるのは、パリ五輪に抵抗する闘争はこれまで何度もこうした独立メディアに頼ってきたし、今後も頼っていくだろう、ということだ。その一例が、本連載の番外編として掲載した、今年5月に予定されている「反オリンピック国際集会」の呼びかけ文である。『ルポルテール』のような読者層の広い独立メディアに掲載してもらうことは、闘争の広がりを左右する極めて重要な広報活動である。
しかしこうした新興独立メディアに十分な取材力が備わっていないことも、また率直な事実である。そもそも寡占メディアの代替を務められるほど独立メディアが育っているなら、エリック・ゼムール旋風が体現している民主主義の危機は起こらない。『ルポルテール』が『ル・モンド』の代わりを務められないからこそ、元老院が公聴会を開くほどの危機感があるのである。
フランスの事情に詳しい読者はこう思われるかもしれない。でも『メディアパルト』はかなり育っているのではないか、と。確かにそうである。少なくとも、ロスチャイルドに買われた後で携帯電話通信サービス会社・SFRの手に落ちた『リベラシオン』よりは、『メディアパルト』の存在感の方が遥かに大きくなっていると言える。私自身、今後フランスで『メディアパルト』の成功例に後が続くことを期待してもいる。しかし大きく育てば育ったで、問題が生まれるのも事実だ。
フアン・ブランコという弁護士・文筆家は、『メディアパルト』の経営および編集方針は、独立メディアと呼ぶには相当微妙なものとなっている、と著作やソーシャルメディア34注34:たとえばこのスレッド。https://twitter.com/anatolium/status/1118903874088206336で述べている。それに対するエドウィ・プレネル社長の反論とブランコの言い分を検討することは私の手に余るのだが、本稿の関心に沿った傍証を紹介することでこの回を締めくくることにする。
本連載で以前に紹介した、オリンピックやスポーツを批判する著作をフランスで数多く出しているマルク・ペルルマン(パリ第10大学教授)は、『メディアパルト』の共同創設者、ローラン・モデュイが「スポーツと民主主義」という「入会資格の厳しいクラブ」の一員として収まっている写真を「左翼はオリンピック(La gauche est olympique)」35注35:https://alencontre.org/asie/japon/debat-la-gauche-est-olympique.htmlと題された記事に載せている。
この写真の撮影日は2017年6月17日。パリ五輪がリマのIOC総会で正式決定する3ヶ月前となるが、本連載「序」で述べた通りこの時期には「内定」している。撮影場所は在パリ英国大使館。フランス最大のスポーツ紙『レキップ』紙やスポーツ専門テレビ局・ユーロスポーツの記者など、名だたる「オリンピック・ステークホルダー」の面々に混じってローラン・モデュイもテニスウェアに身を包み、「法学部の学生」とクレジットされている息子(トリスタン・モデュイ)共々、エッフェル塔を模した「五輪招致期成ポーズ」を取っているのである。
ペルルマンのこの記事を読んだ時、私の長く抱えていた疑問が溶け、色々なことが腑に落ちたのだった。『メディアパルト』はパリ五輪に伴う都市開発については、かなり批判的な調査記事を数多く出している。オーベルヴィリエの「守るべき菜園」の闘争にも深く関与していたジャド・リンガールという記者は、オリンピック会場建設公社(SOLIDEO)内部における人種主義・女性差別主義を暴露する記事36注36:https://www.mediapart.fr/journal/france/180421/jo-2024-des-accusations-de-propos-racistes-et-misogynes-creent-une-crise-interneを発表している。
けれどもこうした記事は「近代オリンピックそのものに対する根本的な批判」には、あと数歩のところで至らないのである。『メディアパルト』によるパリ五輪に関する報道は全般的に「本来ならば素晴らしいものであるはずのオリンピックが、残念なことになっている」という論調となっている。リンガールによる「オリンピックのための資金は、住民のためにはほとんどならない」と題された記事もその例外ではなく、以下のような一文で締めくくられているのだ。「けれどもこうではなく、オリンピックは、セーヌ=サン=ドニ県が被る社会的・環境的な不正を是正する役に立てたはずなのだ37注37:原文では”Les JO auraient pourtant pu, au contraire, servir à rattraper les injustices sociales et environnementales que subit le territoire de la Seine-Saint-Denis”. https://www.mediapart.fr/journal/france/141021/jo-2024-l-argent-profitera-bien-peu-aux-habitants」。
自国開催を控える大手メディアに「近代オリンピックそのものに対する根本的な批判」を求めることが無理筋であることを、『メディアパルト』ほど雄弁に語っている例はひょっとしたら他にないのかもしれない。大会終了後に「反五輪デモの参加者は金銭で動員されていた」などというデマを流す必要すらないほど、反対派は見えないままにされるのではないか。パリ五輪が2年半後に迫る現在、私の胸中に去来するのはこのような不安なのである。
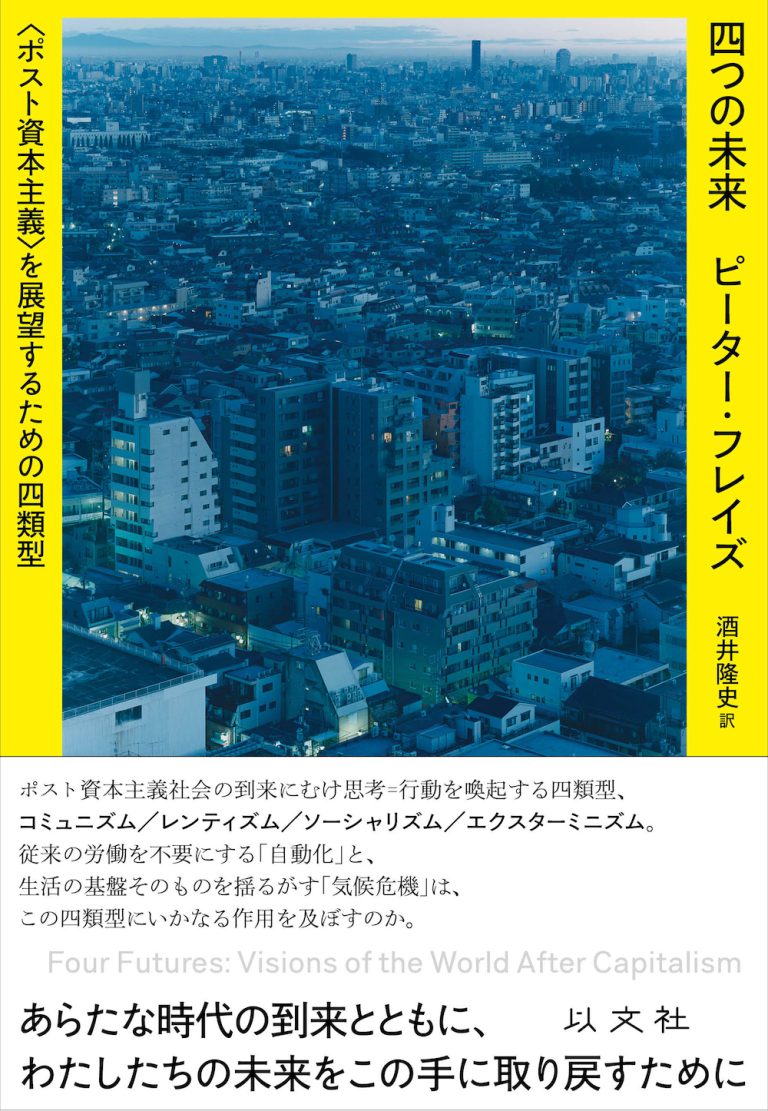

![Read more about the article ノン・エクスクルシーブ・ニューヨーク[第4回]/大崎晴地](http://www.ibunsha.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/20230722_142815946-1-768x513.jpg)