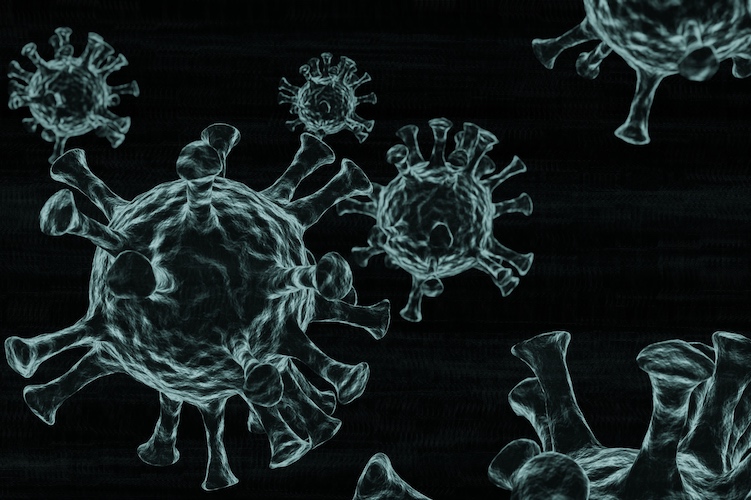〈黄色いベスト〉運動──私たちの足元で地面は大きく動いている(片岡大右 訳)
この運動は、異議申し立ての実践における大きな刷新の動きの一環をなしている──資本主義を思考する人類学者、デヴィッド・グレーバーが『ル・モンド』論説欄に分析を寄せた。
慣習的なカテゴリーをもってしては、現に起こりつつあることをまったく記述しえないということ。それが真に革命的な瞬間というものの特徴のひとつなのだとしたら、わたしたちは今まさに、革命的な時代を生きている。
〈黄色いベスト(ジレ・ジョーヌ)〉〔以下、時に「GJ」〕は、目下急速にその蜂起のクライマックスへと大またで向かいつつあるが、これまでこのドラマが新たな「幕」〔毎週土曜の行動がこのように呼ばれる〕を開くその度に、フランスの解説者たちは──ましてや外国の解説者たちは──、深い混乱を、いやさらには信じられないといった態度をさえ、示してきた。
思うにそれは、過去50年のあいだに、しかしとりわけ2008年のリーマン・ショック以降に、権力が、労働が、反権力の運動が、どのように変化してきたのかを考えるということに関して、彼らがほぼ全面的といってよい無能ぶりを晒しているからなのだ。知識人たちは大部分、こうした変化をほとんどろくに理解してこなかった。
彼らの混乱の原因について、以下に2つの示唆を行うことから議論を始めたい。
(1)金融化された経済にあっては、信用創造の諸手段の至近に身を置く人びと(本質的にいって、投資家とマネジメント階級)だけが、普遍主義の言葉を語りうる立場にある。その結果、個別の欲求や利害に基づく政治的要求はすべて、なにがしかのアイデンティティ政治の表明として扱われてしまう。だからGJの場合には、参加者らの社会的基盤からして、その要求は原(プロト)ファシズム的なものとして以外には想像されえないわけだ。
(2)2011年以降、大衆規模の民主的運動に参加することの意味をめぐる常識的な想定は、世界規模で変化した──少なくとも、そうした運動にいかにも参加しそうな人びとのあいだでは。
「垂直的」ないし前衛主義的な旧来の組織モデルは、水平性モデルの精神へと速やかに移り変わってしまった。そしてこの新たなモデルにおいては、(民主的、平等主義的な)実践とイデオロギーの両者は、つまるところ、同じものの二つの側面にほかならない。けれどもそれを理解できない人びとは、GJのような運動に対して誤った印象を抱くことになる。そうした運動は反イデオロギー的なものだ、さらには虚無主義的(ニヒリスティック)なものだと考えてしまうのである。
これら混乱した主張の背景には何があるのか、わたしの考えを以下に述べることにしたい。
深く反民主的な衝動
米国が1971年に金本位制を放棄して以来、資本主義の本性は深く変化した。今日では、企業の収益の大部分は、何かを生産することでもたらされるのではないし、何かを売ることとさえ関係がない。収益の大部分は、信用を、債務を、また「規制されたレント」を、操作することでもたらされるのだ。政府と金融界の官僚制的装置はあまりに密接に絡み合うようになったので、今や次第に区別し難いものとなっている。
富と権力──特に、貨幣を(つまり信用を)つくり出す権力──もまた、事実上、一体化しつつある。(このことに注意を促そうとして、われわれは〈オキュパイ・ウォール・ストリート〉の際に、「1%」について──つまり、富を政治的影響力に転換し、ついで今度は政治的影響力を富に転換しうる人びとについて──語ったのだった)。
それなのに、政治家もメディア解説者も、こうした新しい現実を一貫して認めようとしない(訳注1) 。公共の言説において租税政策が論じられる際、あたかもそれが今なお主として、政府があれこれの活動の資金を調達すべく収入増を図るための一手段であるかのように語られてしまうというのが、その一例である。
事実を見るなら、今日の租税政策はますます、(1)信用創造の諸手段が決して民主化されないように保証するための手段(公的に承認された信用のみが納税時に受け入れられるので)、そして(2)経済的権力をある社会的セクターから他の社会的セクターへと分配し直すための手段になっているというのに。
2008年以降、各国政府は新規の資金を金融システムに大量注入してきた。注入された資金は、悪名高きカンティロン効果のため、すでに金融資産を持っている人びとに向かい、またマネジメント階級のテクノクラート層という彼らの同盟者に向かい、とめどもなく流れ出していくことになった。フランスではもちろん、これらの人びとがまさしくマクロン派である。
こうした階級の構成員は、自分たちこそが可能なすべての普遍主義を体現する者だと感じているのだけれど、何が普遍的であるのかに関し、彼らの発想はしっかりと、市場に根を下ろしている。あるいはむしろ、次第次第に、市場と官僚制とのあの凶悪な融合体に根を下ろしつつあるのだというべきだろうか。そして両者のこうした融合こそが、「政治的中道」と呼ばれるものの中心をなすイデオロギーなのだ。
この新たな中道主義的現実のなかで、労働者たちはますます、普遍主義を体現することなど決してできない存在とみなされるようになっている。彼らには文字通り、そのための支払いをすること(アフォード)ができないのだから、というのがその理由だ。
例えば、ただただ自分が生き延びるための必要性に身を屈するのではなく、惑星の将来を配慮した行動をできるのかどうかということは、信用創出とレントの管理配分の今日的ありように直接由来する副次的帰結にほかならない。こうして、自分自身や家族の差し迫った物質的必要のことしか考えられないような状況にある者はみな、個別のアイデンティティを掲げているものとみなされることになる。なるほど、一部のアイデンティティ的要求は容認されるかもしれない(恩着せがましい尊大さをもって)。
しかし「白人労働者階級」のアイデンティティ的要求となると、これはただ、レイシズムの一形態とみなされることしかできないのである。同様のことは、米国でも見られた。そこでは、アパラチア山脈の炭鉱労働者たちがユダヤ人の社会主義者バーニー・サンダースに投票した事実を受け、リベラル派の解説者たちが、それはしかしとにかく、レイシズムの表現であることは間違いないと、懸命に主張したのだった。今日、ジレ・ジョーヌたちはファシストであるに違いない、彼らが自覚していないとしてもそうなのだと、奇妙な力説がなされているのと同じことだ。
こうしたすべては、深く反民主的な衝動の表れである(訳注2) 。
テクノクラート・マネジメント階級と労働者階級
「黄色いベスト」運動の成功──つまり、このほんとうに民主的で、さらには蜂起的でさえある政治現象が突然に発生し、たちまちに広まったこと──を理解するには、これまでおおむね指摘されてこなかった二つの要因を、考慮に入れるべきだと思われる。
第一の要因は、資本主義の金融化は、階級諸勢力の配置構造を刷新したという事実だ。何よりそれは、テクノクラート・マネジメント階級と労働者階級を対立させるのだが、前者はますます、職がなくならないように存在するだけの「くそくだらない仕事(ブルシット・ジョブ)」──新自由主義的再分配システムの一環をなす──のもとで雇われるものとなっている一方、後者の労働者階級(ワーキング・クラス)は、今日では「ケア階級(ケアリング・クラス)」として捉えたほうがよいような存在になっている。つまり今日の労働者階級とは、養育し、看護し、面倒を見たり支援したりする人びとなのであって、旧来型の「生産者」の色彩は弱まっているのだ。
デジタル化がもたらした逆説的な効果のひとつは、産業的生産を限りなく効率的なものに変えた一方で、それが保健や教育や他のケア部門の労働を、非効率なものにしてしまったということである。しかもそれには、新自由主義のもとで進んだ、資源配分の流れの管理職階級の側への転換(またそれに伴う福祉国家の縮小)というもうひとつの事実が組み合わせられる。
こうしたことの結果として、事実上どこにおいても、戦闘的労働運動の最前線には教師が、看護師が、介護施設職員が、救急医療士が、また他のケア階級の人びとが、見出されるのである。先週のパリでは、救急隊員らと警察の小競り合いが生じた。この衝突は、こうした新たな勢力配置の鮮烈な象徴と見ることができよう。
もう一度いうが、公共の言説は今のところ、こうした新たな現実に追いつけずにいる。とはいえいずれはわたしたちみなが、まったく新しい問題について、考え始めることを迫られるようになる。それは例えば、どんな職種を自動化できるのかという問題ではなく、どんな職種であればわたしたちは自動化を望み、どんな職種であれば望まないのか、という問題だ。
そしてまた、他の人間存在の直接の助けとなり、直接の利益となるような仕事であればあるほど支払いが少なくなる、そのようなシステムを、わたしたちはいつまで続けていきたいと思っているのか、という問題だ。
戯画化されてきた水平的構造
第二に、2011年の一連の出来事──〈アラブの春〉に始まり欧州の〈広場〉の諸運動を経て北米の〈オキュパイ〉に至る──は、これまでの政治的常識に重大な切断をもたらしたように思われる。全面的な革命の瞬間というものが、ほんとうに生じたのかどうかを知るには、ひとつのやり方がある。ほんの少し前には気ちがい沙汰とみなされていたアイディアが、突如として政治的生活の基本的前提になってしまっているということを、確かめればよいのだ。
例えば〈オキュパイ〉の場合、水平的でリーダーを置かない直接民主主義的な構造は、ほとんど普遍的なといえるほどの戯画化の対象になって、馬鹿げているとか、目に星が浮かんでいるとか、実際的ではないとか散々にいわれ、運動が鎮められるや、それこそが「失敗」の理由として取り沙汰されたのだった。たしかに、こうした構造は、エキゾチックなものに思われたのだろう。それはアナキズムの伝統のみならず、ラディカル・フェミニズムからも、さらには先住民の精神性(スピリチュアリティ)のある種の形態からも、大いに着想を得ていたのだから。
ところが、今や明らかなのは、この構造こそが、ボスニアから香港とクルディスタンを経てチリに至るまで世界の至るところで、民主的組織化の試みが初期設定(デフォルト)で採用するものとなっているということだ。何らかの大衆的な民主的運動が発生するや、今や人びとは、それがこのような形態を取るものと期待する。フランスでは、2016年春の〈夜に立つ(ニュイ・ドゥブー)〉の運動が、この水平主義的政治を大衆規模で受け入れた最初の例だろう。しかし、当初は農村と小都市の労働者たちが自営業者たちとともに始めた「黄色いベスト」のような運動が、自ずとこのモデルのヴァリエーションを採用するに至った事実を見るなら、それが今日、民主主義の本性そのものについての新しい常識になっていることがはっきりわかる。
知識人の前衛などいらない
この新しい現実を理解できていないように見えるほとんど唯一の階級は、知識人たちだ。〈ニュイ・ドゥブー〉の時、この運動の「リーダーシップ」を自任した人びとの多くは、水平的な組織形態というものはれっきとした組織形態なのだという考えを、受け入れることができないか、あるいはそうすることに乗り気ではないように思われた(彼らは単に、トップダウン構造の拒絶と全面的カオスのあいだの違いが判らなかったのだ)。
同じように、今日、左右の知識人は、ジレ・ジョーヌたちは「反イデオロギー」だという主張に固執している。理論と実践の統一が(それは過去のラディカルな社会運動においては、実践側よりもむしろ理論側に見出される傾向があったものだが)、今日では実践の側に存在しているのだということを、彼らは理解できないのである。
これら新しい運動は、知識人の前衛によってイデオロギーを与えられる必要など感じていない。なぜならそこには、すでにひとつのイデオロギーが備わっているのだから。知識人の前衛を拒絶すること、多様性を受け入れること、そして直接民主主義それ自体が、それらの運動にとってのイデオロギーである。
たしかに、これら新しい運動においても、知識人には一定の役割がある。しかしその役割は、これまでよりも少なく語り、多く聞くことに関わっているはずだ。
こうした新たな現実は、金と権力の関係であれ、民主主義の新たな理解であれ、「黄色いベスト」の次なる幕がどのようなものになろうとも、すぐに消え去ることはなさそうだ。地面はすでに、わたしたちの足元で、大きく動いてしまった。
だからわたしたちはおそらく、わたしたちの忠義がどちらに向けられているのかについて、考えてみるべきなのだろう──わたしたちは、金融権力の蒼ざめた普遍主義の側に立っているのか、それとも、日々行われるケアによって社会を可能にしている人びとの側に立っているのか。
訳注1 この文から段落末までは英語原文にのみ記載。
訳注2 『ル・モンド』ウェブ版のこの一文には、中道派の民主主義不信を各国の世論調査によって明らかにした以下の記事へのリンクが張られている。
https://www.nytimes.com/interactive/2018/05/23/opinion/international-world/centrists-democracy.html
解説:〈黄色いベスト〉と民主主義の未来/片岡大右
ジェラール・ノワリエルは、9月に刊行されたばかりの『フランスの民衆史』の結論を、「エマニュエル・マクロンとは、どんな未来の名前なのか?」と題した。
そこで歴史家は、共和国大統領の綱領的著作『革命』の内容を分析し、同書における民衆的諸階級の不在を指摘する。たしかにそこには「貧者」や「弱者」は登場するが、「労働者」は登場しない。「庶民層が言及されるのは、ただ解決されるべき問題としてのみであって、活用されるべき富としてではないのだ」。
革新は社会の上層からしかやって来ないと信じるマクロンにとって、歴史の変化に果たしてきた民衆の役割は決して理解されない。しかし実際には、上・中流階級は民衆的諸階級の活動や抵抗や価値観を様々な局面で受け入れ、こうして社会はしばしば、支配層が当初望んだのとは別様の発展を示してきたのだと歴史家はいう。
じっさい『フランスの民衆史』にあって強調されるのは、「ただ集合的な闘争のみが、人民に自らの運命の改善をもたらしてきた」という事実である。
こうした観点からするなら、マクロン政権──発足当初から、もっぱら少数の「ブルジョワ・ブロック」(B・アマーブル)を支持基盤とするがゆえの脆弱さは指摘されていた(片岡大右「予告された幻滅の記録」『世界』2017年7月号を参照)──が、尊厳を奪われたと感じた庶民層とのあいだの緊張を高めていき、広範な反対運動に道を開くのは時間の問題だったといえよう。
けれども、2018年11月17日土曜を「第一幕」とする〈黄色いベスト(ジレ・ジョーヌ)〉の運動は、従来の運動には見られないいくつもの特徴によって、内外の観察者の驚きや戸惑いを引き起こしている。
とりわけ注目されるのは、それが政治組織や労組と無縁の、むしろそれらに対する不信を背景とした運動であるということだ。そのこととも関わって、旧来の社会運動のようにパリ・コミューンや〈68年5月〉が参照されることは稀であり──とりわけ前者を継承するような歴史感覚は、活動家と知識人の世界では一般的ではない──、代わって活用されるのは、1789年の最初の革命と結びついた一連の象徴である。
こうして運動の現場では三色旗が翻り、《ラ・マルセイエーズ》が歌われる。革命史家ソフィー・ヴァニッシュは、後者の背景としてまったく非政治的な経験──サッカーの応援──を指摘しつつ、国歌が同時に革命歌でもあるというフランスの歴史事情が可能にした実践であるとしている(『メディアパルト』12月4日)。
しかし、当事者により選ばれた歴史的参照項とは別に、この運動に関してしばしば言及されるのは、英国の歴史家E・P・トムソンが18世紀の民衆暴動を説明するために提起した「モラル・エコノミー」の観念である(特に、サミュエル・アヤット「〈黄色いベスト〉とエコノミー・モラルと権力」)。
農民たちの暴動は、市場原理とは別の合理性を持った公正な経済観──生活必需品は適正価格で売買されるべきだといった──を背景としており、彼らはそれが権力者によって裏切られたと感じた時に立ちあがった。民衆諸階級の闘争が労働運動として制度化され、政治組織と結びつく以前の時代とのこうした比較は、たしかに〈黄色いベスト〉の今日的な性格の理解を助けてくれるように思われる。
ジェラール・ノワリエルは、早くも最初の行動の数日後(11月21日)にブログで透徹した分析を発表しているが、そこで次のように述べている──「民衆の抵抗は、こうして政治化されることで一定の枠組みと規律を獲得し、活動家の教育を可能にしたが、それと引き換えに人びとは、自分たちの力を政党と労組の指導者に譲り渡すことになった。」歴史家はこうして、〈黄色いベスト〉のような自然発生的運動が、SNSでの呼びかけを通し、瞬く間に全国──海外県・海外領土を含む──に広まった事実に歴史的意義を認める。「政党と労組の時代」は、過去のものとなったのかもしれないのだ。
もっとも、ノワリエルはこれら中間団体の地位の低下を、単に歓迎しているのではない。〈黄色いベスト〉を「視聴者民主主義」(ベルナール・マナン)の典型的所産とみなす彼は、主流メディアの決定的役割を強調するが、テレビ局がこの運動を初回から生中継し、「サイレント・マジョリティの前代未聞の運動」として扱った一因は、まさにこの反政党的・反労組的性格が好都合だからである(対照的に、2018年春の国鉄労組の闘争の報道は控えめなものにとどまったうえ、ストに憤慨する利用者の姿が無闇に強調された)。
それにまた、既存の中間団体のこうした排除は、ほかならぬマクロンの権力掌握の論理でもある。政党や労組に「回収」されるのを拒む〈黄色いベスト〉たちは、単に現政権の政治的対抗勢力から正当性を奪っているだけ、ということにもなりかねない。また枠組みと規律の不在は、レイシスト的、セクシスト的等々の逸脱に道を開くということもある。それでも歴史家は、この直接民主主義の驚くべき実践を、新しい現実のなかで政党や労組に何ができるのかを再考するための契機として積極的に受け止めるのである。
19世紀の遺産というべき既存の中間団体の厄介払いは、たしかにこの運動に両義的な性格を与えている。先に触れたアヤット論考が指摘するように、特定の共同体的価値観を前提とし、権力者との協約が回復されたとみなされるや収束する限りにおいて、モラル・エコノミーは保守的なものだ。
また、アントニオ・ネグリは、〈黄色いベスト〉という「マルチチュード」の力をその独立性のうちに認め、政治勢力化への危惧を表明しつつ、しかしそのままでも結局、「政治システムによって中和され、無力化されてしまう」だろうとして、政党とは別のかたちでの「組織化」の必要性を説いている(ヴァーソ社のブログ、2018年12月8日)。
さて、こうしたすべてとの対照によって浮き彫りになるのは、デヴィッド・グレーバーの『ル・モンド』論考(ウェブ版12月7日)の、確信に満ちて楽観的な調子である。一連の出来事は、弥縫的な救済の身振りを誇示する機会を与えることでかえって体制を安定させるものにとどまるのか、それとも、より大きな変革の前触れにほかならないのだろうか。
**********
初出:『世界』(岩波書店)2019年2月号。
転載を許可してくださった『世界』編集部のご厚意に感謝いたします。

![Read more about the article 人間狩り・奴隷制・国家なき社会[第2回]/酒井隆史×中村隆之×平田周](http://www.ibunsha.co.jp/wp/wp-content/uploads/2022/06/img_9784750352305_1-768x514.jpg)